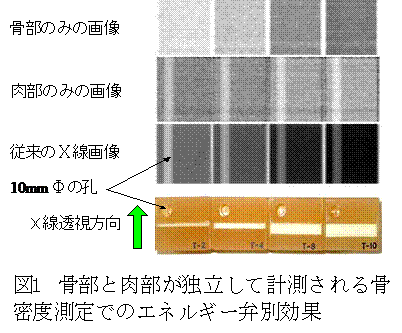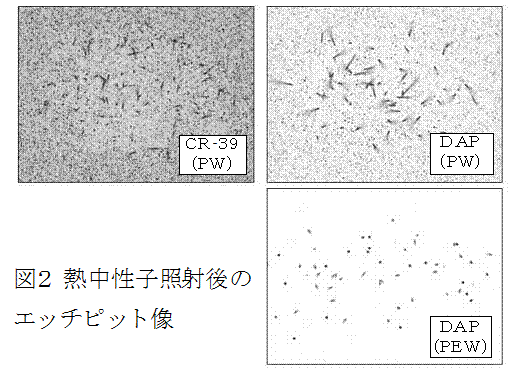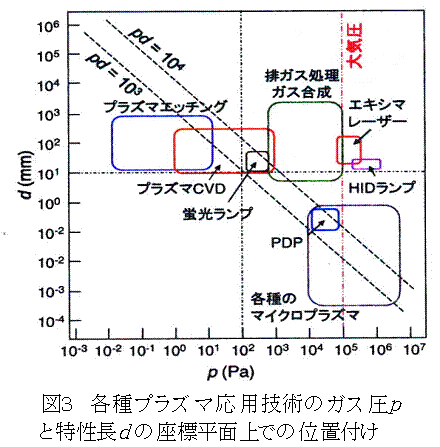�@
�@
�@
|
�v���Z�X |
�Ώہ^�ޗ� |
���߂���v�� |
|
�G�b�`���O |
���k�r�h �}�C�N���}�V�[�� |
�i�m���[�^���H �ٕ����i�`�䐫�j �ޗ��I�� ��ʐω��A������ |
|
�����`�� |
������ �U�d�� ������ ���`���� �L�@���� |
�ψꐫ�i�������j �ޗ��������� �E�ʐ��� ��ɑ���I�� |
|
�\�ʉ��� |
�@�B�I���� ���w�I���� ���w�I���� |
�C�ӌ`��Ή��� ��ʐϒ��ډ� �Ǐ����H�� |
���̃V�X�e���ł͓d�q�̑��s�������Z���A���σG�l���M�[��������̂œd���x�͒Ⴂ���A�����I�ȕ��d�͉\�ł���B��M���t�O���[�l���d���s�����߂ɁA���d���̃p���X����d�ɕ\�ʂ�U�d�̂Ŕ핢�����U�d�̃o�������d�̌`�Ԃ��̗p����邪�A�d���o�H�����k���₷���A�傫�Ȗʐςɋψ�ȃv���Z�X���m�ۂ��邽�߂̍H�v���K�v�ł���B
�C�̂̈��͂���荂���Ȃ�Ɛ}�R�Ō�����悤�ɋ�ԓI�X�P�[����������������Ɉڍs���邪�A�������ɔ����Č����K�X�̑؍ݎ��Ԃ��ʕb�I�[�_�[�ƒZ���Ȃ�B���̗̈�̓}�C�N���v���Y�}�ƌ�������̂ŁA���p�̕������ς���ė���B�v���Y�}�͖{���A�����������A���������̔������A�ςȗU�d�E���d���Ƃ����R�̗D�ꂽ����������B����ɔ�����Ԑ���g�ݍ��킹�����p�̓W�J���l�����A�P�̎g�p�ł̓}�C�N���W�F�b�g�ɂ��i�m���H�p�̃c�[��������A�܂��A�W�ώg�p�̃|�s�����[�ȗႪ�v���Y�}�f�B�X�v���C�ł���B�ŋ߂ł͎E�ۂ�ŋہA���Ȏ��Âւ̉��p�ȂǁA��Â�̕����̃v���Z�X�ɍL���钛���������Ă���B
���͂Ƌ�ԓI�ȑ傫���̊W�Ő������ꂽ���̍u���ŁA�v���Y�}�̐��E���悭�W�]�o�����B�Ō�ɏЉ�ꂽ�W�ω��ɂ�邢�����̐V�����@�\�̑n���ɍ���̖����c��ގv�����`������B
�S�D���ː����S�Ǘ��ƗL���Ή� �|��Õ���𒆐S�ɃZ�L�����e�B����ً}�����Â܂Ł|
������ȑ�w �Ǘ���C�ҁ@�e�n �@��
�����ł͇@���ː����S�Ǘ��Ƃ́A�A�j�ł͂Ȃ����ː��e���A�B�킪���ً̋}�픘��Ñ�A�̎O�ɂ��Ęb���Ē������B
�@�F���ː����S�Ǘ��͂��̗��p��s���ɐ������邱�ƂȂ��A���S�Ɉ��S���ė��p�o����悤�ɂ��邱�ƂŁA���S�����ɂ����R�~���P�|�V��������āA���p�҂�W�ҁA�����Ďs���̊Ԃ̐M���W��z�������������̂ł���B
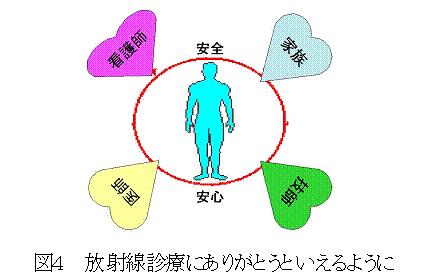 ���݁A��i���ł́A�픘�̂X�X�������҂ł��邪�A�w���̔����ȗ��A�֗����݂̂Ŏg���A���ː��̉e�������m�ł������ԂɁA��ÂɌg����������̈�҂�Z�p�҂����ː���Q�ɂ���ĖS���Ȃ��Ă���B���݂̈��S�Ǘ��̓��͂��̋]���̏�ɑꂽ�ƌ�����B������ɂ��Ă��A����܂ʼn��b�݂̂ŁA�L����݂ł��������ː��́A�����ɂ���ĕs���������炷���̂ƂȂ����B���̍ہA�́A���̂Ђǂ��Ώ��̎ʐ^���R�̐l�X�Ɍ����A���ׂĕ��ː��̂����ł���Ƃ��Ă��܂����B�M���ɂ��ƌ�����肻�̕����A�j�p��̂��߂ɂ̓C���p�N�g�����邪�A���̌��ʁA����ƕs���E�s�M���n��o����A�����āA���̌�ɋN�����������̌��q�F���̂ƁA�����āA���ȏ��E���Ƃ̌�����R�����g������������B���͂��̌�����ǂ������čs�����ł��邪�A�킽���͕��ː��̃��x���Ɖe���̊W�ɂ��āA���Ƃƈ�ʐl�̊Ԃŋ��ʂ̔F���������A�M���W����Ă���ŁA�Ȃ��g�����̗�����i�߂邱�Ƃ��Ǝv���B
���݁A��i���ł́A�픘�̂X�X�������҂ł��邪�A�w���̔����ȗ��A�֗����݂̂Ŏg���A���ː��̉e�������m�ł������ԂɁA��ÂɌg����������̈�҂�Z�p�҂����ː���Q�ɂ���ĖS���Ȃ��Ă���B���݂̈��S�Ǘ��̓��͂��̋]���̏�ɑꂽ�ƌ�����B������ɂ��Ă��A����܂ʼn��b�݂̂ŁA�L����݂ł��������ː��́A�����ɂ���ĕs���������炷���̂ƂȂ����B���̍ہA�́A���̂Ђǂ��Ώ��̎ʐ^���R�̐l�X�Ɍ����A���ׂĕ��ː��̂����ł���Ƃ��Ă��܂����B�M���ɂ��ƌ�����肻�̕����A�j�p��̂��߂ɂ̓C���p�N�g�����邪�A���̌��ʁA����ƕs���E�s�M���n��o����A�����āA���̌�ɋN�����������̌��q�F���̂ƁA�����āA���ȏ��E���Ƃ̌�����R�����g������������B���͂��̌�����ǂ������čs�����ł��邪�A�킽���͕��ː��̃��x���Ɖe���̊W�ɂ��āA���Ƃƈ�ʐl�̊Ԃŋ��ʂ̔F���������A�M���W����Ă���ŁA�Ȃ��g�����̗�����i�߂邱�Ƃ��Ǝv���B
���E�łQ�Q�O���l�ƌ������Ï]���҂̊Ԃœǂ܂�Ă���k�����������Ƃ����G���ɢ���鉼���p����Ɛf�f�p�b�s�ɂ��픚�ł��R�D�Q���������飂Ƃ̋L�����o�����Ƃ�����B���̉���Ƃ́u�������l�Ȃ��̒����e���iLNT�j�����v�̂��Ƃ����A����͖h��̂��߂̃c�[���ł����āA���Q�]����u�w�I�l�@�Ɏg�p���Ă͂����Ȃ����̂ł���B
�e���ƌ����Ӗ��ł́A�ȑO�A�h�u�q�i�J�e�[�e�����ÂȂǂ̑��́j�̊ԂɁA�畆�Ɋۂ������J���ƌ����悤�Ȍ����ȏ�Q�̎c�邱�Ƃ����������A���������o���̐ςݏd�˂̌��ʁA���݂ł͊i�i�ɉ��P����Ă���B���܂́A�D�w�̏ꍇ�ł��u�P�O�O���f���ȉ��Ȃ�َ��ɉe���Ȃ��v�ƂȂ��Ă��邪�A�ȑO����A���̂P�^�P�O�ł����ƃC���v�b�g����Ă���l���������߁A�D�P�ɋC�t�����ɂw�����������l���[���ɔY�ނ̂�����ł���B��Ís�ׂ͏�ɗՏ���̗��v�ƕ���p�̃��X�N��V���Ɋ|���Č��肳��邪�A���K���������Ƃ��d��ȊS���ł������ʂ̏ꍇ�A���X�N�͂����܂ł������ɂ��v�Z�ɂ����̂ŁA���Q�Ɋ�Â����̂ł͖������Ƃ�m���ė~�����B
�A�F����܂Ŏ�Ƃ��Ċj�e���i�m�e���j�����Ƃ���ė����Z�L�����e�B�����A�P�X�X�T�N�Ƀ��X�N���̌����Ń`�F�`�F���n�̃e���O���[�v���Z�V�E���P�R�V���B�����R���e�i�������悤�Ƃ�������������A�����ɏI��������̂́A���ꂪ���������ŕ��˔\�e���i�q�e���j�ւ̊뜜����̉����ė����B�X�D�P�P�Ȍ�ɂ̓A���J�C�_�̌v�悪���R�ɔ��o�������Ƃ������āA�h�`�d�`�łq�e���ւ̑Ή�����������A���{�ł��Q�O�O�S�N���獑���ی�@�ɓ������B�ŋ߂ł��A�|���j�E���ɂ��E�l����������A���������˔\�ɊW����̂��^�킵�����A�q�e���ւ̉\���������������Ƃ͊m���ł���B
�m�e���ɔ�ׂ�ƁA�q�e���́A�킸���ł����ː���������肵��������Ηe�Ղɂ�T����ƌ����Ӗ��ŕ~�����Ⴍ�A�܂��A��ɏq�ׂ����ː��ւ̌��������̂ŁA�l�̂ւ̉e�����܂����������ꍇ�ł��A�S���I�E�Љ�I�e���̑傫�����Ƃ����ł���B
�Q�O�O�Q�N�ɂh�`�d�`�́u���ː����ƈ��S�̃Z�L�����e�B�m�ۂɊւ���s���K�́v���߁A���̌�A�b��w�j�Ƃ��āwTECDOC-1355�x������B�킪�����A�����Ȋw�ȂɁu���ː����̈��S�ƃZ�L�����e�B�Ɋւ��錟���ɂ��Ă̂v�f�v���ݒu����A�Q�O�O�U�N�U���ɒ��ԕ����܂Ƃ߂�ꂽ�B
�q�e���̏ꍇ�A�}���̑g�D��Q�������N�������炍�r������픘�҂̓e�����X�g���܂߂ď����ŁA����ɂً͋}�����ÂőΉ����邪�A���\���r���ȉ��ƍl������唼�̐l�̏ꍇ�́A�[���ƍl������S���I�E���_�I�ȉe���A�܂��A�S�̂Ƃ��Ė��ȕ��]��Q�Ȃǂւ̑Ώ����K�v�ł���B
��Ƃ��āA�����{�݂̐����������ɂ���ĂP�`�T�̃J�e�S���[�ɕ��ނ��A���Ɋ댯�ȕ��ނ̂P�C�Q�ɂ��Ă͓o�^���x�ɂ��đ��݂�c�����邱�ƂɂȂ����B���{�ł̊Y���{�݂͂T�O�O���邪�A���̂W�����a�@�ɂ���A�K���}�i�C�t�i�����S�U�{�݁j�⌌�t�Ǝˑ��u�Ȃǂ��ΏۂƂȂ�B
�q�e���ł͂Ȃ����u���W���̃S�C�A�j�A���̂͂ЂƂ̋��P�ƂȂ����B����͔p�@�ɂȂ����a�@�̊����Ñ��u����Z�V�E���P�R�V���X�N���b�v����Ǝ҂ɂ���Ď����o����A�P�P���l�����ː��픘�ɂ���f�̑ΏۂƂȂ�A�S�X�l��250mSv�ȏ�A�S�l���}�����ː���Q�ɂ�莀�S�������̂ŁA�P�O�N�ȏソ���Ă��A�Z���ɕs���_�o�ǂȂǂ��c�����B
�B�F�ȑO�A���㌤�݂̂őΉ����Ă����ً}�픘��ẤA�i�b�n���̂����P�ɁA�S���̌��q�͎{�݂��u����Ă��錧�̊W�҂�ΏۂƂ��āA�ŋ߂T�N�ԂłT,�O�O�O�l�ɍu�K�E���K�����{�����B���ꂼ�ꏊ���a�@�ł̑̐��m�������҂��Ă���B
�������ː��u�Ђ��v�ł��A�P�ӂ̈�Ô픘�A���ӂ̃e���⎖�̂ɂ��픘�A�����픚�ȂNJ����͕ʂł������͓���������A�킽���͌����^����u�Ђ��v���g�킸�A�u���Ȃ��������ʂ́v�ƌ������Ƃɂ��Ă���Ƃ̌��t���琽���Ȑl����������ƂƂ��ɁA�Ȃ�قǂƔ[��������ꂽ�B
�T�D�Õ�������l�Êw�����̔N�㑪��Ɋւ���ŋ߂̘b�� �|�����펿�ʕ��͂ɂ��14C�N�㑪��̐M���x���߂����ā|
���É���w�N�㑪�葍�������Z���^�[�����@�@���� �r�v
�����搶�ɂ͍ŋ߂܂��܂����\���オ���āA�Ñ�̗��j�ɉ���I�Ȑi�W��^���Ă�������펿�ʕ��͖@�i�`�l�r�A�`���������������������@�l�������@�r������t���������������j�ɂ��N�㑪��@�ɂ��Ęb���Ē������B�搶�͑�P��̖{�V���|�W�E���Řb���ꂽ����M�V�搶�̂���q����ŁA����͂���Ȍ�̐i���ɂ��V�����b��ł���B
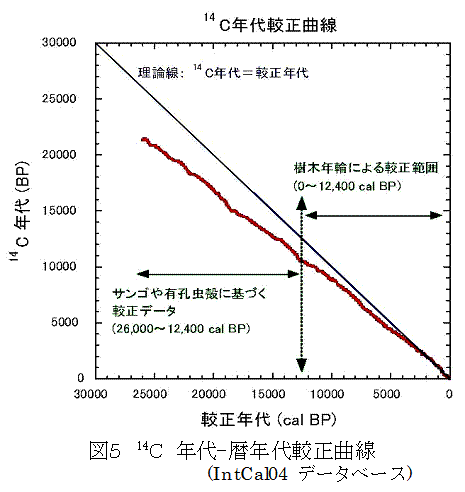 �F�����Ɋ܂܂�钆���q�Ƌ�C���̒��f���q�P�S�m�̏Փ˂Ő��������P�S�b�͖�T,�V�O�O�N�̔������ʼn�ς�����ː����f�ł���B���̂��߁A���̐����Ɖ�ς̃o�����X�ɂ���Ēn����Ɉ��̊����ő��݂��Ă���A����ȓ��ʑ̂��܂߂��Y�f�̑��ݔ�A�P�Q�b�F�P�R�b�F�P�S�b�́A���悻�P�F�O.�O�P�F�P�O�|�P�Q�ł���B�H���Ƃ��ĒY�f��̓��Ɏ�荞���������ʂƁA�Ȍ�A�P�S�b�͕⋋����邱�Ɩ������čs���̂ŁA���X�ω����邻�̑��ݔ䂩��A����̌o�ߎ��Ԃ𐔖��N���I�[�_�[�܂Ōv�Z�o����B�V�J�S��w�̂k�����������m�́A���̌�������ɁA�P�S�b�̃����ϑ��ɂ��Ñ��Ղ̔N�㑪��@���m�����i�P�X�S�X�N�j�A�m�[�x�����w�܂����^���ꂽ�i�P�X�U�O�N�j�B
�F�����Ɋ܂܂�钆���q�Ƌ�C���̒��f���q�P�S�m�̏Փ˂Ő��������P�S�b�͖�T,�V�O�O�N�̔������ʼn�ς�����ː����f�ł���B���̂��߁A���̐����Ɖ�ς̃o�����X�ɂ���Ēn����Ɉ��̊����ő��݂��Ă���A����ȓ��ʑ̂��܂߂��Y�f�̑��ݔ�A�P�Q�b�F�P�R�b�F�P�S�b�́A���悻�P�F�O.�O�P�F�P�O�|�P�Q�ł���B�H���Ƃ��ĒY�f��̓��Ɏ�荞���������ʂƁA�Ȍ�A�P�S�b�͕⋋����邱�Ɩ������čs���̂ŁA���X�ω����邻�̑��ݔ䂩��A����̌o�ߎ��Ԃ𐔖��N���I�[�_�[�܂Ōv�Z�o����B�V�J�S��w�̂k�����������m�́A���̌�������ɁA�P�S�b�̃����ϑ��ɂ��Ñ��Ղ̔N�㑪��@���m�����i�P�X�S�X�N�j�A�m�[�x�����w�܂����^���ꂽ�i�P�X�U�O�N�j�B
��������@�ł����P�ʂ̎������K�v�����A���̌�P�X�V�V�N�ɊJ�����ꂽ�`�l�r�@�ɂ��A���ė��鐔���Ȃ������q�ł͂Ȃ��A���݂����P�S�b�ڃC�I�������đ��肷�邽�߁A�y���ɏ��ʂ̂P�����ȉ��̎�������A��萸�x�̍����l�������邱�Ƃ��킩��A���N��ɂ͑�������p�@�����ꂽ�B���É���w�ł͂��̑�P���@����g���ė������A�Ȍ�A�R���s���[�^�[��������������Q������o�āA�Q,�O�O�O�N������͑�R����Ƃ������鏬�^���A�ቿ�i�����������A������c�ƂƂ����Ђ����ꂽ�B���ݐ��E�łU�O��A�����ł͂W�{�݂���A���̂����̂Q�{�݂��T�[�r�X��Ђł���B
�ŋ߂ł͈��m�����œW�����ꂽ�}�����X�̖̑тɂ��ĂP�W,�R�S�O�N�ƌ����l�Ă���B�����S�O�N�̊m�x�͂Ƃ������A�Â��Ȃ�قǒl���������Ȃ�̂ŁA���R�A���v�덷�������邪�A����ł��T,�O�O�O�N�Ȃ��}�i�P�V�`�R�O�j�N�̐��x�ŋ��߂���B��̓I�Ȏ����͍����̒Y������l���A�y��A�L�k�ȂǑ��l�ŁA��U�A�_�����Ăb�n�Q�K�X�ɕς��A����������A����Ɍő̂̃O���t�@�C�g�ɂ��đ��肷��B�Č����͏o�y�����╨�̂�������ʁX�ɏ������ē����l�̔�r�Ɋ�Â����A����Ɋm�x���グ�邽�߂ɁA�o���邾�������̎{�݂Ɏ����𑗂��đ�����˗����A����ꂽ���l�̕��ϒl�⒆���l���̗p���Ă���B
���̐V��������@�ɂ��ŋ߂̑傫�Șb��́A�Q,�O�O�R�N�̗��j���������قɂ�锭�\�ŁA��B�̖퐶�y��t�����̒l���]���̒l���Â��������Ƃł���B�y��ҔN�ɂ�鏇���͂悭�����̂Ŗ퐶����̎n�܂�͏]���̒�����T�T�O�N�����܂邱�ƂɂȂ����B
����قǐ��x���ǂ��Ȃ�ƁA���܂��܂ȍׂ����l�@���K�v�ŁA���Ƃ��A�������؍ނ̏ꍇ�A�N�ւ̂ǂ̕ӂ���ޗ��ɂ��Ă��邩�����ƂȂ�B�܂��A�P�S�b�N����A���ځA���j�N��ɒu���������邩�����ł���B����ɁA�C�ł��P�S�b�̑��ݔ䂪��C��菬�������Ƃ��������Ă���̂ŁA�C�Y���̉e�����傫���n���ł͔N�オ�Â��o��\��������B
��B�̏ꍇ�ɂ́A�����������͉������Ă��邪�A�Y�f�@�̐M���������߂邽�߁A���݂���̎��Ԃ����ڕ�����Ö̔N�֔N��X��Ȃǂ̔N���͐ϕ�����̔N����P�S�b�ɂ�鑪��N�Ƃ̊ԂŊr���Ȑ����쐬���ꂽ�B����ꂽ�Ȑ��͈̔͂͂Q���T��N�ɂ킽�邪�A���̌��ʁA�}�T�Ō�����悤���P�S�b�ɂ�鑪��l�͗��_�l����ɒႭ�o�Ă��邱�Ƃ��킩�����B���̗��R�͉ߋ��̒n���C�⑾�z�����ɕϓ��������ĉF�����̋������ς��A�P�S�b�̐�������肵�Ȃ��������Ƃɂ��ƍl�����Ă���A���̂����P�S�b����N�オ�U,�O�O�O�N�Əo���ꍇ�A���j�N��͂V,�O�O�O�N�ƌ������x���Ⴍ���ς��������邱�ƂɂȂ�B
�N�ւ����ʏo���鎎���̏ꍇ�́A���̂P�N�̐��x�Ō��߂��郁���b�g�ƁA�P�S�b�̑���@��g�ݍ��킹�āA�������x�̌��ʂ������邱�Ƃ�����B�P�S�b�E�C�O���}�b�`���O�ƌ������@�ŁA�����̔N�ւ��炦���鐔�\�N�Ԃׂ̍����ϓ��̃p�^�[���������̊r���Ȑ��ɋ��߁A���v����Ƃ��낪����A�\�畔���̔N�ォ��|�������������x�ǂ�����o����B�����E�k���N�����Ɉʒu���锒���R�R�[�̉ӗ��͐ϕ�����̎悵������P�O�O�N�̎��炪�����Y���ނ����̕��@�łX�R�T+�W�|�T�N�Ɠ���ꂽ�B����ɂ���āA�݊C�����X�Q�U�N�ɖŖS���������͔����R�̕��ł͂Ȃ����Ƃ���Ă��������ے肳�ꂽ�B
�ŋ߂͊j�����≻�ΔR���̔R�Ăɂ��e�����łĂ��邽�߁A�������Ƀ��C���̐����N�𐄒��������A�ƍ߂���݂̎��̂ɂ��āA�a���N�⎀�S�N�𐄒肷��ȂǁA�@��w�I�ȉ��p�������̑ΏۂɂȂ����Ƃ̂��ƂŁA���x�������Ȃ�ƈӊO�ȕ����ɉ��p���L���邱�Ƃ̂���_����ې[�������B
�U�D���ˌ��𗘗p���������H�Z�p�̌���Ƃ��̓W�J
���Ɍ�����w���x�Y�ƉȊw�Z�p������
�����@���� �@��
 ���́A�M�l�X�u�b�N�ɂ��ڂ�A�L�O�؎�ɂ܂œo�ꂵ��������1/1000�̃}�C�N���J�[���쐬���āA��܂�����Ă��镞���搶���}�C�N���}�V���쐬�̍ŐV�Z�p�ɂ��Ęb���Ē������B
���́A�M�l�X�u�b�N�ɂ��ڂ�A�L�O�؎�ɂ܂œo�ꂵ��������1/1000�̃}�C�N���J�[���쐬���āA��܂�����Ă��镞���搶���}�C�N���}�V���쐬�̍ŐV�Z�p�ɂ��Ęb���Ē������B
�Y�ƊE�̂����镪��ŕ��i�̔��������߂���悤�ɂȂ�A����܂ł́A�����i�������锼���̃v���Z�X�����p�������ʓI�ȓ����H�Z�p�i�l�d�l�r�A�Ō��P�O�ʂ����x�j���g���ė����B�������A���݂͎O�����A���A�V���R���ȊO�̍ޗ��ŁE�E�E�����߂��Ă���B���ہA�f�B�X�v���C�ł����O�����̗v�]�����鎞�ゾ���A����قǂ̖ʐς����H����̂͗e�Ղł͂Ȃ��B�Z���T�[�A�A�N�`���G�[�^�[�����l�ł���B
�����ł����͍��A���s���ƍ������ߗ͂������̕��ˌ��ɂ�郊�\�O���t�B�[�p�^�[���ɓt�����č�������^�ŁA�ˏo���^��i�m�C���v�����e�B���O�Ȃǂ����Č`��������A������k�h�f�`�i�k����������������������
�f�������������������������� �`�����������������j�v���Z�X��ڎw���Ă���B����͈�Ԕ�p�̂����镔�������^����ɒ��͂��A�ʎY���\�ɂ�����@�ł���B�ŋ߂ł́A���ȕւȂt�u�I���ł��A���Ȃ�̃��x���ɒB���Ă͂��邪�A���ˌ��I���͂P�`�Q�~���̐[���肪�o���A�\�ʂȂ�i�m�I�[�_�[�̃p�^�[�������\�ȕ��L�����H��i�ł���B
�g�p���Ă�������͂r�o���������W�̂��ɂ��镺�Ɍ�����w�����̒��^���ˌ��{�݂m���� �r�t�a�`�q�t�ŁA�G�l���M�[�͉��H�p�ɍœK�� �P ����тP.�T�f���u�̓�̃��[�h�ʼn^�]���Ă���A�\�ȘI���T�C�Y�͂`�S�Ƃ������E�ő�̖ʐςŁA�������A�����A�X�y�N�g��̃V���[�v�Ȏd�オ�肪������B
���݁A�ˏo���^�̒i�K�ł͒����g�z�b�g�G���{�b�V���O�@����X�������Ă���B����͋��^�Ǝ����V�[�g���K���X�]�ډ��x�ȏ�ɏ������ĉ����t���A�����g�̃A�V�X�g���ʂɂ���āA��C���ł����`���Ԃ�^�Ɠ����x�܂ŏk�߂邱�Ƃ��o����B
��̓I�ȃf�o�C�X�Ƃ��Ă͑����̉�Ђ���̗v��������A���܂��܂Ȑ���Ⴊ����B���Ƃ��Γd���^�}�C�N���A�N�`���G�[�^�[�̂��߂ɂP�����~�O.�V�������̃{�r���ɂT�O�����̃R�C�����쐬�����B�i�}�U�j�܂��A���o�͋��ɂW�{�̌��X�C�b�`�ł͂��ꂼ��̌��H�ɑg�ݍ��ރ~���[�x�ǂ����^�o�����B
���ː����p�̊ϓ_�ł͂w���^���{���v������B�w���̕����ɂ��z�����̓����g�Q���ʐ^���j���ɗ��p����邪�A���̂̓�g�D��L�@���Ɋւ��Ă͊��x���ǂ��Ȃ��B����A�g�����̒���`��鎞�A�������ς�邽�߂Ɉʑ����ω����邪�A���̃V�t�g�ʂ�����C���[�W���O�͉\�ł���B���̑��ݍ�p�̋����͂قƂ�nj��q�ʂɂ��Ȃ��̂ŁA���̑g�D�ł͂R�������x���オ��B�摜���ɂ͓��߂��ė����������̊Ԋu�ɒu������̉�܊i�q�ɒʂ��Č���郂�A���Ȃ𗘗p����B���e������ω������Ȃ���A�ʑ����̌v�����J��Ԃ��A�O�����ώ@�iX��CT�j���\�ɂȂ�B
���̑��u�ł́A��܊i�q������ΏۂŁA�ڕW���A�����ޗ��Ƃ����Q�O�����~�Q�O�����̕��ʏ�ɁA���C���ƃX�y�[�X���ꂼ��̕����S�����A���݂Q�O�����̃p�^�[�����쐬���邱�Ƃɒu���A�قڂ��̖ړI��B�������B�}�V�͊����������u�ɂ��L�@�ޗ��̉摜�ł���B�f�ʂ͂������b�o�t����ɂ����̂ł���B
�P�����ɂT�O�����̃R�C���͂����ɂ��}�C�N���f�o�C�X�炵��������₷���Ⴞ�Ǝv�����B�ʑ����̉摜���ɂ͐V�������オ������ꂽ�B
�V�D���o�b�N�O���E���h���ː��n��Z���̐��F�̒����Ŕ���������ʕ��ː��̌��N�e��
���ː���w����������
���_�������@���c
�@�E
���c�搶�ɂ͊����ː����ʏ�̂T�{�قǍ����n��ɏZ�ސl�̐��F�ׁ̂A�ɂ߂ĒႢ���ʂł̊ϑ����ʂ����Ƃɂ��āA�������ė������ː��̐����e���ɂ��Ęb���Ē������B
���F�ُ̈�̓}�E�X�̔����a�זE�̂X�T���ɂ���A�l�̏ꍇ�ł��A�ُ킪�����قnj�ɃK���Ŏ��ʐl�������ȂǁA�a�C�Ɛ[���֘A����������B����A�l�̃����p���́A���ː������������ꍇ�A�̂ɉ��̒��������Ȃ��Ⴂ���ʂł����F�ُ̈킪����A�������A���̂قƂ�ǂ��זE��������Ȃ��f�O���ɂ��邽�߁A���ُ̈�́A�����Ƃ����Q�O�N�ʂ͂��̂܂ܒ~�ς����̂ŁA�����ː��̉e��������̂ɕ֗��ȍזE�ł���B
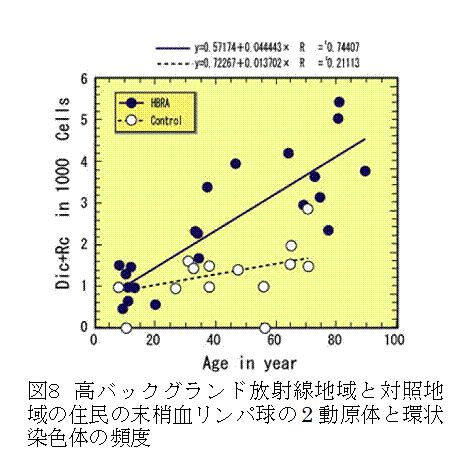 ���`�ɋ߂������L���Ȃ̗z�]�s�Ɏ��R���ː����ʏ�̂R�`�T�{�̒n��i�g�c�q�`�C�g������ �c������ �q���������|�������� �`�������j������B��Ƒ��������A�l�̈ړ����قƂ�ǖ����Ƃ���ŁA�N��Ɛ��ʂ̈ˑ������͂����肷��Ɗ��҂����B�����ɉ��S�������C���L���x�[�^�[�ȂLj�̑��u����������ō̌����烊���p���̒��o�A�|�{�A�Œ�܂ł��s���A���{�Ɏ����A���ĕW�{�����A���F�ُ̈���v�������B�̌��͍����ʈ�łW�Ƒ��A�Ώƒn��łT�Ƒ�����s���A�P�l������Q�U�O�O�זE�i���F�̐��ł͂��̂S�U�{�j�ɂ��Ē��ׂ��B
���`�ɋ߂������L���Ȃ̗z�]�s�Ɏ��R���ː����ʏ�̂R�`�T�{�̒n��i�g�c�q�`�C�g������ �c������ �q���������|�������� �`�������j������B��Ƒ��������A�l�̈ړ����قƂ�ǖ����Ƃ���ŁA�N��Ɛ��ʂ̈ˑ������͂����肷��Ɗ��҂����B�����ɉ��S�������C���L���x�[�^�[�ȂLj�̑��u����������ō̌����烊���p���̒��o�A�|�{�A�Œ�܂ł��s���A���{�Ɏ����A���ĕW�{�����A���F�ُ̈���v�������B�̌��͍����ʈ�łW�Ƒ��A�Ώƒn��łT�Ƒ�����s���A�P�l������Q�U�O�O�זE�i���F�̐��ł͂��̂S�U�{�j�ɂ��Ē��ׂ��B
���ː��́u�]���v�Ɓu���́v�Ɩ��Â���ꂽ���L�̐��F�ُ̈���P�F�P�̔䗦�ŗ^���邱�Ƃ��m���Ă��邪�A�O�҂͐V��ӂ≻�w�����ȂǁA����I�ȕψٌ��ɂ���Ă������B�����͌��݂̋Z�p��p����Ό������ł͂������ʏo���A�Q�N������ŊJ���������x�̍������u�Ōv�������B
�}�W����A���ː��ɓ��L�Ȑ��F�ُ̈�̐��͐��ʂ̈قȂ�n��̍����͂�����ƕ\���Ƌ��ɁA�N��ɒ����I�Ȕ��W�������Ă���A����ʂł�臒l�͌����Ȃ����Ƃ�������B
����A�}�X�͐�����̂��ׂĂ̕ψٌ��̉e���ɂ�錋�ʂŁA�q���ɔ�ׂč���҂̕ϓ����͑傫���A�R���g���[���n��Ƃ̍��͂قƂ�ǔF�߂��Ȃ��B���������āA�ʏ���T�{���炢���������ː��̉e���͑��̊��ψٌ��̉e�ɉB��Ă��܂��Č��o�o���Ȃ��ƌ��_�����B
��������w�ɂ�铯�n��ł̈�w�����ł��A��V�ُ��K���A�����a�ɂ��ăR���g���[���Ƃ̍��͖����A���ǁA��������ʂł́A���ː��ɂ����F�ُ̈�ƕa�C�Ƃ̊֘A���͌����Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ����B
�ꖇ�̐}���쐬����̂ɂ��ꂼ��R�N������ƌ����A�c��Ȏ��Ԃ����������d�����ƌ���ꂽ���A�{���A���v�I�Ȑ��_�ɂȂ肪���̊����ː��Ɛl�ԂƂ̐ړ_���炱��قǂ��k���Ȍ��_�������o���錤�������邱�Ƃɋ������B
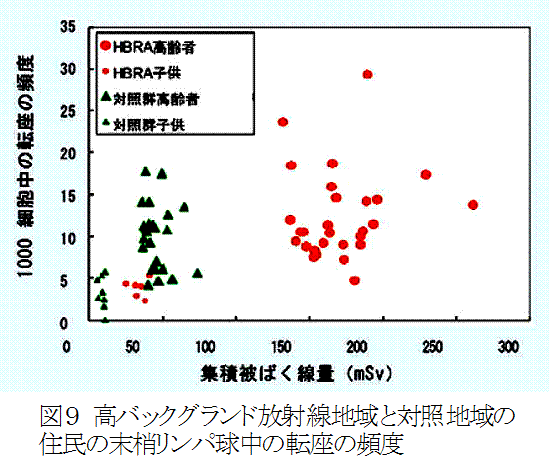
�W�D�ÓT���ː������w�q�����w�ʼn��� �|���t�G���J�C���h���m���Â�Ł|
���s��w���_�����E
�i���j�̎��������C�������@���C ���i
���C�搶�͍זE�ɏC���\�����邱�Ƃ������G���J�C���h���m�̂���q����ŁA���̌��ۂq���x���Ő������邱�Ƃɒ��킵�A�����Ȑ��ʂ����߂�ꂽ�B�����ł͂����D�~�̈�[������Ē������B
�זE�ɕ��ː����Ǝ˂��鎞�A��x�ɕ����ďƎ˂���ƁA��x�ɑS�ʏƎ˂����ꍇ�ɔ�ׂĐ������̏㏸��������B����͍זE�ɕ��ː��̑������C������\�͂����邱�Ƃ��Ӗ����A�����҂̖��O�Ɉ���ŃG���J�C���h�ƌĂ��B�܂��A���B���ɂ���זE�ɏƎˌ�A�����ɓ����t�ɒЂ���ƌ������̃X�g���X��^����ƁA�قƂ�ǂ����ʏꍇ�ł��A�����x��ĒЂ���Ƒ����������c�錻�ۂ������A�C���͔��ɑ������Ƃ����������B��ʂɁA�Бΐ��\���̐������Ȑ��͒����I�����A�قƂ�ǂ̍זE�ł͏����Ɍ��̂��鏬�����X�Ŏn�܂�B����̓G���J�C���h�������Ȃ��זE�ł͌���Ȃ��̂Ō��̉Ƃ�������B
���̂��鐶���Ȑ��́A���_�I�ɂ͕W�I����������Ƃ���A������W�I�_�Ő�������邪�A�����ɏC���̊T�O�͓����Ă��Ȃ��B�����Ȍ�S�O�N�ԁA�v���̌����͑�����c�m�`�̗���������d���ؒf�iDSB�C�c���������� �r���������� �a���������j�������Ƃ̐��_�͂��邪�A�G���J�C���h�ɂ��āA���q���x���̗����͂قƂ�ǐi�܂Ȃ������B����͂c�m�`���q�����܂�ɂ��傫���A�����Ɋւ��킸���Ȑؒf�����m�����i�������A�������A�����̂c�r�a����������悤�ȑ���ʂ��Ǝ˂��Ă��A���̂قƂ�ǂ��Z���ԂɏC������Ă��܂�����ł���B
����������镪�q���x���̋@�\�𖾂Ɏ������w�i�ɂ́A���̂P�O�N�قǂ̊ԂɁA�c�r�a�C���ɂ͂Q��ނ̍y�f���֗^���Ă���ƕ������ė������Ƃ�����B���̈�͏C���ɓ������āA�Ƃ肠�����ꂽ�����𐳔ۂ̔��f�����q���ł��܂����^�C�v�̂��́i�m�g�d�i�C�m���� �g������������������ �d���� �i�������������j�ŏC���m���͒Ⴂ�B���̈�́A���̖��������Ɠ����c�m�`��@�������o���A������Q�Ƃ��Ȃ���C�����鑊���g���i�g�q�C�g������������������ �q�������������������������j�ŁA�C�������͂P�O�O���ɋ߂��ƍl�����Ă���A���ꂼ��Ɋ֗^�����`�q�Q�͑O�҂��j�t�V�O�A�j�t�W�O�A�c�m�`�o�j�����ȂǁA��҂͂q�`�c�T�P�A�q�`�c�T�Q�A�q�`�c�T�R�Ȃǂƕ����������Ă���B
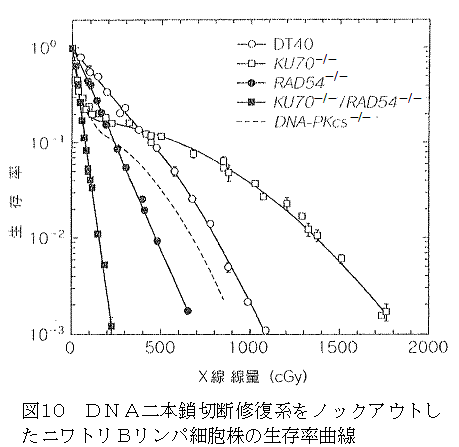 ����ɁA�����̒[���ƂȂ����̂̓j���g���̂a�����p�זE�ɁA����̈�`�q�������m���Œu����������ς��̊������݂���Ƃ̕i���c�r�ꋳ����A�����j�ɐڂ������Ƃł���B�����ŋ����������Ă��A���̐e���c�s�S�O�����ƂɁA��q�����Q��ނ̏C���n�c�m�`�Ɋ֗^�����`�q�����ꂼ�ꌇ���������ψي��i�j�t�V�O�|/�|�A�q�`�c�T�S�|/�|�j�Ƃ��̗�����������������d���������������邱�Ƃɐ��������B
����ɁA�����̒[���ƂȂ����̂̓j���g���̂a�����p�זE�ɁA����̈�`�q�������m���Œu����������ς��̊������݂���Ƃ̕i���c�r�ꋳ����A�����j�ɐڂ������Ƃł���B�����ŋ����������Ă��A���̐e���c�s�S�O�����ƂɁA��q�����Q��ނ̏C���n�c�m�`�Ɋ֗^�����`�q�����ꂼ�ꌇ���������ψي��i�j�t�V�O�|/�|�A�q�`�c�T�S�|/�|�j�Ƃ��̗�����������������d���������������邱�Ƃɐ��������B
�}�P�O�͂������g���čs�����T�^�I�Ȏ����̃f�[�^�ł���B���Ғʂ�q�`�c�T�S�|/�|�Ɠ�d�������͐e���ɔ�ׂĂ��̏����Œ�R�����Ⴍ�Ȃ��Ă���B����ɑ��Ăj�t�V�O�|/�|�͓��قȌ`�ŁA���ʂ��Ⴂ�Ƃ���ł͊��������A���ʂ���������ɂ�āA�e����萶�������ǂ��Ȃ��Ă���B���͂��̓�̌��������A�זE�̑Ε��ː����͕�������̎����ɂ���đ傫���ς�邱�Ƃ��ǂ��m���Ă���̂ŁA�����Ŏ����𑵂��������������Ȃ����B���̌��ʁA�C���m���̒Ⴂ�j�t�͑S����ʂ��đ��݂��邪�A���ꂪ�قڂP�O�O���ɋ߂��q�`�c�͓�d���̑����o���オ�鎞���ɂ̂ݑ��݂������Ƃ�������A�}�P�O��������邱�Ƃ��o�����B�܂�A�e���͏C�����̍�����d�����̎����ł��j�t���q�`�c�Ƌ������邽�߁A�������ďC������������̂ɑ��A�j�t�V�O�|/�|�ł͂q�`�c���̓ƒd��ɂȂ�A�S�̂Ƃ��Ē�R�������܂�̂ł���B����ʂł͋ɒ[�Ɋ��̍���������ɂ���זE�̎����ڗ��Q����������Ă���ƍl������B�}�̎����͂��̍l���Ɋ�Â��A�e������̑��ݔ䗦�Ƃ��ꂼ��̍y�f�̏C�������Ȃǂ����肵�Čv�Z�������̂ŁA����قǂ̃t�B�b�e�B���O�ɐ��������̂͐��E�Ŏn�߂Ăł���B
���̗��������Ƃɖ�P�f���^���������x�̒Ⴂ���ʗ��Ō�����\�ׂ��Ƃ���A�e���Ƃq�`�c�T�S�|/�|�͂�����������ʗ��̏ꍇ���ǂ��Ȃ��Ă���̂ɑ��A�j�t�V�O�|/�|�ł͓�d�������Ɠ����̈������ʂƂȂ�A����ʗ��ł͂m�g�d�i�C���n���d�v�ł������Ƃ����������B�Ȃ��A���̃��x���ł��A����ɐ��ʗ��������čs���Ə������\���オ���čs���A�ꌅ���炢�Ⴂ�Ƃ���ŕs�A���ȉ\�̏㏸�������A����ɕʂ̏C���n�̑��݂��������ꂽ�B����ɂ��Ă͂T�R�a�o�P�Ɩ��t����ꂽ�y�f�ɂ��Ă̕�����B
���̑��A�d���q�Ȃǂłk�d�s�̑����Ƌ��ɑ傫���Ȃ鐶�����ʂɂ��Ă̍l�����Ȃǂ��Љ�ꂽ���A�C���y�f�Ɛ��������̊W�����q���x���ł����܂ł킩��A�K���̕��ː����Î��ɗL���Ȗ�̐v�ɂ������Ɏ肪�͂������Ȉ�ۂ����B�́A�d�������������m�̘_���ɐڂ��čזE�ɉ\�����邱�Ƃ��͂��߂Ēm��A������ۂ����M�҂����A���̈�`�q���x���̃��J�j�Y���������܂ŕ����������ƂɊ������o���A���̐��ʂm�ɕ���̂��P�����̍��ŊԂɍ���Ȃ������Ƃ����G�s�\�[�h�ɂ���Č����̐��E�Ɉ����߂����v���������B
�i���c�L�j
�@
�@
�@