第52回放射線科学研究会より(聴講記)
表記研究会は平成25年10月25日(金)13:30から19:00までサンエイビル(大阪市中央区南船場)において開催された。今回の講師は義家敏正氏(京都大学原子炉実験所)、井上博之氏(大阪府立大学大学院)、大津留 晶氏(福島県立医科大学)及び二宮和彦氏(大阪大学大学院)であった。なお、講演会終了後、講師の皆様にご出席頂き、同所にて技術交流会を行った。
1. エネルギー粒子による金属の照射損傷メカニズムを探る
京都大学原子炉実験所研究員 京都大学名誉教授 義家敏正
講師の義家先生は、長年にわたって、原子力材料の照射損傷の研究に携わってきたこの分野での第一人者である。今回、その集大成ともいえる研究成果をまとめて拝聴できたのは、筆者にとっても大変有益であった。講演では、まずはじめに、高エネルギー荷電粒子(イオンビーム、電子ビーム)や中性子による材料照射効果研究の概要説明があり、それは、入射粒子と材料との相互作用の基礎研究から原子力材料の放射線による劣化機構の解明と耐放射線材料の開発、そして、放射線を用いた材料創製、材料分析評価、と多岐にわたるものである。そのあと、金属の照射損傷構造からどのような照射損傷メカニズムを知ることができるか、いくつかの例を挙げながら解説された。最初の話題はカスケード、サブカスケード損傷に関するものである。
銅、銀、金といったFCC金属において、14MeV中性子照射したときの損傷状態を電子顕微鏡で観察した結果を議論した。重イオンや中性子照射の場合、それらによってはじき出された原子(PKA:Primary
Knock-on Atom)のエネルギーが大きいため、それが次々と他の原子をはじき出してある領域に多くの欠陥が生ずる。これをカスケード損傷と呼ぶ。PKAのエネルギーが十分大きければ、カスケード損傷はサブカスケードに分裂する。図1は、金、銀、銅におけるサブカスケード(白い点)とカスケード(丸で囲んだ領域)である。ターゲット金属の原子番号が小さくなるにしたがって、カスケードは広くちらばるが、これは、原子番号の小さい原子ほど散乱確率が小さく、移動距離が長くなるというラザフォード散乱の特徴によって説明できる。次に、核分裂中性子照射と核融合中性子照射の差異に関する解説があった。原研(当時)の材料試験炉(JMTR)からの中性子は1−2MeVにスペクトルのピークを持ち、一方、米国ローレンスリバモアのRTNS−IIからのD−T反応による中性子は14MeV のエネルギーを持つ。この2種類の中性子を同じdpa値(同じ弾性的付与エネルギー量)だけ照射した金で比較すると、核融合中性子(14MeV)で照射したほうが、形成された欠陥の大きさは大きく、また数も多い。このことは、dpaが必ずしも照射損傷を評価するうえで十分よいパラメータではなく、PKAスペクトルを考慮する必要があることを示すものである。さらに、自由点欠陥FMD(Freely
Migrating Defects)の量を、転位の形状変化から見積もる方法も示された。
次に、近年話題になっている格子間原子欠陥集合体の1次元運動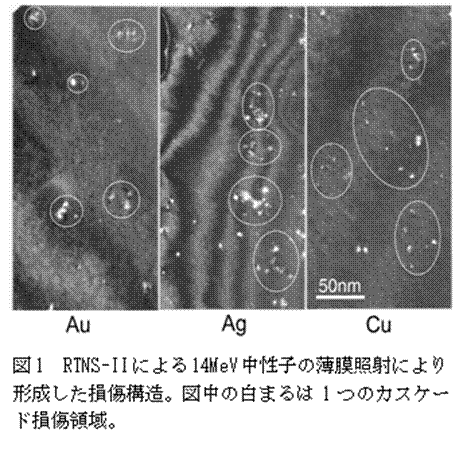 に関する説明があった。格子間原子は集合体として格子間型転位ループを形成することは知られているが、この転位ループが超高圧電子顕微鏡下での電子線照射その場観察において1次元運動を行うことが観察された。この1次元移動の機構は、分子運動学法による計算機シミュレーションによって明らかになった。すなわち、照射損傷としてフレンケル対(格子間原子と原子空孔の対)だけでなく、格子間原子の1次元集合体(クラウディオン)がカスケード損傷内で生成し、原子の稠密方向に移動するのである。格子間型転位ループの1次元運動の発見は、格子欠陥分野における新しい基礎的知見を与えただけでなく、原子力材料の照射効果研究にも大きな影響を与えた。その1つがボイドの生成機構である。ボイドは原子空孔の集合体であり、原子力材料の強度特性に大きな影響を与える。普通は、刃状転位のバイアス効果により原子空孔がマトリックス内に過剰になり、ボイドが発生すると考えるが、刃状転位がなくともボイドが発生することがある。
に関する説明があった。格子間原子は集合体として格子間型転位ループを形成することは知られているが、この転位ループが超高圧電子顕微鏡下での電子線照射その場観察において1次元運動を行うことが観察された。この1次元移動の機構は、分子運動学法による計算機シミュレーションによって明らかになった。すなわち、照射損傷としてフレンケル対(格子間原子と原子空孔の対)だけでなく、格子間原子の1次元集合体(クラウディオン)がカスケード損傷内で生成し、原子の稠密方向に移動するのである。格子間型転位ループの1次元運動の発見は、格子欠陥分野における新しい基礎的知見を与えただけでなく、原子力材料の照射効果研究にも大きな影響を与えた。その1つがボイドの生成機構である。ボイドは原子空孔の集合体であり、原子力材料の強度特性に大きな影響を与える。普通は、刃状転位のバイアス効果により原子空孔がマトリックス内に過剰になり、ボイドが発生すると考えるが、刃状転位がなくともボイドが発生することがある。
これは、格子間原子集合体が1次元運動してカスケード損傷領域から拡散し、原子空孔が残ることで説明できる。講演の最後に、加速器駆動システム(ADS)において、核破砕中性子による照射損傷構造を考えるうえでも、カスケード損傷の概念は重要であることが示された。PKAエネルギーが高い場合でも照射損傷の基本がサブカスケードであるとすると、1つのサブカスケード内での現象をシミュレーションすればよい。この考えに基づいて、ミクロな照射欠陥構造から機械的性質変化までのマルチスケールモデリングが構築された(図2)。図に示すように、PHITSコード、MD,反応速度論などを組み合わせて、ミクロな欠陥構造からマクロな機械的性質まで一貫した計算ができることが示された。
国内の発電用原子炉の多くが高経年化時代を迎え、放射線の原子力材料への影響を正確に把握することは今後ますます重要になってくる。今回の講演で示されたような照射効果の基本的理解の積み重ねが今後とも必要不可欠であることを再認識させられた講演であった。 (岩瀬彰宏 記)
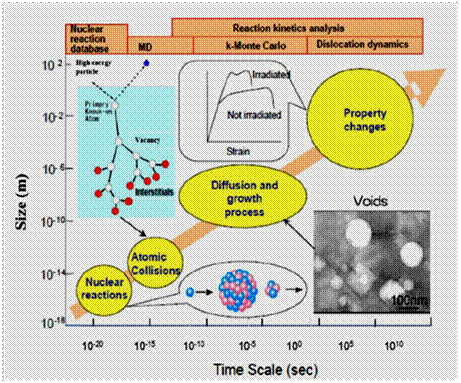
図2 高エネルギー陽子による照射損傷のマルチスケールモデリング
2. 地層処分環境での炭素鋼オーバーパックの耐食性
大阪府立大学大学院工学研究科 井上 博之
福島原発の事故以来、核燃料廃棄物の処分が改めて関心を呼んでいる。講師の井上先生は、長年にわたり使用済み核燃料から発生する高レベル放射性廃棄物を密閉する金属容器(オーバーパックとよぶ)の耐食性を研究してこられたこの分野の第一人者である。また最近は、福島原発事故に関連して、圧力容器、格納容器材料のガンマ線・海水複合環境下での腐食挙動にも取り組んでおられる。
講演では、まず高レベル廃棄物の地層処分についての一般的説明があった。日本では、使用済み核燃料を再処理した後に発生する高レベル廃棄物を30−50年間中間保存じ、そののち地層への最終処分を行う計画である。フランスやスイスでも同様の計画を有するが、一方、北欧や米国では、使用済み核燃料を再処理せずに直接処分する方法(ワンスル―)が検討されている。オーバーパックの機能は、埋設直後の初期段階に外力による破壊や地下水との接触による溶融反応から廃棄物を保護することにある。我が国の処分モデルでは、オーバーパックは、少なくとも1000年の寿命が要求される。オーバーパック破壊後は、ベントナイト緩衝材で1−2万年、さらに周辺岩盤で数万年、計10万年程度の閉じ込めを想定する。10万年というのは、これら多重バリアにより放射能レベルがウラン鉱石のレベルにまで十分に低下する時間である。
次にオーバーパックの寿命を決定する、地下水による腐食に関する説明があった。オーバーパックの腐食は、全面腐食のほか、水素脆化や応力腐食割れも含む。我が国では、処分環境で緩やかに腐食が進行することを前提とした材料(準耐食型という)である炭素鋼オーバーパックを主たる候補に位置付けている。炭素鋼の特徴は、資源がたくさんあり安価であること、長い期間のデータ、ナチュラルアナログ研究背景があることなどである。最終処分場閉鎖直後(100年程度)は残留大気に含まれる酸素分子により酸化性環境となるが、閉鎖後長期にわたって無酸素の還元性環境におかれる。鉄鋼材料では、還元性環境では応力腐食割れ(SCC)は生じないと考えられていたが、1980年代に還元性中性地下水で応力腐食割れが生ずることが、高圧天然ガスパイプラインの破損事故において見出された。このSCCをニアニュートラルSCC(NNpHSCC)という。パイプラインと類似の環境におかれる炭素鋼オーバーパックにおいても、NNpHSCCの発生、進展を研究することは重要である。そこで、オーバーパック候補材の模擬材(SM400B)のNNpHSCC感受性を低速度歪試験(SSRT
)により評価した。図3にCO2-N2,純CO2,純Ar ガスを吹き込んだ溶液における平均pHとSCC感受性を示す。縦軸はSCC感受性が高いほど小さな値を示す。また、SSRT試験中の試験片の自然電位とSCC感受性指数の関係を調べた。その結果、NNpHSCCが発生する電位域は、Parkinらによる定電位SSRTの結果と同じく、水素は正電位よりも卑側の還元性電位気に限られること、NNpHSCCが発生する上限のpHは保守的にみて、8.2-7.8であることなどがわかった。
原発から発生する高レベル放射廃棄物の地層処分に関しては、今後、再処理を伴わない使用済み核燃料の直接処分も含めて検討されるようであり、今回の講演で示されたような、地層処分関連材料の腐食に関する基礎的研究は、いろいろな状況を想定して今後ますます重要になってくることを再認識した。
(岩瀬彰宏 記)
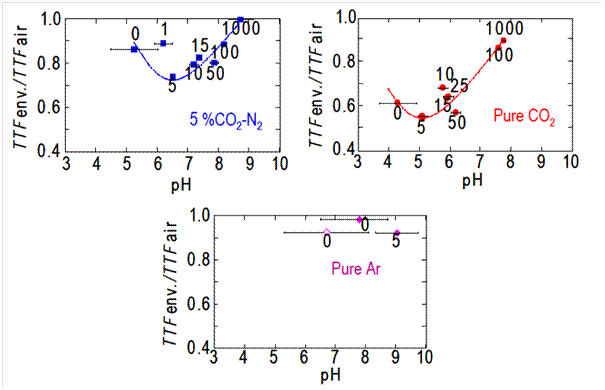
図3 5%Co2-N2ならびに純Co2、純Arガスを吹き込んだ溶液の平均pHとSCC感受性指数TTFenv./TTFair の関係
(図中の数字は添加したNaHCO3の濃度を、各印上のエラーバーはSSRT前後における溶液pHの変化の範囲をそれぞれ示す。)
3.放射線と甲状腺
福島県立医科大学・医学部放射線健康管理学講座 教授 大津留 晶
大津留晶先生は、長崎大学でこれまで携わってこられた原爆被爆者を中心とした被ばく医療、特に甲状腺・内分泌学の専門家としての経験を活かし、2011年10月より福島県立医科大学医学部放射線健康管理学講座の教授として、また同時に大学附属病院放射線災害医療センター部門長として活躍されている。講演では、最初に、2011年3月11日に発生した福島第一原発事故時における福島県立医科大学における緊急被ばく医療の実際について、紹介があった。大規模災害時には、災害派遣医療チーム(DMAT)が被災地に派遣される。今回の災害時には、DMATの応援を得て、医療スタッフ180名からなる35チームが編成され、3日間で168名の救急患者を福島県立医大が受け入れた。さらに、原発から30km圏内の避難地域からの遠方搬送患者175名を受け入れた。初期の頃は、ベッド数が足りずに、ロビーに布団を敷いて患者を受け入れるという状況であった。また、福島第一原発での作業員の傷病者12名を受け入れて、入院治療を行った。スライドでは、当時の病院内の混乱と緊張感が伝わる写真が何点か紹介された。事故後、福島県から県外へ避難する県民が急増した。これを年齢階層別に分析すると、2010年までは非常に少なかった15歳以下とその両親と思われる年齢の転出者が2011年以降急激に増えていることがわかる。このことは、若年者に対する放射線の健康リスクを懸念する人たちが、リスクを避けようとして県外へ転出している現実を示している。
さて、この放射線による健康リスクで一番懸念されるのは、チェルノブイリ原発事故の影響などを考慮すると、小児の甲状腺がんである。事故により飛散したヨウ素131による甲状腺における内部被ばく線量の推定は、ヨウ素131の半減期が8日と短いために、被ばく直後に計測されないと困難になる。弘前大学のグループは、原発周辺地域より初期に空間線量率が高くなった地域へ避難した住民を対象に、甲状腺モニターを用いてヨウ素131の甲状腺等価線量を測定した。それによると、成人54名中検出したものが74%であり、最大が33m、中央値が3.6mSvであった。子どもについても、8名中6名で検出し、最大が23mSv、中央値が4.2mSvであった。極めて限られたデータからの予測にはなるが、チェルノブイリ原発事故での子供の甲状腺等価線量が、数百mSvから数千mSvと推定される状況と比較すると、福島での被ばく線量はかなり低く、放射線による小児甲状腺がんのリスクは極めて小さいと推定される。
このような状況の中、現在、福島県立医科大学では、福島県からの委託を受けて、「県民健康管理調査」を行っている。その内容は、次に掲げる5つの調査からなる―1)基本調査(初期外部被ばく線量)、2)子供甲状腺超音波検診、3)妊産婦調査、4)避難地区(21万人)の健診検査、5)避難地区(21万人)の健康度・生活習慣病調査。その結果、例えば基本調査による初期外部被ばく線量の評価では、約38万5千人を解析し(平成25年2月公表時)、1mSv以下が、66.3%、5mSv以下が99.8%であり、最大被ばく線量が25mSvであった。
一方、原爆被爆者における臓器別、及び被ばく時年齢別の発がんリスクでは、特に甲状腺がんにおいて、被ばく時年齢が若いと発がんリスクが高くなる傾向がある。同様の傾向は、チェルノブイリ原発事故後の甲状腺がん発生頻度を示すデータでもみられる。甲状腺がんが若年で発症しやすい理由の一つとして、大腸がんや乳がんに比べて、少ない遺伝子変異でがんになるというモデルが提案されている。これまでに、甲状腺がんの発症に係わると考えられる遺伝子として、細胞増殖に関与するいくつかの遺伝子の変異が明らかにされている。例えばそのうちの一つであるBRAF遺伝子に変異をもつトランスジエニックマウスを作成すると高率に甲状腺がんを発症することも明らかにされている。しかし、発がん過程における遺伝子変異の全容はまだ不明な点が多く、これからの研究課題である。
放射線被ばくによる健康影響のうち、最も注目されるのが小児の甲状腺がんであることから、県民健康管理調査でも図4に示すような基準で、超音波診断装置を用いた甲状腺がんの一次スクリーニングを行っている。
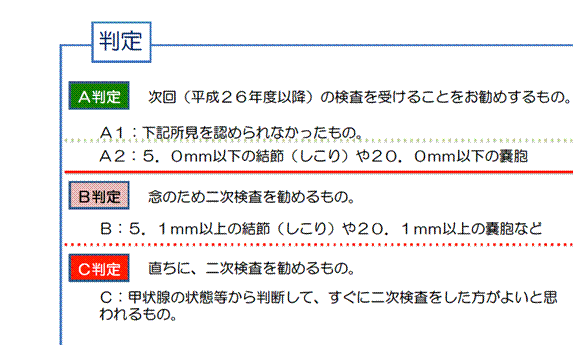
図4 甲状腺一次スクリーニングの判定基準
平成25年8月の発表で、約19万人の検診を終了し、A判定は99.3%、2次検査を行うB、C判定が0.7%であった。ただし、A判定の中でも、小さなのう胞や結節を認めるA2判定が44%あり、また、B、C判定の中で、18名がその後の手術で甲状腺がんと診断された。この結果に関する放射線の影響を明確にするために、弘前市、甲府市、長崎市でも同様の甲状腺の超音波検査を行ったところ、A判定99%、うちA2判定は56.5%、B判定が1%であった。このことは、精密なスクリーニング検診を行えば、どこでも福島県でみられたと同様の甲状腺に関する所見が得られることを示している。また、甲状腺がんの多くは、ゆっくりと進行するものであり、進行の遅いがんと速いがんを見分ける診断が今後重要な課題となる。
福島県が取り組む県民健康管理調査は、これまでに例がない大規模な健康調査であり、甲状腺に限らず健康に係わる様々な情報発信の元になる貴重な調査になることは明らかであり、今後のデータの蓄積に期待を寄せるものである。 (児玉 靖司 記)
4. 負ミュオン特性X線を用いた非破壊多元素同時分析
大阪大学大学院理学研究科 二宮 和彦
ミュー粒子は素粒子の仲間であるレプトンに属し、負電荷と1/2のスピンを有する。電子のおよそ200倍の質量を有し、10-6sの時間で電子とニュートリノに崩壊する。その反物質である正電荷を有する正ミュオンは陽電子とニュートリノに崩壊する。したがって負のミュオンは重い電子、正のミュオンは軽い陽子とみることも出来る。ミュオンは地球大気の原子核に、宇宙からの宇宙線が衝突して生成され、地上に降ってきている。通常手の掌には毎秒1個程度の割合で来ているそうであるが、この程度の数では到底ビーム実験には使えそうもない。しかしながら平成21年度より共同利用が開始された東海村のJ−PARCを施設を利用することによりミュオンをビームとして使用可能となった。ここでは高エネルギーの陽子を炭素の標的に衝突させて、生成したπ中間子の崩壊によって生成するミュオンを利用する。平成22年3月の段階では1パルス当たり72,000個のミュオンが生成され、当時の世界最高値である。
正のミュオンは固体物理研究の分野で、μSR(Muon Spin Rotation)として局所磁場の知見を得るツールで知られているが、今回の講演は負ミュオンの利用である。物質中に打ち込まれた負ミュオンは減速停止して原子の負ミュオン軌道に捕獲され、電子と置換してミュオン原子を形成する(図5)。捕獲された負ミュオンが脱励起する際、存在した軌道に相当するX線が放出されるが、ミュオンの質量が電子の200倍程度であるため、放出されるX線のエネルギーもそれに対応して、電子軌道起因の特性X線に比して200倍程度大きな値を示す。エネルギーが高いため、物質深部からの情報も得られることが、本手法の大きな特長である。放出されるX線は元素に特有であり、水素以外の元素に対してミュオン原子の形成確率はほぼ同等であるため、元素選択性も問題にならず、またミュオンの入射エネルギーの選択によりミュオンの停止位置を制御して物質の深さ方向の知見を得ることも可能となする。物理的手法による多元素分析法はICP−AES,ICP−MS、XPS、PIXE、中性子放射化分析などが挙げられるが、非破壊で位置選択性を有するのは負ミュオンの利用が唯一といっても良い。
実例として金属の考古学資料の分析結果を示した。考古学資料は貴重なため非破壊で検査を行う必要があり、一般に表面はメッキされていたり錆などで覆われていることや製作過程での偏析の可能性もあり、深さ方向の知見を得られる本手法は大きな利点がある。紹介したのは紀元前3世紀秦代の通貨である半両、我国の天保通宝である。天保通宝は製造が容易であったため多くの藩で偽造されて流通した背景があり、水戸藩での水戸正字の分析結果とも比較した(図6)。これらの結果は化学分析値と良い一致を示した。
この手法が新規の分析法の一つであることは理解できたが、現状では大型の加速器の利用は避けられず、特別な試料の分析に限定されそうだとの印象は免れなかった。
(大嶋隆一郎記)
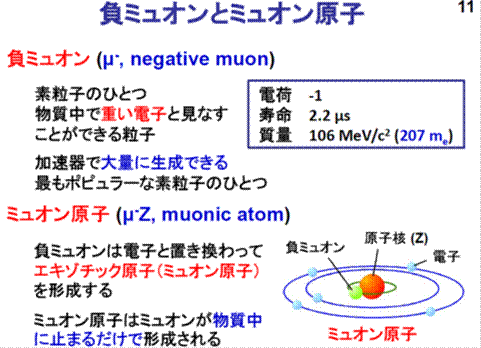
図5 負ミュオンの性質とミュオン原子
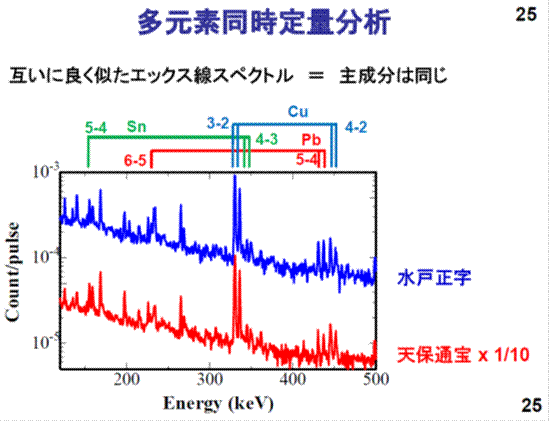
図6 天保通宝と水戸正字との分析結果