第51回放射線科学研究会より(聴講記)
表記研究会は平成25年7月19日(金)13:30から19:00まで住友クラブ(大阪市西区江戸堀)において開催された。今回の講師は大河内拓雄氏((公財)高輝度光科学研究センター)、城戸義明氏(立命館大学)、宇佐美徳子氏((独)高エネルギー加速器研究機構)及び藤田雅之氏((公財)レーザー技術総合研究所)であった。
1. 時間分解光電子顕微鏡顕微鏡(PEEM)による磁気ダイナミクス研究の新展開
(公財)高輝度光科学研究センター 大河内拓雄
筆者らは最近、FeRh合金におけるイオン照射誘起強磁性の研究をSPring-8の25SUビームラインのXMCD-PEEM測定を用いて行っている。この測定方法は、物質の磁性の評価に大変有益な方法である。そこで、この実験でいつも大変お世話になっている大河内氏に、このビームラインを用いた最新の研究成果の紹介をお願いした次第である。
講演では、まず光電子顕微鏡(PEEM: Photo Emission
Electron Microscopy)の原理の説明から始まった。PEEMは、円偏光ビームの偏光方向によりスピンの上向き下向きに対する状態密度の違いを反映した吸収強度の違いを光電子量の2次元マッピングとして捉えるものである。放射光による電子の励起に必要なエネルギーは元素によって異なるため、PEEMを用いることにより、特定の元素に伴う磁性の2次元情報が得られる。フェリ磁性GdFeCo垂直磁化薄膜で得られたPEEM像とMCDスペクトルの説明があった後、今回の講演の主題である、光誘起磁化反転ダイナミックスの研究の説明に移られた。磁気記録デバイスの書き込み速度のさらなる向上が求められているが、磁場を用いず光(フェムト秒レーザー)で磁化制御する技術の開発が進んでいる。しかし、光で磁化反転するメカニズムはまだ十分に解明されていない。そこで、BL25SUのPEEM測定ラインにパルスレーザーを組みあわせた装置を開発し、フェリ磁性GdFeCoの光誘起高速磁化反転ダイナミックスの解明に取り組んだ。図1に時間分解PEEM測定のセットアップと時間分解測定のタイミングチャートを示す。磁化反転現象の繰り返し撮像で行うためには、ワンショットの撮像を行うたびに磁区を初期状態にリセットする必要がある。そこで、試料ホルダ裏にセットした磁場コイルを用いて150 μs、100Oeのパルス磁場を発生させる。その後Ti-sapphireパルスレーザー(波長800nm、パルス幅120fs)を用いて消磁を行い、そのあとΔtの時間を経たのち、放射光をあててPEEMによる磁化観察を繰り返し行うというシステムである。レーザーと放射光の時間差Δtの関数として磁化変化を測定することにより磁化反転ダイナミックスを評価することができるのである。用いたGdFeCo試料は、Gdを26%含む試料と22%含む試料である。この2種類の試料の大きな違いは角運動量補償温度であり、前者は380K,後者は100Kである。また、多層膜構造中に、熱ブロック層であるSi3N4層を入れた試料と省いた試料について実験を行った。その結果、Si3N4層が入ったGd 26%試料、入らないGd 26%試料では、数nsで最終的な磁化状態に落ち着くのに対して、Si3N4なしのGd 26%試料では、磁化が最終状態に至るのに30ns以上を要することがわかった。この研究の今後の展開として、フェリ磁性を構成するGdとFeの元素別ダイナミックスの観測、単純反転と円偏光依存反転のダイナミックスの違いを明らかにすることなどが挙げられた。本測定に関しては、現在は技術的成功を収めた段階であり、今後、系統的なデータの蓄積に向かうとのことであった。今後の展開が楽しみである。次に、高周波励起下でのNiFe磁気円盤の共鳴運動の観測について説明があったのち、最後のトピックスとして絶縁性試料のPEEM観察について述べられた。BL25SUにおけるXMCD-PEEM測定は全電子収量法で行うため、試料の帯電は測定にとって大きな妨げになる。しかし、一方で、樹脂や誘電体、岩石・隕石、といった絶縁性材料のPEEM測定のリクエストがユーザーから多く寄せられた。そこでタングステンワイアをマスクとして用い、測定したい数10μmの微小領域以外をAu導電性膜で覆うことにより、今では、フェライトや高分子、隕石といった絶縁性材料に対して、帯電問題を解決してPEEM観察に成功している、筆者らのグループでも最近、CeO2などの絶縁体において放射線照射により磁性が発現することを見出しているが、その起源を探るためにXMCD-PEEM観測は大変有用であると思われる。従って、筆者にとっても、絶縁体試料でのPEEM観察成功は大変な朗報である。 最後に、PEEMによるいろいろな測定法の開発は本ステーションの利用ユーザーの研究アイデアによって先導されるものでるので、今後も多彩な課題提案を期待しているという言葉で、全体の講演を締めくくられた。
(岩瀬記)
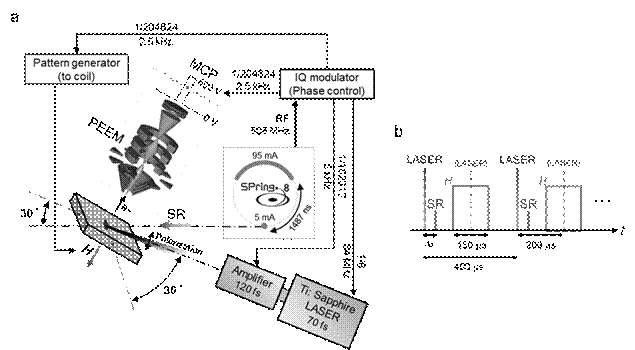
図1 時間分解PEEM測定のセットアップと時間分解測定のタイミングチャート
2.イオン物質表面相互作用
立命館大学・理工学部 城戸義明
講師の城戸教授は、長年にわたり、イオンと物質最表面との相互作用の研究を精力的に推進されてきた。1996年には立命館大学の放射光施設に光電子分光と中エネルギーイオン散乱分光法(MEIS)を結合した複合分析システムSORISを建設し、以後、この装置を用いた独創的研究を行っている。今回の講演では、その中から、イオンビームと固体最表面との相互作用における特徴的現象とその応用例のうち、いくつかを紹介いただいた。
講演では、まずSORISシステムの説明が行われた。放射光による光電子分光とMEISを結合したSORISでは、分子線エピタキシーによる試料作製、清浄表面出しのためのスパッタ銃、赤外線加熱なども備えており、表面研究に必須の超高真空中in-situでの試料作製から分析まで一連の作業を行うことができる。MEISで用いるToroidal分析器は、入射ビームサイズを十分絞り、印加電圧一定の元で電極間ギャップを広げて十分な統計性を確保するなどの工夫を行って通常より高い分解能1x10-3を達成した(図2)。次に、イオンと固体最表面原子との相互作用について、いくつかの基礎的研究例を紹介された。まず、Ni表面にAu原子を0.4モノレイヤー蒸着した試料の最表面から散乱されたイオンのスペクトルは、内殻電子の励起に起因して低エネルギー側にテールを引く非対称なプロファイルを持つことが報告された。この非対称性は、検出器の分解能が十分良いために観測できたものである。この非対称性は、EMG関数によってよく近似できることも示された。次に、イオンが試料最表面から散乱される場合の電荷分布が非平衡になる実験結果が示された。Heイオンの場合、試料表面から出射するイオンはHe0,He+,He2+の3種類である。その割合は、ある一定以上の通過距離があれば一定の値、すなわち、平衡電荷分布をとるようになる。図3は、アモルファスSiO2膜表面から散乱されたHeのうち、He+イオンの後方散乱スペクトルである。アモルファス媒質にもかかわらず、鋭い表面ピークがみられる。これは、電荷が平衡分布には達せず、He+の割合が平衡値よりかなり大きいことによって生じた現象である。イオン・固体最表面の基礎的研究として最後に紹介されたのは、かすめ衝突効果である。高速イオンビームが試料の結晶軸に沿って入射し、かすめ衝突して大角散乱された出射する場合、ランダムパスを通過する場合に比べて大幅な電子的エネルギー損失を被る。固体の原子は有限温度では熱振動しているので、原子によるシャドーイング効果は完全でなく、背後の原子にヒットする確率は、格子振動の大きい場合、すなわちデバイ温度の小さな固体の場合、けっこう大きな値となる。この場合、原子芯近傍を通過することで内殻電子の励起確率が大きくなるため、大きな電子的エネルギー損失が起こることが示された。
最後に、イオン・固体最表面相互作用の基礎的知見をもとに、高分解能イオン散乱実験の応用例がいくつか示された。それは、高温超電導体薄膜基板や強誘電体としてサーミスタなど広く応用されているSrTiO3表面構造の評価、そしてAuナノ粒子および、Au/Pdコアシェル構造粒子のサイズ・形状分析、成長過程評価への応用である。これまで、イオン散乱分析は、主に層状構造の解析に用いられてきた。一方、各種ナノ粒子や量子ドットの分析には、主にトンネル顕微鏡(STM)や原子間力顕微鏡(AFM)が使用されることが多いが、高分解能イオン散乱法を用いれば、これらナノ粒子の形状や、サイズの分析、成長過程の評価も可能であることが、Auナノ粒子をルチル基板上に形成した試料における実験例をもとに示された。
講演のまとめとして、高分解能イオン散乱分析が、固体最表面に関する定量的情報を与えるツールとして、「VersatileかつUnique」な分析方法であることが強調された。
講演を聴講して、SORISビームラインの独創性、有用性に感心するとともに、これを用いた物質とイオンの相互作用の基礎研究や応用研究が、今後ますます発展することを願うものである。
(岩瀬記)
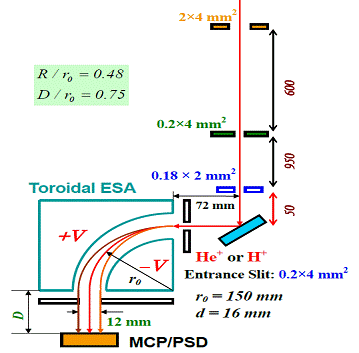
図2 入射ビーム・試料とトロイダル分析器
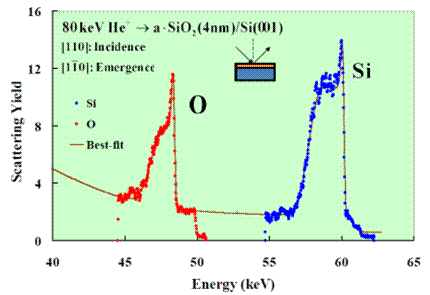
図3 80keVHe+イオンをa-SiO2(4nm)/Si(001)に入射させて得られた後方散乱スペクトル
3. 放射光を用いて放射線の生物作用のメカニズムを探る
高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所 宇佐美徳子
今回の研究会での最初の二つの講演は何れも放射光による固体物性の研究であった。宇佐美講師が所属しているつくばのフォトンファクトリー(以下PF)も我が国の放射光研究の一大拠点である。しかしながら、放射光による放射線生物学の研究は少ないと講演の最初の部分で話された。宇佐美講師らは、東京都田無にあった東大の放射光施設を利用して研究をスタートしたが、つくばにPFが建設されるにあたり、当初から試料準備室も含めた放射線生物学の研究施設が計画されたので、優れた研究環境が整備されたそうである。近年、放射線生物学の分野ではRIを標識に使う頻度が減り蛍光物質等が用いられる傾向が増してきたが、PFの施設では準備室から非密封RIが利用可能となっており、使い勝手の良い設計になっている。
講演ではまず放射線生物学の成り立ちからの経緯を概観した後、放射光施設ならではの研究成果を紹介した。放射光の特徴はエネルギー選択制に優れ、高輝度であることである。PFには生物系として2つのブランチビームラインがある。BL-27Aは軟X線(2〜4keV)、BL-27BはX線(4〜20keV)で、ビームライン光学系は何れも非密封RI使用エリアの外に設置されている。BL-27Aのような低エネルギーX線照射では、通常は真空内照射となるが、それでは細胞は死んでしまうので、ビームを大気中に取り出し、生きた細胞や生体分子水溶液などに照射出来るように設計してある。この時のビームサイズは6×3mmで、それより大きい試料に対しては試料自体をスキャン出来るようになっている。一方BL-27Bでは通常の照射以外にブロードビーム(max 50mm×8mm)照射とマイクロビーム照射が可能としてある。
生体にとって照射に伴う重篤な損傷はDNA二本鎖切断であり、放射光のエネルギー可変性を利用した研究成果としてフォトンエネルギーが100eVを超えると急激にその収率が増加することが明らかとなった。これは広いエネルギー領域での照射が可能な施設によって系統的にDNA切断収率を測定した初めての成果であった。損傷の修復されやすさや生体内に外部からドープした重金属による放射線生物効果の研究も行い、白金化合物添加により放射線増感効果があることが見出され、その成果は放医研でのガン治療に応用されている。
講演の後半はバイスタンダー効果に関する最近の成果を紹介した。1992年にα線により放射線の照射を受けていない細胞にも遺伝的変化が生じていることが発見され、バイスタンダー効果として注目を浴びるようになった。低線量放射線の生物影響の研究として、細胞集団の平均でそれを調査する方法では、そのメカニズムまで踏み込むことが困難なため、特定の細胞にのみ照射可能なマイクロビーム装置が多くの施設で設置されるようになった。2006年段階で世界にはすでに30を超える施設があるが、現在はさらに増えていると思われる。我国においても関東地区だけでもPF以外に原研高崎研、放医研、電中研の4か所に線種の異なるマイクロビーム照射装置がある。PFのビームは水平であるので、細胞を良好な生理的条件で照射して観察するには不都合なため、ビームをSi単結晶の311回折を利用して垂直方向に反射させそれを顕微鏡の試料ステージに固定した細胞に照射できるようにした。この手法ではビームのエネルギーは5.35keVと自由にビームのエネルギーを選択できるPFの利点は犠牲となるが、光電子の飛程は0.8μmで細胞外へ漏れだすことはないため特に問題とはならない。また、強度は必要ないので、集光は行わず、スリットを用いて任意のサイズのビームが得られるように設計してある。ステージの駆動や解析システムは独自で開発したものを使っている。このインラインのシステム以外にオフラインの装置を用意してあり、試料ステージを共通にしてあるので、照射後の観察を精査可能にしてある。さらに、顕微鏡を横置きにして水平ビームを利用するシステムも構築し、放射光利用の利点であるエネルギー可変の実験を可能にしてある。
実験では細胞全体への照射と細胞核のみへの照射の生存率を調べた結果、細胞核のみへの照射に比べて細胞全体への照射では明らかに生存率が増大した。これは細胞質内に何らかの放射線センサーが存在して修復のシグナルを出していることを示唆している。また、自然突然変異頻度も低下していることが観察され、突然変異を引き起こす細胞が選択的に排除されている可能性がある。これらの結果をさらに調査するため、核にはビームが直接照射されないマスクも開発した(図4)。
このマイクロビーム照射により低線量照射の生物影響について新しい知見が得られつつあることが良く分かった。これまでいわゆる放射線生物の研究者間でも様々な議論が輻輳していた低線量照射の生物応答の本質が整理されることを予感した講演であった。(大嶋記)
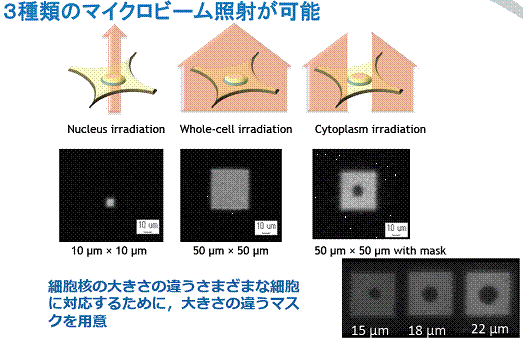
図4 様々な細胞に対応可能な照射マスクを作成
4. 高輝度レーザーによる物質改質・加工
(公財)レーザー技術総合研究所 藤田雅之
今回のエキゾチックビームは何れもフォトンの応用であるが、藤田講師の講演はレーザービームであり、少し性質が異なる。レーザー利用技術は多岐にわたっているが、今回の講演はタイトルにあるように物質の改質・加工に関するものである。レーザー核融合の場合のような高出力におけるプラズマ物理は基礎的な研究も進んでいるが、レーザー加工の分野では必ずしも基本的な物理が明らかにされていないそうである。レーザー加工の特徴は○非接触、反動がない、○微小スポットにエネルギーを集中できる、○エネルギー密度、パルス幅、波長を調整することにより、加熱、溶融、蒸発を選択可能である。また、要素として○波長、○エネルギー密度(パワー密度)、○パルス幅の3つが挙げられる。レーザーによる加工の基本はレーザー光の照射によって材料中の電子にエネルギーが吸収され、その電子と周囲の電子との相互作用により、エネルギーが材料中に伝播されて、加熱、融解、蒸発に至ることである。レーザー光からは対象として見えているのは照射材中の原子内の電子だけであり、素材が金属、半導体、誘電体かどうかを識別しているわけではない。しかしながら、金属では自由電子が多く、表面近傍で全てのエネルギーが吸収され内部までビームは侵入しない。その深さをスキンデプスと呼ぶ。一方、ガラスのような誘電体では自由電子が殆どないので、ビームはそのまま透過してしまう。しかしながら、強いビームを内部に集光させた場合には多光子吸収が生じ、これを利用した加工が可能となる。お土産や記念品にガラスのブロック透明体に東京スカイツリーなどの立体像が描かれたものを目にすることがあるが、これは短パルスレーザー光を内部に集光させてそこで形成されるマイクロクラックで描いたものである。この手法はガラス部品の切断に利用される。半導体ではバンドギャップが1〜数eVであり、レーザーの波長に依存して励起されたりされなかったりする。また一部の化合物では、レーザー波長によりC−C,C−H、C=Cなどの化学結合の切断が可能であり、この手法はリソグラフィ技術に応用される。前述のように金属へのレーザー照射では光はスキンデプスまでしか入らないが、加工出来る領域がそこにとどまるわけではない。レーザー照射により表面近傍にプラズマが生成され、プラズマがレーザー光のエネルギーを吸収して温度が上昇し、その熱が熱伝導により深部まで伝播することにより融解、蒸発が可能となる。
この性質をうまく利用すると様々なミクロな加工が出来るようになる。例えばプラズマの発生にまで至らない極端短パルスでは加工はスキンデプスにとどまり、細かい加工が可能となる。一方、プラズマが発生するパルス幅ではビームのエネルギーはプラズマの加熱に費やされ、スキンデプスより深いところへの加工は熱伝導による加熱が担う。
レーザー光強度のピークパワーはそのパルス幅がナノ秒、ピコ秒、フェムト秒と短くなるにつれ、桁違いに大きくなり、1965年頃に比して現在は12桁強度が増している。産業利用されているハイパワーレーザーのパルス幅による利用例を図に示す。
講演の後半では主に超短パルスレーザー加工による興味ある結果を示した。ナノ秒パルスによる加工は熱拡散長さで決まるのに対してフェムト秒パルスではプラズマの発生前に加工が終わるので加工深さは光侵入長のみで決まる。従ってフェムト秒パルスで穴を開けた場合には穴の淵がきれいであるが、ナノ秒パルスでは熱による加工層が形成されるのでがたがたの穴となる。講師の例えによればフェムト秒加工は新雪の上の第一歩であるが、ナノ秒パルス加工は新雪の上を多くの人が歩いてぬかるんだ状況を思い浮かべれば良い。レーザー光の強度分布をうまく利用するとビーム径よりも小さい加工も可能であり、100μm程度のスポットサイズのビームを使って毛髪に20μmの穴を開けた例を示したが、この場合には投入エネルギーの大部分は無駄となる。魅力あるフェムト秒レーザーであるが、装置がまだ高価で用途が高付加価値の物に限定されて市場が小さく新領域の開拓が必要である。その一つは低強度照射での興味深い現象の応用である。きっかけは加工閾値近傍で開けた穴の周囲に数100nm程度の周期の縞組織が形成されていることに気づいたことである。この自己組織化の成因は解明されていないが、レーザー光の偏りに直交する向きに筋が形成される。そこでレーザー光を掃引して広い面積にこの周期構造を形成させた。これに可視光が照射されると回折格子の原理で表面が虹色に見える。周期構造を形成した金属表面では摩擦係数も減少する。透明な材料でも可能であるが、投入エネルギーが大きくなる。そのため表面に金属膜をつけ、そこにレーザー照射して金属膜の縞構造を透明材料にインプリントすることを試みたところ、金属膜の500nm程度の周期よりも小さな周期構造が形成されることを見出した。これはガラス表面のフレネル反射を減じて周囲からの映り込みの防止に利用できるが、可視光領域をカバーするには、更に細かい100nm程度の周期が必要で、そこには至っていない。その応用の一例としてLEDランプからの光の放射効率を上げることを述べた。省エネの象徴の一つであるLEDランプは、素子の発光効率は高いが、可視光を外部へとりだす材料に課題があり、温度を上げて光を取り出すためソケット部分が熱くなる。筆者も自宅の照明の一部をLEDに交換した際、ソケット部分の温度が高いのに気づき、エネルギーロスがまだまだあると感じたことがある。講演の最後の部分では半導体デバイス技術として重要な結晶シリコンの照射による非晶質化、あるいは結晶−非晶質の相転移の制御など多彩なトピックスを紹介した。非常に魅力あるフェムト秒レーザーであるが、システムの高価格がまだまだネックで応用の範囲が限定されていることが理解出来た。(大嶋記)
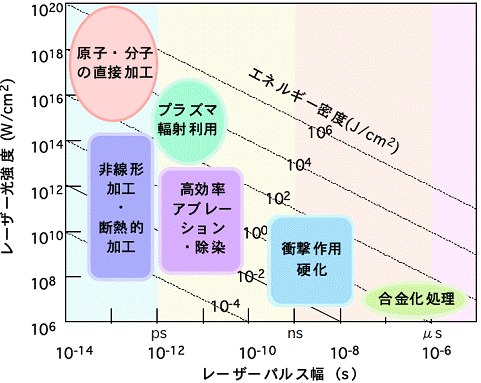
図5 高輝度レーザーの産業利用