第50回放射線科学研究会より(聴講記)
表記研究会は平成25年4月19日(金)13:30から19:00まで住友クラブ(大阪市西区江戸堀)において開催された。今回の講師は村井耕二氏((公)福井県立大学)、関 修平氏(大阪大学大学院)、松橋信平氏((独)日本原子力研究開発機構)及び小笹晃太郎氏((公財)放射線影響研究所)であった。
1. イオンビーム突然変異を利用した小麦の遺伝子解析と品種改良
(公)福井県立大学生物資源学部 教授 村井耕二
村井教授とは、昨年10月に京都で国際学会(「物質中の高速重イオン国際シンポジウム」SHIM2012)を開催したときが初対面であった。長年、理研の加速器利用などでお世話になっている阿部知子博士の紹介で講演していただいたが、大変面白いお話だったので、ぜひONSA放射線科学研究会でも、ということでお願いし、今回講演いただくことになった。講演では、まずDNAの基礎に関する解説から始まった。次に、何らかの要因によってDNAの変化である突然変異について話された。突然変異体の解析は遺伝子の機能解析に有用である。物理的刺激、あるいは化学的刺激により突然変異率を高めることが可能であり、自然界で起こる突然変異を待つのでなく、いろいろな突然変異誘発法を用いて研究が進められている。その中でも、高エネルギーイオンビーム照射は、電子を高密度に励起できる(すなわちLETが大きい)ため、DNAの欠失変異体を効率的に得る有効な手段である。ある遺伝子の部分を欠失させた突然変異体と正常体を比較することにより得られる形質の違いを見れば、その遺伝子の機能が特定できるのである。村井教授らは、この手法を重要な農作物の1つである小麦の品種改良に利用する研究を進めている。小麦の乾燥種子に、理化学研究所、リングサイクロトロンから得られるGeVエネルギー領域の重イオンビームを照射する。照射した後に生育させたM1植物体は対立遺伝子に欠失が得られるが、表現型は正常である。M1体を自家受精して得られるM2植物体はメンデルの法則に従い、25%の割合で変異個体が現れる(図1)。このような方法で得られたM2世代の調査の結果、次々と葉をつける栄養成長期が続き、花を咲かせる生殖成長期に移行(この移行を「花成」という)しない変異体(mvp)が発見された。図2で丸で囲んだ植物体がmvp変異体である。野生型の植物体に比べ、節間成長がみられず葉が繁茂した栄養成長段階であることがわかる。そして、mvp変異体DNAでは、花成において重要な働きを担う花成遺伝子WAP1が欠失していることが明らかになった。村井教授らは、このようにしてイオンビーム変異体の解析から見出した、小麦の生育に重要な遺伝子WAP1について、日本全国の様々な小麦品種がどのようなタイプのWAP1遺伝子を持っているか調査した。その結果、北陸地方の従来品種「ナンブコムギ」は、作用力の弱いWAP1遺伝子を持ち、九州地方の早生品種「ニシカゼコムギ」は作用力の強いWAP1遺伝子を持つことを発見した。そこで、ナンブコムギとニシカゼコムギを交配し、ナンブコムギから耐寒雪性を受け継ぎ、ニシカゼコムギから作用力の強いWAP1遺伝子を受け継いだ、福井県での栽培に適した優良コムギ「福井県大3号」(愛称名ふくこむぎ)を育成した。図3にふくこむぎの栽培の様子を示す。加工適正検査の結果、ふくこむぎはパンや中華麺用に優れた性質があることがわかり、現在、「産地品種銘柄」として生産普及が始まっているとのことである。さて、講演後の質問で、「それは遺伝子操作にならないのか?食品として安全なのか?」という質問があった。実は京都での国際会議でも同様の質問がドイツ人研究者からあったので、多くの人が同じ疑問を持っているに違いない。講演で紹介されたコムギの研究では、イオン照射は花成遺伝子の同定を行うために利用されている。生産普及を開始したコムギは、イオン照射によって得たデータをもとに、通常の手段で従来種を交配して作ったものであり、照射した種子を育成したものではない。イオンビーム照射による突然変異に関しても、国際学会、今回の研究会とも、質問に対しては、「イオンビームによる突然変異は自然界で起こる変異率を高めるだけであり、遺伝子操作ではなく、安全である」との答えをいただいている。(岩瀬記)
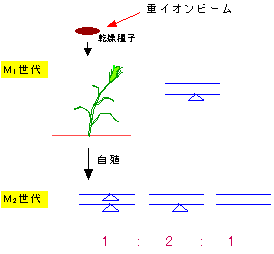
図1 イオンビーム変異体の獲得スキーム
△は欠失遺伝子を示す。
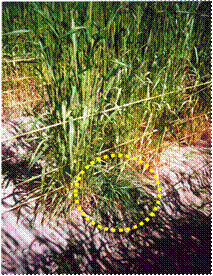
図2 mvp変異体(○の部分)

図3 小麦新品種「福井県大3号」(ふくこむぎ)の栽培
2. 1つの粒子による多機能複合ナノ材料の形成
大阪大学大学院工学研究科 教授 関 修平
電子やイオンなど荷電粒子ビームを用いた微細加工技術はすでに多く行われているが、それはビームによる化学反応をある狭い空間に集束させて行うものである。一方、高エネルギーイオンは、そのイオンパスに沿った狭い領域で高密度電子励起を起こすため、1つのイオンによる効果が、ナノ構造体形成をもたらすことが期待できる。講師である関教授は、有機材料(高分子)に高エネルギーイオンを照射することにより新規ナノ加工技術の開発を精力的に行っている。講演では、まず、単一イオンを用いたナノ加工法(これを関教授は、Single Particle Nanofabrication Technique, SPNTと呼んでいる)の原理についての説明があり、そのあと、生体材料融合ナノ材料、刺激応答型ナノ材料、電子機能ナノ材料に関する最近の成果について紹介された。その内容は多岐にわたるものであったため、ここではその1部のみを紹介することにしたい。SPNTのプロセスは、有機薄膜の形成、高エネルギーイオン照射、未反応部分の溶解であり、これでナノ構造有機体が作成される。図4にその概念図を示す。図で示すように、イオンビーム周辺の狭い領域(コア)にまずエネルギーが付与され、その後2次電子によるエネルギー付与領域(ペナンブラ)が取り囲む。高分子の単一ナノ加工法で重要な化学反応はペナンブラ領域で起こる。この加工法でまず問題になるのは、用いる加速器が一般には高価で大規模であるため、採算性に問題があるのではないか、ということについての言及があった。しかし、最近は医療に用いられる加速器の小型が進み、また、SPNTプロセスに必要な照射時間(したがって加速器使用時間)もすごく短いことを考えると、採算的にもそれほど非現実的ではないということである。図5には、代表的架橋性高分子(polystyrene(PS))をもとに、これに反応性官能基であるethynylene基を導入して架橋効率を向上させた高分子への高エネルギーイオン照射による1次元ナノ構造体形成とその表面機能化の例を示した。PSは、SPNTによる1次元ナノ構造体形成に最適な材料の1つであり、イオン周辺の2次電子によるエネルギー付与の計算式に従ってサイズ制御性の検討が十分に行われている。Ethnylene基導入により、高分子架橋反応率は大きく向上し、図に示すような高いアスペクト比を有するナノ構造体の形成にも耐えうる。架橋反応点であるethynylene基は分子鎖1個程度なので、多数のethynylene基がナノ構造体表面に存在し、これらが表面化学反応点として作用し、図5aに示すように、リンカー分子を介してタンパク質を表面に固定することも可能になる。一方で、形成されたナノ構造体は基板表面との相互作用により2次元分散していることを利用すれば、溶媒洗浄時のナノワイヤー間の相互作用を積極的に用いて、図5bに示すようなナノワイヤーの表面配列を誘起できる。このような1次元構造から2次元構造に拡張されたナノシートは平面上のタンパク質分子配列のプラットホームとしても作用する。高速イオンによって誘起された反応は一般に高分子の損傷と捉えられがちであるが、SPNT法によって形成された「幹」を中心に表面装飾を行うことで膨大な表面を損傷のないフレッシュな分子で機能化することが可能になるのである。このようにSPNTにより、ナノ構造体の示す構造的あるいは機械的特性に加えて、より化学反応に対し繊細である電子物性についても紹介があった。そして、「SPNT法によってナノ構造を形成する材料の探求を行うというアプローチから、ナノ構造化したいものを自由にナノ構造化していくという考え方の転換を意図した手法となるべく、SPNT法の可能性をさらに展開していきたい」ということで講演を締めくくられた。SPNT法は非常に応用範囲の広い手法であることが講演からわかり、今後の研究の展開が大変楽しみである。(岩瀬記)
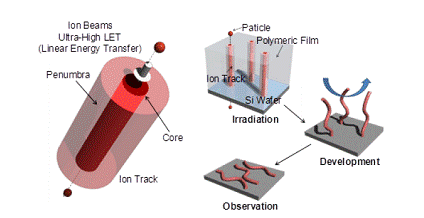
図4 単一粒子ナノ加工法の概念図
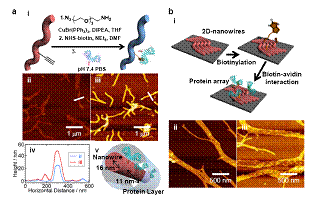
図5 アビジン・ビオチンシステムと化学修飾を用いたタンパク一次元ナノ構造体の形成
3. 福島第一原子力発電所事故からの復興に貢献する放射線利用技術
(独)日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門 松橋信平
(独)日本原子力研究開発機構では、福島第一原発事故により環境中に放出された大量の放射性物質の除染や汚染拡大の防止、除染により発生した廃棄物の減容化等の課題に、様々なアプローチで取り組んでおり、松橋講師により本講演でその取り組みの一端が紹介された。講演の冒頭に紹介されたのは、伊達市にある小学校の25メートルプール水の除染への取り組みである。放射性セシウムで汚染されたプール水を排水するにあたって、そもそも排水濃度の法的な基準が無かったために、厚生労働省による飲料水に対する暫定規制値(200 Bq/L)以下を目安とし、また、pH 5.8〜8.6を適応した。まず、このプロジェクトを実証試験と位置づけ、本試験から得られたプール水の除染法を方法論として一般化し、手引き書を作成することにした。一般化に際して目指したことは、危険がなく、シンプルで、確実性が高く、適応範囲が広く、特殊な装置や資材がいらない方法を確立することである。伊達市の小学校でまず試したのは、凝集沈殿法である。これは、プール水にゼオライト粉末を入れ、攪拌して水中の放射性核種を吸着させた後、凝集剤を添加して凝集・沈殿させ、上澄み水を排水するという方法である。この方法で、伊達市、福島市の7カ所8つのプールについて実証試験を行った。方法論は毎回改良が加えられ、最終的に実証試験結果に基づく手引書を作成し、公開した。実際の作業では、学校関係者や地元の方々との信頼関係を構築できたことが成果につながった。さて、本講演で松橋講師は、放射線に関わる研究者として、このプロジェクトに関わった意義を次のように話された。すなわち、これまでに自分が得た知識や経験を用いて、困っている人々の役に立ちたい。そのように考える「人」であり、「研究者」でありたい。これは、福島第一原発の事故に際して、多くの放射線研究者によって共感される思いであろう。その後、講演の話題は、高崎量子応用研究所で行われている量子ビームを用いた先端研究に移った。まず、紹介されたのは、放射性セシウム用ガンマカメラの開発である。ガンマカメラは、医療分野でよく使われているが、放射性セシウムの高エネルギーガンマ線の検出には対応しておらず、改良が必要である。そこで、ピンホール型ガンマカメラを試作し、オオイタドリやダイズを用いて、137Csの移行を調べた結果、放射性セシウムの植物中の移行を画像化し、数量的に評価することが可能であることが分かった。これにより、放射性セシウムの低集積作物品種や高集積浄化植物の評価が可能になり、これらの植物の開発だけでなく、放射性セシウムの集積を制御する栽培法の確立にも役立つことが期待される。この開発過程で、134Csと137CsをNaI(Tl)スペクトロメータを用いて簡便に弁別定量する手法も考案した。次に、高分子材料への放射線照射によるグラフト重合を用いたセシウム捕集材の開発が紹介された。開発された捕集材は、体積の3,000倍の処理能力があり、高いセシウム捕集特性を示すことが確認された。さらに、福島住民の要望に応えるために、水中に微量で溶存する放射性セシウムを、水道水の管理目標値(10 Bq/L)以下まで除去可能な捕集材を開発し、これを充填した浄水器を作り、商品化することに成功した。その他、セシウム高吸収、または低吸収植物の開発、及びセシウム濃縮菌の開発、さらには材料・機器の耐放射線性評価とそのデータベース化の整備などが現在進行中の研究として紹介された。
最後に、本講演により、(独)日本原子力研究開発機構において、福島復興と原発事故の収束に向けた様々な研究が進行中であり、その取り組みの中から実際に役立つ技術が生み出されていることを知り、感銘を受けた。(児玉記)
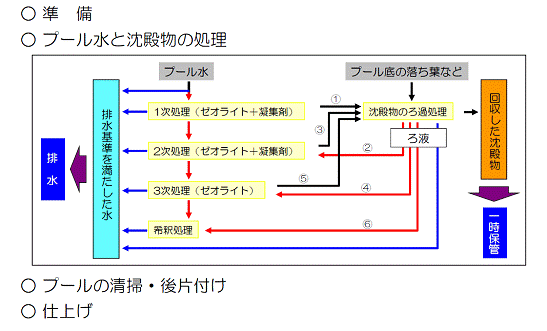
図6 手引書に示した操作手順
4. 放射線疫学の基礎的手法
(公財)放射線影響研究所 疫学部 小笹晃太郎
疫学の“疫”は“伝染病”を意味し、疫学とは、「伝染病の流行状態を研究する医学の一分野であり、集団中に頻発する疾病の発生を、生活環境との関係から考察する学問」とのことである。メデイアを通して、我々も様々な疫学調査による解析結果を目にする機会は多いが、その手法そのものについて解説を聴くことは少ないことから、小笹先生による講演は、疫学手法を知る貴重な機会であった。疫学の追跡調査(コホート研究)は、調べる対象集団をきちんと把握することから始まる。例えば、がんについて追跡調査するには、最低10万人規模の対象集団が必要である。次に、生活習慣などの曝露状況を最初にしっかりと把握し、さらにその状況について追跡することになる。さて、この疫学調査で、何らかの原因と病気との発生に間に因果関係があるのか無いのかは、いくつかの視点から推論される。それらは、関連の時間性、強固性、特異性、一致性、及び整合性であるが、これらの中で必須なものは「時間性」である。時間性とは、何らかの病気の発症について、曝露の時間的な先行を意味する。それ以外は必須ではないが、あれば因果関係が強く疑われる。さて、疫学の追跡調査で得られた結果の量的な評価の表し方の理解は大切である。例えば、喫煙によって肺がんがどれだけ過剰発生するかの量的な評価として、発生率の差が自然発生率の何倍か(過剰相対危険度)、発生率の自然発生率との差はどれくらいか(過剰絶対危険度)、何%が関与するのか(寄与割合)などの指標が使われる。リスクの量的評価には、観察期間の長さも評価に入れる。放射線影響研究所での放射線影響の評価指標としては、過剰相対リスク(ERR)と過剰絶対リスク(EAR)が用いられている。放射線被ばくの効果に他の因子が関連して発生率が修飾される効果を交互作用という。交互作用がない場合は、2つの因子は独立して作用することを意味しており、1つの因子が他方の作用を促進する場合を正の相互作用、逆に抑制する場合を負の相互作用という。負の相互作用が見られる場合は、共通の作用経路の存在が示唆される。実際に、1950年〜2003年までの被爆者における総固形がんの死亡リスクをみると、吸収線量に対して過剰相対リスクは直線的に増加することが示される。リスクが有意となる最低線量域は、0〜200mGyである。さらに、被爆時年齢と発がんの過剰相対リスクの関係をみると、被爆時の年齢が低いほどリスクは高くなり、また、被爆時年齢が低いほど、がんは相対的に早く現れることが明らかになった。さらに、生命表を用いて100mSv被ばく後の生涯リスクについて解析すると、被爆時年齢が30歳の場合には、リスクが約1%増加すると推定された。部位別のがんのリスクを過剰相対リスクで比べると、放射線被ばくでリスクが高くなるがんもあるが、被ばく影響がみられないがんもあることが分かる。興味深いことに、肺がんに対する放射線と喫煙の交互作用を調べてみると、1Gy当たりの相対リスクは、1日当たりのたばこの本数が10本弱で約2(200%増加)になり、重喫煙者では、放射線の影響は見えなくなる(負の相互作用)。これは、肺がんに対する喫煙の影響が、放射線の影響以上に大きいことを意味している。さて、交互作用とは、放射線の真の効果の大きさが、他の因子の存在によって変化することであった。これに対して、交絡とは、他の真の効果のある因子の存在によって、放射線に効果があるように(あるいは、ないように)見えてしまうことである。例えば、放射線被ばくをしていない集団と放射線被ばくをしている集団で相対リスクを計算する場合、もし、被ばく集団に喫煙者が相対的に多く、被ばくなし集団に喫煙者が相対的に少ないと、被ばく集団に喫煙の影響があたかも放射線の影響のように見えてしまうことがある。これは、交互作用とは異なり、見せかけの影響である。しかしながら、原爆被爆者では交絡因子はほとんど見られていない。唯一あるとすると地域差であるが、他と比べても交絡因子が少ない疫学調査という特徴がある。最後に、低線量域でのリスク評価のこれからの課題として、測定すべき影響が小さいことの問題、喫煙等の生活習慣や地理的分布などによる交絡や偏りの影響などの不確定要素、並びに残留放射線・医療放射線被ばくなどの考慮等があげられる。さらに、個人被ばく線量の推定精度も、±35%あるといわれている。
以上のように、本講演では、(1)疫学追跡調査のしくみ、(2)リスク評価の方法、(3)真の姿をゆがめてみせる要素について、基本的な事項を押さえながら具体的な症例について解説いただいた。講演を聴講して、疫学の調査結果の数値だけをみて解釈するのではなく、その数値がどのような考え方を元に導き出され、そこにはどのような不確定要素が含まれていそうかという点にも気を配って解釈すべきであることを学んだ。有益な講演であった。(児玉記)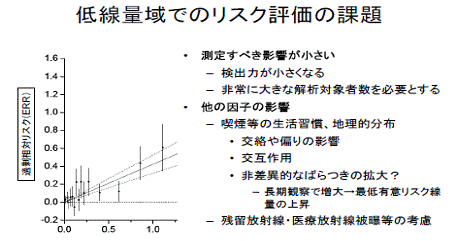
図7 低線量域でのリスク評価の課題