第47回放射線科学研究会より(聴講記)
第47回放射線科学研究会は、平成24年4月20日に住友クラブにて開催し、4人の講師の方にご講演をお願いした。
1. 放射性セシウムの地水圏環境での動態と関西地域でできる東北支援
京都大学原子炉実験所原子力基礎工学研究部門
准教授 藤川 陽子
震災、原発事故から1年以上経った今でも、セシウムをはじめとする放射性物質の除染や農作物に対する影響に関する問題は深刻である。本講演では、初めに福島原発事故による放射性セシウムの放出経過が説明され、そのあと、セシウムの地水環境での動態、そして、災害廃棄物の関西圏受入れなど、東北支援にも言及された。
福島第一原発からのCs-137放出は2011年6月の段階では、チェルノブイリ事故の2割と推定された。これは主に格納容器配管シールなどからの漏洩によると考えられる。(その後JNESによる再評価で、この数値は1割に下方修正されたが、マスコミは積極的には取り上げなかったとのことである)。1号機では3月13日にリーク拡大、2号機は、15日にドライウエルベントを行った。炉内燃料の数%程度のCsが放出されたと考えられる。なお、15日6時ごろ発生した衝撃音は、その後2号機ではないらしいことが判明している。福島第一原発から大気へ飛散した放射性物質(I-131,Cs-137など)の濃度は、東京都で15日にピークに達した(図1)。また2012年2月の推定では、大気放出分のうち海洋への放射能移行は50%以上である。これら放射性物質による土壌汚染は、チェルノブイリと比較して多くて10-20%ということである。
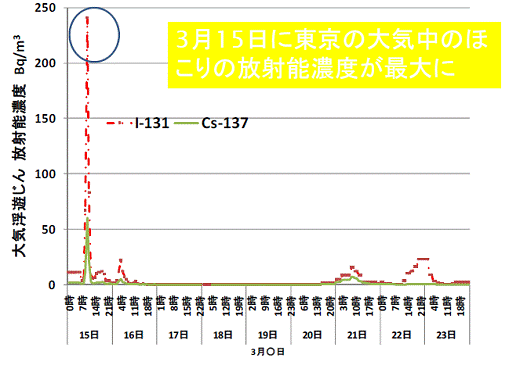
図1 東京都の大気浮遊じん中放射能濃度の推移
次に、放射性セシウムの土や水環境での挙動に関する解説があった。植物の葉面に吸着したCsは、土埃に吸着したものは洗えば落ちるが、溶解性Csは植物内に吸収される。一方、土から農作物への放射性Cs移行は、いろいろな条件に依存する。土壌によりCsを保持しやすいかしにくいかに差がある、植物によりCsの取り込み方に差がある、肥料のやり方にもCs取り込み量は依存する、などである。日本と欧米の土壌は、母岩、気候、植生などの違いにより、異なる性質の土壌が発達している。Csの吸着分配のデータ(図2)によると、一般に、日本の土壌は放射性Csを離しにくい(すなわち、Csを保持しやすい)という結果が出ている。
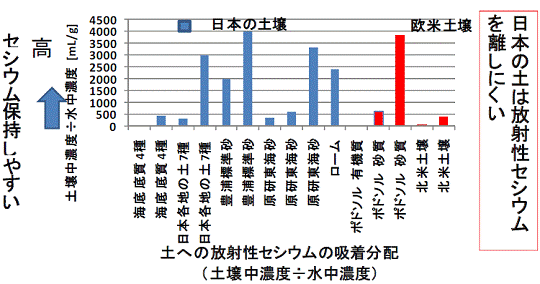
図2 各国の土壌の放射性セシウム保持特性
次に、具体的な例として、玄米中の放射性Cs濃度が高くなる場合に関して言及があった。それは、Csを保持しにくい土壌であった、放射性Csの稲わらが土壌にすきこまれた、水田でカリウムが欠乏気味であった、灌漑水に放射性Csが混在していた、窒素肥料による硝化の結果pHが低下して土壌からCsが脱離した、といった場合である。なお、海洋では、放射性Csの固相への分配比は淡水中より1-2ケタ低下するそうである。そして、地水圏中での放射性Csの挙動に関して、以下のようなまとめが示された。1)土や樹木に落ちた放射性Csは空間線量増加を招き、外部被ばくの要因となる、2)Cs-134による空間線量はCs-137の2倍である、3)日本の土はCsを離しにくい性質を持つ。またイネ科の作物はCsを吸収しにくい。そのために、米や農作物中の放射性Cs濃度は土壌中の濃度に比べてあまり高くない。4)ただし、地域によっては、山林、湖、池の産物には注意が必要である。
最後に、災害廃棄物と放射性Cs、それに関連して関西でできる東北支援の話をされた。原発事故の影響を受けた福島県を中心に放射能汚染のある廃棄物が大量に発生し、焼却による減容は困難である。さらに津波や地震による大量の廃棄物が宮城、岩手で発生しており、復興の妨げになっている。これら災害廃棄物の受け入れに関しては、大阪府も受け入れの安全性を巡って検討とアセスメントを行ってきている。リスクベースで議論し判断することが必要であり、受け入れ可能なリスクについても合意が必要である、さらに、放射性物質についても自治体での独自の環境アセスメント実施が必要である、というのがこれからの考え方として重要であると述べて講演を終えられた。
本講演を拝聴し、被災地域の農作物やがれき受入れ等に関して、風評に惑わされず、正確な科学的情報を基に判断するべきであると改めて認識した。
2. エネルギー弁別型X線装置 〜X線でのエネルギースペクトルの検出と活用
静岡大学電子工学研究所 准教授
株式会社ANSeeN 取締役最高技術責任者 青木 徹
講師の青木先生は、株式会社ANSeeNの経営者でもある。この会社の名前の由来を真っ先に質問したが、もともとは「見えないものをみる」ということで、UnSeenという名前を考えたが、Unで始まる会社名もどうかということで、青木の頭文字のAをとって、ANSeenとしたそうである。もちろん、セキュリティチェックにも応用できる製品開発ということで、「安心」という意味も含んでいるのだろうが、会社名1つにも、意気込みやアピール性が感じられて興味深かった。
さて、本講演は、「見えないものを見る」新たなX線装置の開発の話である。X線による透過画像は、医療、非破壊検査、セキュリティチェックなどの分野で広く利用されており、より正確な透過情報が得られる検出技術が望まれている。しかし、現在利用されているX線検査装置は透過X線の強度情報のみを利用するため、本質的にアウトプットはモノクロであり、可視光領域での画像処理に比べると機能や精度の面で劣る。もちろん、X線でも光子のエネルギー分解機能を持たせて可視光と同じく波長情報を得ることができるが、低いスループット、冷却の必要性、検査時間の長さなどの制約から、工業用途には向かなかった。そこで、講師らは、常温でも高いエネルギー分解能を有し、高スループットを実現するX線デジタルスペクトロメータ(ANS-XDS0001)を開発するに至った。本デバイスは、次世代X線検査装置の技術検証や研究開発をターゲットとしており、図3に示すように、PCとUSB接続することにより測定条件を制御することで簡単な測定が可能である。
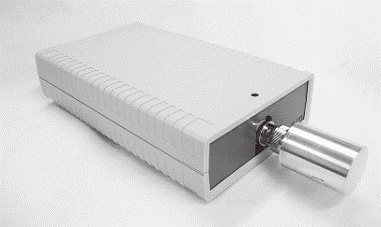
図3 X線スペクトロメータ ANS-XDS001
((株)ANSeeNより販売中)
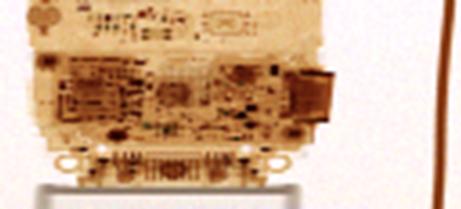
図4 エネルギー弁別して撮像したX線スペクトルを用いてエネルギー合成着色を行ったX線透過像
実際の測定例として、携帯電話基板の透過像を図4に示す。これは、X線スペクトルを低中高3段階のエネルギーに分割して合成着色した例である。デバイスとしてエネルギー区分したイメージングが可能であることを示している。このようなX線エネルギースペクトルを取得できる検出器では、学術的に正確な材料識別を行うことが可能である。たとえば、図5に示すように、スーツケース内のC(たとえば爆薬塊)、Ti(カメラ部品)、Al(スーツケース本体)を、エネルギー帯域を変化させて識別することができる。
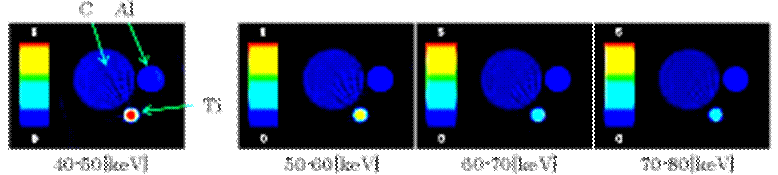
図5 各エネルギー帯のCT像
本デバイスが高スループットと高エネルギー分解能を両立できている理由は、主にその信号処理方式にある。本製品では、波形の立ち上がりのみを用いる「パルスハイト方式」を採用しているため、従来方式の10倍以上のカウントレートに対応しつつ、同等のエネルギー分解能を有しているのである。
そして、講演の最後に、「本製品により、これまで一般工業用途で利用が難しかったX線のエネルギー情報を用いたアプリケーション開発を進めることができ、講演で話した応用例の先行開発に大いに役立つと確信する」と締めくくられた。
(岩瀬 記)
3. 低線量放射線影響の虚像と実像:
ニューラルネットワークスによる解明
京都大学名誉教授 佐々木正夫
昨年3月11日の東京電力福島第一原発の事故以来、低線量放射線の健康影響は国民的関心事になった。しかしながら、100mSv以下の低線量域における発がんリスクに関しては、原爆被爆者の疫学調査からは学術的に明確な影響は導き出せないとされている。佐々木先生は、この問題に全く新しい独自の局面から切り込み、これまで明らかにされなかった興味深いデータを導き出すことに成功した。講演の冒頭から先生は、原爆被爆者の疫学調査で、100mSv以下の線量域の影響が対照群と統計的有意差がないということは、「影響がない」ことを意味するわけではなく、統計検定量の限界の問題であるので、この結論を一般化するのは誤りであると指摘された。佐々木先生の主張はさらに以下のように続く。ICRPの「直線・しきい値無し(LNT)仮説」は、放射線防護上の便宜的設定基準であって、放射線影響の学術的評価尺度ではないため、影響評価の実際にあたっては学術的に説得力のある線量効果関係が解明される必要がある。我が国における原爆影響研究は、戦後長い間封印されてきたために、被ばくの実際に即応できる迫力ある学術基盤が醸成されてこなかった。そのために、東京電力福島第一原発事故に当面して研究者の軸足が大きく揺れる事態に陥った。
そこで、佐々木先生は、情報工学等で用いられているニューラルネットワークス(ANN)の「integrate–and–fire」理論を取り入れた原爆放射線影響に関する連続確率密度関数の統計計算法を考案し、原爆被爆者の発がんデータベースに適応した。その方法とは、発がん率における被ばく線量対応の相対リスクの累積離散分布を求め、それを微分可能な連続関数として表し、微分変換により連続した相対リスク、または過剰相対リスクの確率密度関数で表現するというものである。1度聴いて、すんなりと理解できる理論ではない。しかし、そこから得られる情報には、これまでの常識を覆す驚きが隠されている。例えば、広島の男性肺がんの場合、過剰相対リスクが低線量域で負の値となる。このことは、低線量域でがんの自然発生率が抑制されていることを示している。すなわち、肺がん発生に関して、しきい値が存在することを意味する。興味深い解析結果である。
広島と長崎の被爆者における全固形がん過剰相対リスクについて、従来報告されてきた「階層線量区分法」と「ANN法」を比較すると、両者はよく一致することが分かった。このデータについて広島と長崎を別々に解析すると、興味深い事実が浮かび上がる。これまで、広島+長崎の固形がんに関する過剰相対リスクは、0.2-0.3Svでラクダのコブのように盛り上がることが示されていたが、この低線量域でのリスク上昇の原因は、長崎被爆者に由来することが明らかになった。この低線量域での発がんリスク上昇は、肺がん、肝がん、及び胆嚢がんの寄与による。その原因は、今後の検討課題であるが、佐々木先生は、長崎西山地区を中心としたプルトニウム汚染による内部被曝ではないかと推測している。同じ理由で長崎では対照地区の発がん率が高く、これが長崎での発がんリスクを低くしている可能性がある。長崎西山地区は、いわゆる“黒い雨”が降った地域であり、土壌からプルトニウムが検出されていることはよく知られている。ウラニウム235の生物学半減期(15-100日)に比べてプルトニウム239の生物学的半減期(200年)は格段に長い。プルトニウムによる長期内部被曝と発がんリスク上昇との関連性は重要な指摘であろう。
ANN法によって解析すると、男性の肺がん、胃がん、及び膵臓がんに顕著なしきい値が特異的に見られる。これらのがんほど顕著ではないが、肝がん、胆嚢がん、白血病では、男女に共通してしきい値がみられる。このような臓器特異的、また、性別特異的な差異がみられる理由として、喫煙の関与が疑われる。これについて、佐々木先生は、低線量被ばくによって喫煙による発がんが抑えられる結果、しきい値が現れるのではないかと説明する。ANN解析法によって得られた重要な指摘事項の一つである。
女性の代表的ながんである乳がんと子宮がんに関しても興味深い結果が得られた。乳がんでは、しきい線量はほとんどなく、線量の増加とともにリスクはほぼ直線的に上昇し、広島と長崎で差はみられない。これに対して、子宮がんでは、広島・長崎ともに共通して放射線の寄与は認められない。この場合、放射線は発がんのプロモーターとしても作用していない。子宮がん発症の主要な要因がヒトパピローマウィルスの感染であるからと考えられる。
白血病の解析においても、興味深い事実が明らかになった。広島被爆者の白血病では、しきい値がみられ、基本的には固形がんとよく似た線量効果を示す。これに対して、長崎被爆者の白血病では、三菱兵器工廠での作業員(九州外からの徴用者を含む)を除くと1Sv近くまで発がんリスクの低下がみられる。長崎は、成人T細胞白血病(ATL)の多発地域であり、全体の17% を占める。したがって、長崎被爆者の白血病にみられたしきい値は、低線量放射線がATL発症を抑制していることを示唆している。
さて、特定の固形がんや長崎の白血病などで典型的に現れた低線量域のしきい値は、なぜ生じるのであろうか。本講演で聴衆が感銘を受けたのは、佐々木先生が疫学データを独自のANN理論で解析して得られた全く新しい結果に対して、分子レベルでの説明まで考察していることであった。放射線発がんの出発点となるDNA2重鎖切断(DSB)の修復過程には、非相同末端結合(C-NHEJ)、Alt-非相同末端結合(Alt-NHEJ)、及び相同組換え(HR)の3経路がある(図6)。
低線量放射線被ばく時に活性化される適応応答現象では、低エラー性のC-NHEJが働いて、高エラー性のAlt-NHEJやHRを抑制する。佐々木先生は、このDSB修復の経路選択と低線量放射線影響が関連すると主張する。すなわち、低線量被ばくで非相同末端結合(C-NHEJ)が活性化されると、相同組換え(HR)が抑制され、喫煙などの影響による突然変異生成を低減化する。なぜか。タバコ代謝産物などによるDNA損傷はDNA付加体であり、これはDNA複製を介してDSBとなり、相同組換え(HR)によって修復される。
低線量放射線被ばくによって非相同末端結合(C-NHEJ)に修復経路が切り替わると、HR過程によって生成される突然変異が低下することになる。また、ATLの原因である成人T細胞白血病ウィルス(HTLV-1)の宿主DNAへの組込みには相同組換え(HR)が働く。したがって、非相同末端結合(C-NHEJ)の活性化は、HTLV-1DNA組込みを抑制し、ATL発症を抑えることになる。このようなDSB修復の経路選択は、クロマチンを形成するヒストンの修飾と連動しており、長期にわたって記録される可能性が指摘されている。
最後に、放射線による非がん疾患の代表である心血管疾患(心筋梗塞、脳梗塞)は、しきい値様反応を含めてがんによく似た反応を示すことが明らかになった。心血管疾患は、がんと共に死因の2大疾患であるので、共通した生物学的機構が存在するとすれば、非常に興味深い問題である。
以上、本講演にて紹介された佐々木先生の原爆被爆者疫学データの新しい理論に基づく解析では、これまでの解析では隠れていた新しい現象が次々と明らかにされた。本講演は、その現象の分子基盤に至る考察も解説され、それが今日的な魅力的課題として提示されている点において大いなる刺激を受けるものであった。
会員サロン
体質研究会と放射線
(公財)体質研究会・JAPI
主任研究員
常務理事 中村清一
最初に、講演者の中村清一氏により、現在の公益財団法人体質研究会の前身である財団法人体質研究会の歴史的経緯について説明がなされた。同研究会は、昭和16年(1941年)11月18日に京都大学名誉教授(医学部)辻寛治先生の寄付金により設立された。終戦後は、経済状態の激変で活動困難な時期もあったが、昭和32年には血液事業を開始、同39年には眼球銀行の設立、さらに同41年には、臨床検査部門が設置された。しかし、昭和57年頃より、これらの収益事業の経営が難しくなり、運営に支障がではじめた。昭和59年9月、菅原努先生が理事長に就任され、収益授業は全て移譲・廃止して受託研究中心の活動にするなど大改革が行われて今日に至っている。その間、平成22年には、公益財団法人としての認可を受けた。
現在の体質研究会の主な活動は、「ライフスタイルと健康」、「リスク評価に関する研究」、「低線量放射線の健康影響に関する研究」、及び「放射線照射利用の促進に関する活動」などである。また、機関誌として「環境と健康」の発刊、学会や研究の支援、シンポジウムや講演会の開催などを行っている。
まず、放射線照射利用促進協議会(JAPI)の活動から紹介された。JAPIは、平成10年(1998年)4月、会員約200人で発足した。現在、放射線は、診断・治療を含めた医療分野を始め、工業分野などで幅広く使われており、その利用は私たちの日常生活に深く浸透している。しかし、そのような中で食品照射は、食料の殺菌・殺虫を始め、発芽防止、熟度調整や加工食品の保存期間延長などに、多くの国で利用されているにもかかわらず、我が国ではその有用性について正しい評価が与えられていないのが現状である。日本は世界に先駆けてジャガイモの芽止めのための照射が認可されたが、その後の食品照射に関する進展は全くなく、世界的に取り残された状態にある。JAPIは、これまで「JAPIニュースレター」(年6回)の発行、年2回の講演会、さらに見学会等の開催を継続してきた。平成20年4月から、JAPIは体質研究会の活動の一つとして再発足し、JAPI協議員会の中に企画委員会、ニュースレター編集委員会、ホームページ委員会等を設置して、活動の幅を広げている。今後のJAPIの活動に期待したい。
次に、高自然放射線地域(HBRA)住民の健康調査の結果が紹介された。放射線のリスク評価体系は、原爆被爆者の寿命調査結果を基礎にして構築されてきた。しかし、高線量被ばくの影響から低線量被ばくの影響を推定するには解析数の限界から無理があること、また、高線量率での単回被ばくは、低線量率での持続的な低線量被ばくのリスク評価には適切な評価系とはいえないこと等が指摘されてきた。そこで、高自然放射線地域住民の健康調査が注目されるようになってきた。これらの地域住民は、生まれたときから生涯を通して高い自然放射線に曝されているので、低線量率で低線量の放射線被ばくの人体影響を理解する上で非常に貴重な調査対象である。
世界の平均自然放射線量は、年間およそ1〜2 mSvであるが、それより数倍高い自然放射線量を示す高自然放射線地域(HBRA)が知られている。例えば、1)中国・広東省陽江、2)インド・ケララ州カルナガパリ、3)ブラジル・ガラパリ、4)イラン・ラムサールなどである。このうち、体質研究会が現地の研究者と共同で行ってきた調査結果について、主に中国とインドの例についてここでは紹介する。
体質研究会は、中国・広東省陽江の高自然放射線に注目し、菅原努京都大学名誉教授を中心として中国の研究グループと共同で地域住民の健康に及ぼす低線量放射線の影響について、1992年から大規模な疫学調査を開始した(図7)。


図7 上:中国山東省陽江の住居 下:ウランやトリウムを含んだ粘土からレンガを作り住居に用いている。
調査項目は、1)個人被ばく線量(屋外線量、屋内線量、居住係数、移住調査)、2)死亡調査(がん死亡調査、死因調査、リスク評価)、3)交絡因子調査、4)染色体異常調査の4項目である。また、調査対象者の条件として、1)2世代以上同一箇所に居住していること、2)3ヶ月以上村を離れたことがないこと、3)医療被ばくの経験がないこととして、コホートを設定した。その結果、まず、年間被ばく線量については、内部被ばくも含めて対照地域(CA)で1.67 mSvに対し、高自然放射線地域(HBRA)では5.87mSvと推定され、約3.5倍HBRA住民の被ばく線量が高いことが明らかになった。疫学調査に関しては、1979〜1998年の間に、HBRA住民89,694人、CA住民35,385人について調査し、12,444人の死亡を確認した。
このうち、がんによる死亡者数は1,202人(9.7%)であった。解析の結果、HBRA住民のがん死亡率、非がん死亡率はCA住民のそれと有意な差はなく、HBRA住民のがん死亡率、及び非がん死亡率の相対リスクはほぼ1であった。高レベル自然放射線の発がんへの影響はみられなかったのである。では、染色体異常に関してはどうだったのだろうか。末梢血リンパ球中の染色体異常は、放射線に対して最も鋭敏で、しかも信頼できる生物学的指標である。解析の結果、二動原体染色体(不安定型染色体異常)の頻度は、累積被ばく線量に依存して増加することが明らかになった。
興味深いことに、相互転座(安定型染色体異常)に着目すると、頻度が二動原体染色体より数倍〜10倍ほど高く、しかもCA住民とHBRA住民とに差が無く、累積被ばく線量増加に伴う増加はみられなかった。
次に、インドのHBRA住民調査の結果について紹介する。体質研究会は、1999年よりインド・ケララ州のがん登録センター(RCC)と、6行政地区、約18万人を対象にした共同研究を開始した。その後、2007年には、ケララ州カルナガパリ地区全域にコホートを広げた。1991年の人口調査によると、カルナガパリ地区には385,103人の人々が住んでおり、世界のHBRAの中でも最も人口密度の高い地域である(図8)。
調査項目は、1)個人被ばく線量(全ての家屋での屋外線量と屋内線量、居住係数、移住調査)、2)疾病・死亡調査(がん罹患、がん死亡、非がん死亡、リスク調査)、3)交絡因子調査、4)染色体異常調査である。まず、年間の外部被ばくによる被ばく線量について調べたところ、CAで0.8mGyに対し、HBRAで3.6mGyであり、約4.5倍HBRA住民の被ばく線量が高いことがわかった。HBRAの特定の場所では、70mGyであった。これらの結果に基づいてコホートを設定し、このうち30〜84歳の住民69,958人についてがん罹患率を分析した。2005年末までに、白血病30人を含む1,379人のがん症例が確認された。解析の結果、HBRA住民のがん罹患率は、CA住民のそれと有意差がなかった。また、がんの部位別の分析でも、累積被ばく線量とがん罹患率との間に有意な関係はみられなかった。また、二動原体染色体を指標とした染色体異常調査では、HBRA住民の染色体異常は、累積被ばく線量に依存して増加がみられた。これらの結果は、中国広東省陽江で得られた結果を支持している。


図8 上:インド・ケララ州カルナガパリ 下:漁民はトリウムを多く含む砂浜で暮らしを営む。
以上の中国、及びインドにおける高自然放射線地域(HBRA)住民の健康調査は、自然環境放射線が累積被ばく線量に応じて住民のリンパ球に染色体異常を誘発するが、それが住民のがん発生率やがん死亡増加につながっていないという重要な事実を明らかにしている。これらの成果は、昨年UNSCEAR会議で正式な検討課題として取り上げられることになり、現在、調査結果の報告書を作成中とのことであった。今後の展開が楽しみな研究成果である。
(児玉 記)