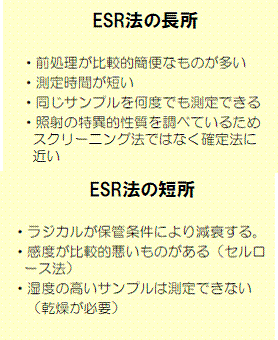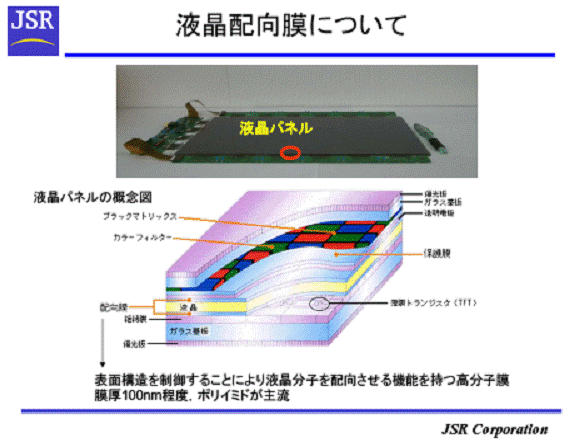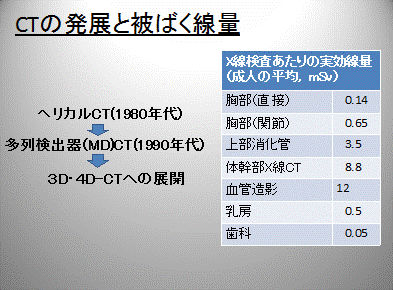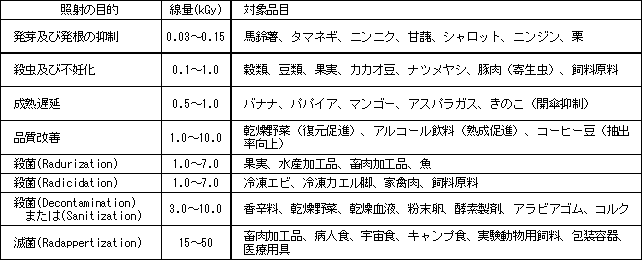�P�D���ˌ�����ђ����q�����p���������q�ޗ��̍\�����
JSR������Ўl���s�����Z���^�[�@
�y�i�@�N�Y
�V�����ɏ�������Ƃ̂���l�Ȃ�A�ԓ��̓d���f���ɂ�����JSR�i���j�̃R�}�[�V�����E���b�Z�[�W������Ă��邱�ƂɋC�����Ă����邾�낤�B�ŋ߂͉p����J�^�J�i�̊�Ɩ��������Ė��O���������ł́A���̉�Ђ�������Ȃ��ꍇ������JSR�����̈�ł���B�N�y�̕��Ȃ���{�����S���ƌ������ق����Ƃ��肪�ǂ��Ǝv���BJSR�̏o���̓^�C���p�����S�������鍑���Ђł���B���̌㖯�c������č��ł̓^�C���p�����S���̋����ȊO�ɉt���p�l���֘A�ޗ��A�����̐����p���W�X�g�������̍����q�ޗ�������f�ރ��[�J�[�Ƃ��Đ������Ă���B�y�i�u�t�͎��Ђ̗��j�ƌ��݂̑���ɂ킽�鐻���i�ڂȂ�тɐ����E�������_�ƂȂ��Ă��鍑���O�̎{�݂��Љ�ꂽ��A��͏��i�̈�ł���t���p�l���p�ޗ�����ѐV�K�̏ȔR��Ή��^�C���ޗ������グ�A�����̊J���Ɍ������Ȃ����ˌ��Ȃ�тɒ����q�̗��p�ɂ��ču�������B�ߔN�A�����q�ޗ��ł́A�i�m���x���ł̕��q�v���嗬�ƂȂ�A���̍\����͂ɂ͎s�̂̃��{�p�v�����u�݂̂ł́A�Ή�������Ȃ��ꍇ�������Ȃ�A��^���u�̎{�݂𗘗p������Ȃ��Ȃ��Ă���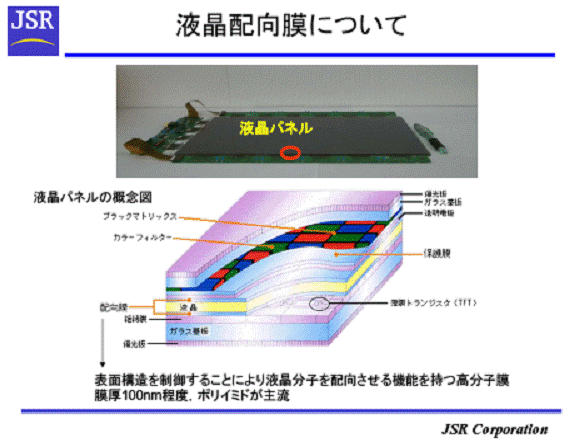 �����ł���B
�����ł���B
�}1�@�t���p�l���̍\��
�@�ŋ߂̖w�ǂ̕\���f�q�͉t���p�l���ɂȂ��Ă���A�\���i�ʂ̐��\����𑽂��̃f�o�C�X���[�J�[�������Ă���B�t���p�l���͑��w�\���ɂȂ��Ă���A���S�̉t���͗�����100nm���x�̌��݂̃|���C�~�h�̔z�����ŋ��܂�Ă���B�t���͖{���z�����鐫����L���邪�A�\�ʔz�����̍\���ɂȂ���ĕ��Ԑ��������邽�߁A���̖��\���̔����I�m�����d�v�ł���B�u�t��͗����ّ�w��SOR�{��(BL8)��SPring-8�̕��ˌ��{�݂𗘗p���āA���\���̉�͂��s�����B�|���C�~�h���͌����̃|���A�~�b�N�_�n�t����Ղɓh�z���A�M�������s���ĖړI�̖����쐬����̂ŁA�M�����ɔ����|���C�~�h���̌`���ߒ���CO�\���̃X�y�N�g���ω��ɒ��ڂ����w���z���[���\������@(NEXAFS)�ɂ���Ė��炩�ɂ��邱�Ƃ��o�����B����ɃC�~�h���������i�ނɂ�āA���̕��ʐ������サ�A�\�ʂɐQ�Ă��镪�q�̊������������邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B�܂��A�|���C�~�h���̕\�ʂ�z�ł�����Ƃ������r���O�������t���̔z�����̐���ɗL���ł��邱�Ƃ��m���Ă��邪�A���̏����ɂ���Ăǂ̂悤�Ȗ��\���ω��������Ă��邩�́A���炩�ɂ���Ă��Ȃ������B����̌��ʁA���r���O�ɂ�莅�{��̃|���A�~�h�����r���O�����ɉ��L����ăx���[�����\�ʂɕ��s�ɔz�u���銄�������܂邱�Ƃ������ƂȂ����B����Ƀ|���A�~�h���Ɛڂ���t�������q���̔z����Ԃ��������A�t�����q��CN�\���ɒ��ڂ��Ĕz�����̔z���ɂȂ���ĕ���ł��邱�Ƃ��m�F�ł����B���̌��ʂ͔z�����̍\���ɂȂ���ĉt�������q�w���z�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B���ɉ�ܖ@�ɂ�钲�����s�����B�w���������\�ʂɑ��ăX���X���̔����p�œ��˂������ꍇ�A���ˊp���S���˂̗ՊE�p�����傫���ꍇ�ɂ́A�w���͎��������ɂ܂œ���̂ɑ��āA�ՊE�p�����������ꍇ�ɂ͑S���˂��邪�A�i�m���[�g�����x�̐[���܂ł͓����ĉ�܌��ۂɊ�^����B������G�o�l�b�Z���g�g�ƌĂ�ł���B��ʂ̂w����ܑ��u�ł͂��̋��x���キ�G�o�l�b�Z���g�g�ɂ���܂͊ώ@����ł��邪�ASPring-8�̂w���ł͉\�ɂȂ�B���r���O���������z�����ɂ����Ă͓��ˊp�̑傫���ꍇ�ɂ͗L�ӂȈٕ����͔F�߂��Ȃ������̂ɑ��āA�G�o�l�b�Z���g�g�ɂ���܂ł̓��r���O�����ɔz���������q���������Ƃ��m�F�ł����B
�@�^�C���̐�������p���܂ł̃��C�t�T�C�N���œ�_���Y�f�����̊������ł��傫���͎̂g�p���ł���B���낪���R�ƃO���b�v�͓͂w���̊W�ɂ���̂ŁA�ȔR��^�C���v�ɂ͗��҂����܂��o�����X�����邱�Ƃ��v�������B�^�C���͕��G�ȍ\�����Ƃ邪�A���낪���R�ɊW����̂́A�n�ʂƐڂ���g���b�h�̕����ł���A�d�v�ȕ��ނ��t�B���[�ł���B�����ɗp������X�`�����u�^�W�F���S��(SBR)�Ȃǂɂ͕⋭�ނƂ��āA�J�[�{���u���b�N��V���J��1/4���x���荞�܂�Ă��邪�A�ŋ߃V���J���ǂ����Ƃ����炩�ɂ���A�ȔR��^�C���Ƃ��Đ��������悤�ɂȂ��Ă����B�������V���J�͕��U���ɗ��̂ŁA�V�����J�b�v�����O�܂��S���ɓY�����邱�Ƃɂ��A�V���J�U�����邱�Ƃ��}���Ă����B�ߔN�A�S�����q�̖��[�ɃV���J�Ɣ������₷�����\������閖�[�ϐ��Ƃ�����@���̗p�����悤�ɂȂ����B���I�S�e����������ђe�����̘c�ˑ����̉���ɂ����Ă����[�ϐ��ނ̂ق����D��Ă���B
�Y�������⋭�ނ̕��U�̒��x�ׂ�ɂ͌�������p���Ĉꎟ���q����т��̈ꎟ�ÏW�̂̃T�C�Y���ώ@���邪�A�J�[�{���u���b�N�̏ꍇ�ɂ͌��w�������ł́A�����Č����Ȃ����߁A�d�q���������p������B�����ł̓V�����J�b�v�����O�܂Ɗ��\��������ꍇ�̈ꎟ���q�ƈꎟ�ÏW�̂̃T�C�Y���z��SPring-8��2��ނ̏��p�U�����u�Œ��ׁA���҂ňꎟ���q�̃T�C�Y�͓����ł����Ă��A�V�����J�b�v�����O�܂��g�p�����ꍇ�ɂ͈ꎟ�ÏW�̂̃T�C�Y���傫�����U�����܂�ǂ��Ȃ������̂ɑ��āA���\������ꂽ�ꍇ�̈ꎟ�ÏW�̂̓T�C�Y�������A�ǂ����U���Ă����B�����̎�@�ł͎����̃T�C�Y�ɐ����邽�߁A��^�̎����ł�����q�x�N�g���͈̔͂��傫���Ƃ�钆���q���p�U���ɂ�鑪����s�Ȃ��w���ɂ�鑪��ƕ�����nm�����m�ɂ킽��L���T�C�Y�̗��q�̕��U��Ԃ̒m���邱�Ƃ��\�ƂȂ����B�����q���p�U������͌��q�͌����J���@�\���C�̂R���F�ɐݒu����Ă��鏬�p�U�����葕�u(SANS-J�����PNO)��p���Ē��������B���[�ϐ��ނł͈ꎟ�ÏW�̂̃T�C�Y������������ɍ����\��������Ă��邱�Ƃ����炩�ɏo�����B
�u���̒��߂�����ɂ�������SPring-8�A�t�H�g���t�@�N�g���[�A�����ّ�wSR�Z���^�[�A��B�V���N���g�����������Z���^�[�Ȃǂ̕��ˌ��{�݂���{���q�͌����J���@�\�̒����q�{�݂̎Y�Ɨ��p���i�ɂ���āA���Y����̌������傫���O�i�������Ƃ��������ꂽ�B
�Q�D��Âƕ��ː�
���s��w���q�F������
���ː����S�Ǘ��H�w��������@�����瑾�Y
�����u�t�͋��s��w��w�@�_�w�����Ȃ��C����A���ː���w�����������i���㌤�j�Œ����Ζ����ꂽ��A���s��w���q�F�������Ɉڂ�ꂽ����ŁA���݈��S�Ǘ��{�����߂Ă�����B����͕��㌤����̂��o������ɁA���ː����Â̐�[�I�Șb��ƕ��ː��̈��S�̉ۑ�ɂ��ču�����ꂽ�B
�u���̖`���Ɍ�����O�ɔ������ꂽ�G���u���Y�t�H�v��CT����ƃK���ɂ�����ƌ�������̋L������X�f�ڂ��ꂽ�̂����������ɏo����ĉ䂪���̌���̏Љ�����ꂽ�B�d�ԓ��̂�L���ɂ͉ߌ��Ȍ��t���x���Ă��邪�A�L���̓��e�͂���������O�̂��Ƃ�������Ă���A�}�X�R�~�͔�����߂ɁA���ː��ɑ��Ă������̂悤�ȃZ���Z�[�V���i���Ȉ��������āA��O��f�킹��B1895�N�̂w���̔����ȗ��A�̂̒���������s�v�c�Ȍ��Ƃ��Ăw���̗��p�͈�w�̕���ł߂��܂����i���𐋂��Ă����B�����̎B�e�ɂ��Ă��ȑO�͎B�e���Ɂu�����Ƃ߂āv�̎��Ԃ����������B�ߔN�ł́A�����̃t���b�g�p�l���̂悤�ȃf�B�W�^���@��̐��\���オ�ڊo�܂����A�B�e�ɔ���������ʂ̒ጸ�����}���ɐi�݁A�����B�e�̏ꍇ�ł́A�����u�̘I�o�Ŕ�����ʂ�0.1��Sv�̃��x���܂łɉ������Ă��邱�Ƃ��������ꂽ�B
�����āA���ː��f�f�Ƃ��ĕ��y�̖ڊo�܂���CT (Computer Tomography)��PET (Positron Emission Tomography) �ɂ��Ă̘b����Љ�ꂽ�BCT�͑̂̂w���f�w�ʐ^���Ƃ��@�Ƃ��āA�p��EMI�Ђ̃n�E���X�t�B�[���h��ɂ���Ĕ��\����A���̌��тɂ����1979�N�Ƀm�[�x�������w�E��w�܂����^���ꂽ�B�������Ȃ���A���̂悤�Ȃw���B���@���f�f�ɗL���ł��邱�Ƃ����Ɏ����Ă������{�l�������M�����m�ł���B�����͂b�s�����ɏo��10�N�ȏ�O�ɂw����]���f�B�e�@���J�����Ă����B���������̕��@�͉�]��i�K�I�ɍs���Ăw���t�B�����ɎB��������̂ł���A�A�i���O�g���O���t�B�Ƃ������ׂ����̂ł������B�n�E���X�t�B�[���h��͓d�q�v�Z�@�ƌ��o�퐫�\�̐i�W�ɃT�|�[�g����Ăb�s�@�����������E�ɕ��y�������Ƃɂ��m�[�x���܂ɂȂ������B�m�[�x���܂ɂ̓^�C�~���O���K�v�ł��邱�Ƃ��w�E���ꂽ�B���{�ł�1975�N�������q����CT����������Ĉȗ��A���ł�1��3���قǂ�CT������A�S���ǂ��ɏZ��ł��Ă�������CT������������������Ă���B���̌�w���J��CT�ƌĂ�鑕�u�̊J���ɂ��A3�����I�B�e���\�ƂȂ����B���㌤�ł̓w���J��CT���u�𓋍ڂ������f�Ԃ�2����A���܂��ܑ��{�����l�a�Z���^�[�ɂP���݂��o���Ă��������ɍ�_��k�Ђɑ������A��Ў҂̌��f�ɑ傫�Ȋ�^���������A����V�������Ĕp�Ԃ�����Ȃ��Ȃ��������ł���B�����ł͐����ƌ��o��̐��𑝂₷���Ƃɂ��A�Z���ԎB�e�Ńw���J��CT�B�e���\�ɂȂ��������łȂ��A4�����B�e�Ə̂��ĐS���̉^���܂ł��B������@����J�����ꂽ�B����A�z�d�q�j���܂𓊗^���Ď�ᇕ������x�����O����PET�@��10�N���O�ɂ́A��ʂɓ���݂̂Ȃ��f�f�@�ł��������A���ł͍J�̕��ʂ̘b��ɂȂ���蒅���Ă����B�ߔN��CT��MRI��PET��g�ݍ��킹�āA��萳�m�Ɋ����肷��@�킪�o�Ă���B����ɃI�[�v��PET�Ə̂��āA��p�����Ȃ��瑦���Ɋ����̐؏���PET�Ŋm�F�����@��A���q���ɂ��K�����Â̍ہA�ł����Y�f�C�I���ɂ���Đ�������z�d�q�j��̒Y�f11����̐M���𑨂��Ď菇�ʂ�ɒY�f�C�I���������ɓ��B���Ă��邩���m�F�����@�̊J�����i�߂��Ă���B�����͉�������q�C���[�W���O�̐i�W�ɂ��Ƃ��낪�傫���A�F�m�ǂȂǔ]�̋@�\�����ɂ��K�p�����悤�ɂȂ��Ă���B�������Ȃ���ACT�����ɂ����������ʂ͂����Ԃ�ጸ�����ꂽ�Ƃ͌�������10mSv���x�ł���APET�ƕ��p�̏ꍇ�ɂ�15mSv���x�ƂȂ�B���̂��Ƃ���̕��Y�t�H�ł̋L�q�ɂȂ����Ă���B���Y�t�H�̋L���ł͂�������CT��������ƃK���ɂ�����悤�Ȉ�ۂ�^���A��ʎs����CT�������Ȃ��ق����ǂ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������͋C���������ꂩ�˂��A���ː��f�f�̗L�p����W���邨���������B�����u�t�͂��̃��X�N�̖ڈ��Ƃ���1000�l�̏W�c���Ƃ肠�����ꍇ�ɁA���̓���400�l���x�͗l�X�ȗv���ɂ���ăK���ɂ����邪�A10mSv�̔�������ꍇ�ɂ͐��U�ł��̒��̈�l���x��CT�����������ŃK���ɂ�������x�ł���Ɛ������ꂽ�B���ː���100�`200mSv�ȏ��������ꍇ�ɃK���ɂ����銄���͔�����ʂɔ�Ⴗ�邱�Ƃ͊m������Ă��邪�A100mSv�ȉ��̏ꍇ�ɂ��Ă͉Ȋw�I�ȍ����̂���f�[�^�͖w�ǂȂ��B���s�̕��ː���Q�h�~�@�ł͒���ʔ���ɑ��ẮA100mSv�ȏ�̃��X�N�����ʑ��֊O�}���Ă��邾���ł���B�����u�t���10mSv�̕��ː���������ꍇ�ɑ̑g�D���@���Ȃ锽��������������`�q�̋����ɒ��ڂ����������s�����B��`�q�͉��x�Ȃǂ̈��q�ɂ���Ă��ς��̂ŁA���̎����͑�ς����������ł���B�畆���`������悤�ȑ@�ۉ��g�D�ɂw���Ǝ�10mSv�̔���W�c�Ɣ�����Ȃ��W�c�̂Q���T����̈�`�q�ɂ��ĒO�O�ɒ����������ʁA���O���ɂ��₯�ǂ̂悤�ȉ��ǂɔ�������T�̈�`�q�ɕω��͌���ꂽ���̂́A�K���̔����Ɗ֘A�����`�q�ɂُ͈�͌����Ȃ������B
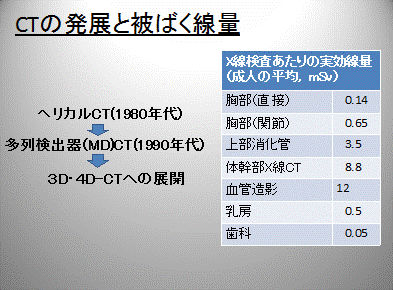
�}2�@CT�̔��W�ɔ����e����̔������
�u���̍Ō�̕����ł͎��ÂɊւ����ː��ɂ��Đ������ꂽ�B�w���̔�����A��������������ÂɎg�����݂͐F�X�Ȃ��ꂽ���A�����ł�1899�N�̔畆�K���̎��Â̐������ŏ��̂悤�ł���B�����̓��W�E�������p���ꂽ���A�����ɕ��˂����d�q�Ȃǂ̒m�������܂�Ȃ��Ĕ픘�̉e�����傫�������B���݂̏��������Â͔����̗e��Ɋi�[���ė]���ȕ��ː��͎Օ����Ďg�p���Ă���B���W�E���͓V�R���璊�o����̂ō����ł��܂蕁�y���Ȃ��������A�₪�Č��q�F�Ǝ˂Ő����o����R�o���g60�ɂƂ��Ă�������B����̓e���R�o���g�ƌĂ�A���ł���d�̑����r�㍑�Ŏg���Ă��邪�A��i���ł̓��C�i�b�N�ɂ�鎡�Â����S�ɂȂ��Ă���B�Ǝ˂ɂ�鎡�Â͑g�D�̕��ː����̈Ⴂ�𗘗p���Ă���A�]���͕������Đ��\��̏Ǝ˂��������A�ŋ߂ł͑���ʂ������݂̂ɏW�����ďƎ˂���K���}�[�i�C�t�Ƃ��T�C�o�[�i�C�t�Ȃǂ̕��@���g����悤�ɂȂ��Ă���A�R���s���[�^�̔��W�ɕ����Ƃ��낪�����B��������W�I�T�[�W�F���[�ƌĂԁB���݂̓u���b�O�s�[�N�ł̐��ʂ������������Ȃ邱�Ƃ𗘗p�������q�����Â���ɂȂ��Ă���A�H�w�I�Ȏ��ӋZ�p�̔��W�̊�^�ɕ����Ƃ��낪�傫���B���q�����Â�300���~���炢�����邪�A������ی��K�p�ɂȂ�ł��낤�B
���q�F�������ł͒����q�𗘗p������f�ߑ����Ö@����ɔ]��ᇂɑ��čs���Ă���B
��Ís�ׂɑ��Ă͕��ː�����̐��ʋK�����K�p����Ȃ��̂ŁA��Õ��ː�����ɂ��ĊW�ґS�̂ɗ��𑣐i���d�v�ł���B
�R.�@�H�i�Ǝ˂̓��O�ɂ����铮���ɂ���
���{����w��w�@���w�n������
�Óc�@���
���N�A�H�i�Ǝ˂̌����Ɍg����Ă����Óc�u�t�ɍŋ߂̍����O�̏ɂ��ču�������肢�����B
���E�l���̋}���ȑ���ɔ����A�K�v�ȐH�Ƃ̐��Y�ɂ͐悸�_�n�̊m�ۂ���ɂ��_�Ɛ��Y�̑����}��K�v�����邪�A����ɂ͌��E�����B����ł͎��n��̖Ŏ����l�X�ȗv���ɂ����3�����x����Ƃ�������������B
���ː��Ǝ˂͉��x���オ��Ȃ������ł���A���ߗ͂ɗD��āA��ʏ������\�ȕ����E�ۂł���A�|�X�g�n�[�x�X�g�_����g��Ȃ��čςނȂǂ̗��_������B�Ǝː��ʂ̓K�ȑI���ɂ��A����h�~�A�E���A�ŋہE�E�ۂ��\�ł���A���L���H�i�ɑ��钷���ۑ����\�ʼn��p���삪�L���B
�H�i�ɑ�����ː��Ǝ˂͌����A�R���p�Ƃ��ė①�Ȃǂ�v���Ȃ��H�i�����@�Ƃ��Č������Ȃ���A1970�N��ɂ͂��łɋZ�p�I�����͏I���A���̌���S�������A���p�������Ɛi�B�H�i�Ǝ˂̎��p���ɂ͏ƎːH�i�̌��S���]�����K�{�ł���B��{�I�ɂ́@�P�D�Ő��w�I���S���i�}���Ő��A���K�����A��`�Ő��A�זE�Ő��A�Ê�Ő��Ȃǁj�A�Q�D�������w���S���i�ˑR�ψقɂ�鉘���Ő������̓Ő������j�A�R�D�h�{�w�I�K�i���i�h�{���̒ቺ�A�A�����M�[�������̐����j�@��3���ڂɂ��ď\���Ȍ������K�v�ŁA����3���ڂ�S�ۂ���K�v������B�����̌�����1960�N��ȍ~�ɍs��ꂽ�c��Ȏ������ʂɂ��āA���ېH�Ƌ@�ցA���ی��q�͋@�ցA���ەی��@�\�̍������ƈψ���ő����I�ɐR�c����āA1981�N�ɂ͕��ϐ��ʂ�10kGy�ȉ��̏ƎːH�i�ɂ����Ă͂��̌��S���ɑS�����͂Ȃ����Ƃ��錾���ꂽ�B����Ɋ�Â���1983�N�ɂ͍��ېH�i�K�i�ψ���(Codex�ψ���)�Łu�ƎːH�i�Ɋւ��鍑�ۈ�ʋK�i�y�щ����K�́v���쐬����A���ۊԂł̐H�i�Ǝ˗��ʂ̊�{�I�K�i�ƂȂ��Ă���B�]���A���W�I�g�L�V���i�n�鏒�j�A�|���v���C�s���i�����j�Ȃǂ̓Ő��̖�肪��N����āA�H�i�Ǝ˂ɔ�����l�X�̍����ɂȂ��Ă��邪�A����̏ꍇ����̒ǎ��ɂ���čČ������F�߂�ꂸ�A���E�I�ɂ͖��Ȃ��Ƃ���Ă���B���{�ł͐H�i�Ǝ˂͈�؋֎~�ł���A�n�鏒�̉�~�ߏ����͗�O�K��ł���B���̓_�͈�×p��Ȃǂ̕��ː��ŋۂ��@�Ŗŋۏ����̈���@�Ƃ��āA�F����Ă��邱�ƂƂ͑S�����قȂ��Ă���B
���O�̐H�i�Ǝ˂̏����ʂ͒�����M���ɕč��A�E�N���C�i�A�u���W���A��A�A�x�g�i���Ƒ����A���{�͔n�鏒�݂̂ł��邪�A�����ʂƂ��Ă̓x�g�i���ɑ����Ă���B�؍��ł�20�i�ڈȏオ������A�x�g�i���ł͗Ⓚ�G�r�ȂǂɏƎ˂��s���Ă���B�o�ϋK�͂ł݂�Εč������i�̍������h���̏Ǝ˗ʂ������g�b�v�ł���B�ŋ߂͉ʎ��ɑ���E����ŋۂɑ���Ǝ˂����E�I�ɑ�����X���ɂ���A�n���C�ł̓p�p�C���̒n���C�~�o�G�����h�~�ɕϊ��w���Ǝ˂ɂ��E���������s���A����ɕč��ƃ^�C�̊Ԃł̓^�C�Y�̏Ǝˉʎ��̕č��ւ̗A�����F�߂���Ȃǂ̗Ⴊ�o�Ă����B�C���h�Y�̃}���S�[�͍ݕăC���h�l�ɐl�C������A�C���h�ł̏Ǝˏ����ς݃}���S�[�͕č��ɗA������Ă���B�Y�n����̒������ړ���]�V�Ȃ������č��ł́A�V�N�x��ێ����邽�߂ɃC�`�S�̕\�ʂ̖h�J�r�ɏƎˏ������Ȃ���A�n���o�[�K�[�p�①�ғ��ɂ��Ǝ˂���Ă���B�X�y�[�X�V���g���Ȃǂ̋@���Œ����F���H�ł͖h�u��A�Ǝ˂ɂ��E�E�ŋۂ����������A���̂������œ��ڂł���H�ނ������A���j���[���L�x�ɂȂ����B���O���ł̏ƎːH�i�̋��i�ڂ������ɂ�āA���{�ł͗A���H�i�̒��ɏƎ˂̍��Ղ̂��鎖�Ⴊ��������B���{�ł�1967�N����1981�N�ɂ����Ă̐H�i�Ǝ˓��葍�������̒��ŁA�n�鏒�i��~�߁j�A�^�}�l�M�i��~�߁j�A�āi�E���j�A�����i�E���j�A�E�C���i�[�\�[�Z�[�W�i�E�ہj�A���Y���萻�i�i�E�ہj�A�~�J���i�\�ʎE�ہj�̂�����V�i�ڂ�ΏۂƂ������S���̌������s���A�S�Ă̕i�ڂɂ��Ė��Ȃ����Ƃ��m�F����āA1972�N�ɂ͐��E�ɐ�삯�Ĕn�鏒�̉�~�ߏƎ˂������ꂽ�B
�\�P�@�H�i�Ǝ˗��p�@
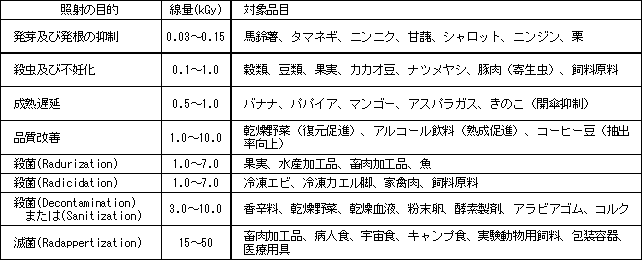
���͏�L�̑��̕i�ڂɂ��Ă�������������j�ł��������A�n�鏒�̋����_�@�ɏ���Ғc�̂̋������Ή^���ɂ���āA�v�悪�ڍ����āA�����Ɏ����Ă���B���݁A�n�鏒�̉�~�ߏƎ˂͖k�C���m�y�_����8��g�����x�s���Ă�����x�ŁA�m�y�_���̑S�戵�ʂɐ�߂銄���͏������A����ȊO�͒ቷ�������Ă���B�č��ɂ����Ă͓��{�ŏ����܂Ƃ��Ă̂ݎg�p�������Ă���N�����v���t�@����p������~�ߏ������s���Ă���B���݁A���h���̋ƊE�����ɑ��č��h���̕��ː��Ǝ˂̔F�����߂Ă��邪�A���̔w�i�ɂ͏��O���ł͍��h���ւ̕��ː��Ǝ˂���ʓI�ɂȂ��Ă����������B�Ӟ��̎��͌��n�œV����������A�y�R���̉�������\���������B�Ӟ��̑����̓n���Ȃǂ̒����H�i�Ɏg�p�����W������{�̐H�i�q���@�ł̓O����������1000�ȉ��̋ې��ɂ��邱�Ƃ��v������A������N���A���邽�߂ɂ́A���{�ł�120�����x�̉ߔM�����C�ɂ�鏈�����s���邪�A���h�����L�̕����Ȃ�Ȃ����߂ɂ͕��ː��������D��Ă���B���O���ł̍��h���̕��ː�������������ɏ]���āA�Ǝˍ��h�����A�������\���������Ă��邪�A���{�ł͋֎~����Ă��邽�߂ɁA�C�t�����ɗA�������ꍇ�ɂ͕ԑ���������A�ƊE�Ƃ��Ă͑傫�ȑ����ƂȂ�B�O���Œʏ�s���Ă����@�ł���Γ��{�ł������ꂽ�����ǂ��ƍl�����邽�߁A�ƊE�ł͋��\�������Ă���B���̒S�����ǂł�������J���Ȃ͍��h���Ǝ˂Ɋւ���Ē������O�H�����Ɉϑ��������A�悤�₭�T���ɕ����o�āA���̒��ŃA���L���V�N���u�^�m���̓Ő��ɂ��Ă���Ȃ钲�����K�v�Ƃ��ꂽ�B�A���L���V�N���u�^�m���͓��Ȃǂ̎��b�ɏƎ˂����ꍇ�ɐ�������邱�Ƃ��m���Ă���A���̓Ő��Ɋւ��Ă����[���b�p�ȂǂŌ������s���Ă������A�ʏ�̐ێ�ʒ��x�ł͑S�����͂Ȃ��Ƃ���Ă�����̂́A���ł͍����ł̌����Ⴊ�s���Ƃ��ꂽ�悤�ł���B���݁A�����̌����҂ň��S���̊m�F���s���Ă���Œ��ł��邪�A���̌o�܂��炻�̕��͂��H�i�Ǝˌ��m�@�Ƃ��Ďg�p�o���邱�ƂƂȂ�A����22�N3���Ɍ���@�̈�ƂȂ����B�H�i�Ǝ˂͑����̍��X�Ŏ��p�����i��ł���ɂ��ւ�炸�A�䂪���ł͑��ς�炸�u�n�鏒�v�̉�~�߂ɂ����K�p���F�߂��Ă��Ȃ��B�����P�V�N�ɓ��t�{����o���ꂽ���q�͑�j�̂Ȃ��ŁA�H�i�Ǝ˂����グ��ꂽ�̂��@�ɁA�L����e�n�ŊJ����A�����̈ӌ����ꂪ�݂���ꂽ���A���łɋƊE�����o����Ă��鍁�h���̏Ǝ˔F�\���ɂ��āA�R���͐i�W���Ă��Ȃ��悤�ł���B
���H�i�Ǝˌ��m�@�̍ŋ߂̓���
�i���j�R�[�K�A�C�\�g�[�v�@�A��@���s
�@�R�o���g60�ɂ��K���}���Ǝˎ����ЂƂ��Ē����ȁi���j�R�[�K�A�C�\�g�[�v�͕����Q�P�N�Ɂi�Ёj���{�A�C�\�g�[�v����b�ꌤ�����̎{�݁E�X�^�b�t�̏��n���A���݂͂R��̏Ǝˎ{�݂�L����×p��̖ŋہA�����q�̉����Ȃǂ̋Ɩ�����e���̌����E���C�Ȃǂ��s���Ă���B�I���T�ł͕���22�N7���ɓ��Ђ̌��w�������Ă�������������ł���B
�A��u�t�ɂ͑O�̌Óc�u�t�̍u���̌���āA�H�i�Ǝ˂̌��m�@�ɂ��ču�������肢�����B�u���ł͐悸���Ђ̌�������ыƖ����e�̏Љ��A�H�i�Ǝ˂̌��m�@�S�ʂɂ��ďЉ�A����ɂ����g���g����Ă���ESR�@�ɂ��Ă��̏ڍׂɂ��Ęb���ꂽ�B
�@���łɌÓc�u�t���q�ׂ��悤�ɓ��{�ł͐H�i�ɑ���Ǝ˂͐H�i�q���@�ɂ�茴���֎~�ł���A�]���ĐH�i���Ǝ˂��ꂽ���ǂ��������肷���i���K�v�ł���B����ɕ���18�N�ɊJ�Â��ꂽ���q�͈ψ���̐H�i�Ǝ˂Ɋւ���L����ŐH�i�Ǝ˂��������ɂ͌���@�Ƃ��Ă̌��m�@���K�v�Ƃ��ꂽ�B�������A�H�i�ɑ���Ǝ˂͌����H�i�ɕω���^���Ȃ����Ƃ��ő�̃����b�g�ł���̂ɁA���m�@������ƂȂ�B���݊C�O�ŗp�����Ă��錟�m����@�̃^�C�v�ɂ͇T����V�܂ł���A�T�͊m��@�A�U�͏��m��@�A�V�̓X�N���[�j���O�@�ł��邪�A���s�ł͂܂��m��@�͂Ȃ��B���݂̐H�i�Ǝˌ���@�ł�臒l�ȏ�ł���A�Ǝ˂Ɣ��肷�邪�A臒l�����̏ꍇ�ɂ́u�Ǝ˂��ꂽ�Ƃ͌����Ȃ��v�Ƃ�������ɂȂ�A��Ǝ˂Ƃ͌���Ȃ��B
����͏Ǝ˂���Ă��Ă����炩�̗��R�ŁA���莞�Ɍ������Ă��܂����\����ے�o���Ȃ�����ł���B���{�̌��s����@��TL�i�M���~�l�b�Z���X�j�@�i����19�N�j�ɑ����ĕ���22�N3���ɂ��̉���@�y�уV�N���u�^�m���@���������ꂽ�BTL�@�͐H�i�ɕt�����Ă���ɔ��ʂ̍z����O�O�ɍ̎悵�āA���̔M���~�l�b�Z���X�𑪒肵�A�Ǝ˂̗L���肷����@�ł���B�����A�H�i�ɕt�����Ă���z���̗ʂ͏��Ȃ���ɁA�̎悵���z���ɕ��ː��Ǝ˂��ꂽ�ꍇ�ɔM���~�l�b�Z���X������ł��邩�ǂ����������łȂ����߁A�M���������Ȃ��ꍇ�ł��A�ēx���̃T���v���ɑ��Ċ�Ǝ˂��s���Ċm�F���Ƃ��Ƃ��K�v�ƂȂ�B�䂪����TL�@�͊O���̊����݂Ė�肪����Ƃ���Ă������A����PL�@��MDL(Minimum
Detectable TL level)�̓����ɂ�蓯���̊�ɂȂ����B�V�N���u�^�m���@�͓��ނȂǂ̎��b���Ǝ˂��ꂽ�ꍇ�ɂ̂ݐ�������A���L���V�N���u�^�m����GC-MS�ő��肷�邪�A�W�������̓���ɓ�_������B���݁A���̑��̌��m�@�̌��Ƃ��Č����Ǝ˂��Ă��̔����𑪒肷��PSL�i�����~�l�b�Z���X�j�@��ESR�i�d�q�X�s�����j�@�Ȃǂ̌������i�߂��Ă���BPSL�@��TL�@�ɔ�ׂĎ����ڑ���o����̂Ŋȕւō����x�ł��邪�A�Ǝˌ�Ɍ����Ǝ˂��ꂽ�O��������ƃV�O�i������������Ƃ�����_������B2008�N����2009�N�ɂ����ĊC�O�ł��łɍ̗p����Ă���ESR�@�̍������������̂��߂Ɍ��J�Ȃ̉Ȋw������ɂ�錤�����s���A�u�t�������o�[�̈�l�Ƃ��ĎQ�������B
�}�R�@ESR�@�̒����E�Z��
�䂪���ł͖@�߂ŐH�i�Ǝ˂͌����֎~�ƂȂ��Ă���̂ŁA���m�@�͂��̐H�i�ɑ��ďƎ˂��Ȃ��ꂽ���ǂ��������߂��i�ł���A�@���ᔽ���ǂ����̊m�F���Ƃ邱�ƂƂȂ�B���̂��ߌ��m�@�͌����ŋq�ϐ��̂��铧�����̍������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��BESR�@�͕��ː��Ǝ˂ɂ���Đ��������ŗL�Ŕ�r�I����ȃ��W�J���肷���@�ł���A�T���v���̑O�������ȒP�ʼn���ł�����\�ł���A���莞�Ԃ��Z���ԂƂ����������������ŁA�����̑������͊�������K�v�����邱�Ƃ�A�Ώە��ɂ���Ă͊��x���Ⴍ�Ȃ��_������B�C�O�ł�ESR�@�ɂ�����@�Ƃ��Ă͂P�D���ށA�Q�D�Z�����[�X�ށi���h���j�A�R�D���ށi�����ʎ��j��3��ނ�����BESR���u�̎�v�ȃ��[�J�[�͌���3�Ђ���A���̓��̈�͂��łɐH�i�Ǝˌ��m�p�Ƃ��Ĕ̔�����Ă���B���[�J�[���Ɏd�l���قȂ邱�Ƃ�A�T���v���̐���ɂ���đ��茋�ʂ��قȂ邨���ꂪ����̂ŁA����@�Ƃ��č̗p����ɂ́A���̊��݂���K�v������A�W�������Ƃ��Ďs�̂̃A���j���y���b�g���Ǝ˂������̂�p���邱�Ƃ����������B�u�t�͊C�O�ł̏Ǝ˗���Q�l�ɂ��č��h���A�s�X�^�`�I�̊k�A�C�`�S�̎�Ȃǂɂ��Ē��������B���݁AESR�@�ɂ���͏o���オ���Ă�����̂́A�ӔC�҂ł����������q���������̒S���҂��ւ�������Ƃ�A�܂��m���Ⴊ���Ȃ����ƂȂǂ̉ۑ肪����A����ɑ����̌����҂ɂ�钲�����K�v�ƍl���Ă�����悤�ł���B���s�̖@���̂��Ƃł́A���m�@�̏d�v�������܂邱�Ƃ��l�����A����ɍďƎ˂̉ۑ���܂߂āA��ʓI�Ȍ��m���s����悤�ɂ������ƍu������߂�����ꂽ�B
�@���x�⍑���̔F���̈Ⴂ�ɂ����̂ł��낤���A�C�O�ōL����e����Ă��邱�Ƃ��A���{�ł͊����Ƃ��ǂ��Ȃ��Ȃ�������Ȃ����Ⴊ�������A�H�i�Ǝ˂����̈��̂悤�ł���B
�i�哈�L�j