第42回放射線科学研究会聴講記
研究会は平成22年7月16日(金)13:30から17:30まで住友クラブ(大阪市西区江戸堀)で開催した。今回はエキゾチックビームシリーズ<8>として、長沼毅氏(広島大学生物圏科学研究科)、福西暢尚氏((独)理化学研究所仁科加速器センター)、土田秀次氏(京都大学大学院工学研究科)、堀岡一彦氏(東京工業大学大学院)の4名の方々であった。
1. 地球生命の起源はパンスペルミア(宇宙胚種)か?
広島大学生物圏科学研究科 准教授
長沼 毅
長沼講師の専門はastrobiology(宇宙生物学)とのことであるが、講演では深海から宇宙までの広範囲な領域に住む生物について大変興味深い講演をしていただいた。地球生命の起源は宇宙にあるのではないかというパンスペルミア(宇宙胚種)説は古来より多くの研究者によって提唱されてきた。キリスト教の勃興により全ての生き物は神が創ったとされ、宇宙胚種説は廃れたが、ダーウインの進化論以降、ケルビン卿、ヘルムホルツ、アレニウスなど著名な研究者もこの説を唱えている。しかしながら、宇宙から地球上への移動手段及び生命の起源について説得力のある説明がなされていないことから、この説は生命学者の支持を得ているとは言い難い。ただ、長沼講師によれば、地球内に生命誕生の起源を求める場合でも、まだ誰もが納得するような学説はないので、両者の間に決定的な差があるとは言えないそうである。
長沼講師は(独)海洋研究開発機構に所属していた当時、同機構所有の有人潜水調査船「しんかい」で深海の生物の調査を行っていた。深海の海底火山の噴出孔周辺にはチューブワームと呼ばれる独特の生物(動物)が生息している。チューブワームは外殻がキチン質で出来ている一個の直径が数センチ、長さが最大3メートル程度のまさに円筒形の動物であり、その体内に微生物が共生している。動物であるが、海底の岩盤に固着していて動くことはない。その地域は太陽光の届かない海底であり、地上の植物のような光合成によってエネルギーを得ることは出来ない。その代わり、チューブワームは海底火山から噴出する硫化水素やメタンなどを原料とする化学反応によってエネルギーを得ている。さらにチューブワームは動物ではあるが、移動は出来ないため、体内に共生する微生物が行う化学反応のエネルギーを取り込んで生活をしている。通常の動物は他者を食することによって、生命を維持するが、チューブワームは微生物から養分をもらうだけで他者を食することのない独立栄養の生命体である。海底火山から噴出する熱水中に微生物が存在している。
生物が生存出来る温度は120℃程度であることから、これら微生物が400℃もある熱水中に生息しているとは考えられず、おそらく熱水の噴出によって海水中に吹き上げられたものであろう。海底の水温は大体2〜3℃程度であることを考慮すると海底の地下にはこれら微生物が棲む適温帯が存在しているはずであり、この領域を地下生物圏と呼ぶ。講師らは地下生物圏の調査を原子力機構の瑞浪超深地層研究所(岐阜県)及び幌延深地層研究センター(北海道)の立坑に研究室を設置して行う計画を遂行中で、すでに500mは完成し、1000mまでの計画を進めているとのことである。
30年ほど前までは我々が知っている生物圏は陸上と海洋だけであった。そこで生息する植物の総重量は1兆トン、動物は100億トン、微生物3千億トンで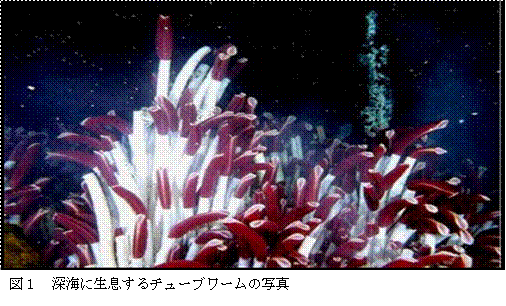 あるのに対して、地下生物圏での微生物の総量は控えめに見積もっても3から5兆トンもあり、他の生物圏の総量よりもはるかに大量である。このことは水と熱さえあれば、他の天体にも微生物が存在する可能性を示唆している。例えば木星の衛星には火山活動の痕跡を示すものがある。イオには火山活動が観察されているが、エウロパの表面は氷で覆われているもののその表面パターンは融解後に再凍結した可能性を示唆している。
あるのに対して、地下生物圏での微生物の総量は控えめに見積もっても3から5兆トンもあり、他の生物圏の総量よりもはるかに大量である。このことは水と熱さえあれば、他の天体にも微生物が存在する可能性を示唆している。例えば木星の衛星には火山活動の痕跡を示すものがある。イオには火山活動が観察されているが、エウロパの表面は氷で覆われているもののその表面パターンは融解後に再凍結した可能性を示唆している。
従ってエウロパには活火山があり、その熱によって融解した海が氷層の下部にあり、さらにその海底の地下には生物圏の存在する可能性がある。類似の構造は地球の南極にある。南極大陸の氷層の下には大小145もの湖が存在していることが知られており、その中の最大のボストーク湖に向けて穴を掘って生物の調査を行う計画が進行中である。長沼講師は今度の南極の夏にその湖の地下生物圏の調査を行うことになっているとのことである。さらに壮大な計画として、スペースシャトルで有人潜水調査船を木星の衛星まで運び、エウロパの海に潜ることも真面目に提案されている。
さて、地球外でそのような微生物の存在が確認されても、それがどのように地球まで到達したかという疑問が残る。講師の考えでは隕石が方舟になった可能性がある。宇宙の強い放射線に暴露された生物は生存が困難であるが、もしそれら生物が隕石中の表面から3m以上の内部に潜んでいれば十分に遮蔽される。又、地球の大気層との摩擦で表面が高温になったとしても隕石に関する調査結果ではその内部は生物が耐えられる程度の温度上昇しか起こらないことも実証されている。
講演の中ではご子息が描かれたチューブワームの絵を紹介したり、宇宙飛行士になり損なった写真を示したりなどエピソードを交えながら地球の内部から宇宙空間の広い領域における生物の存在の可能性について興味深く話され時間の経つのを忘れるほどであった。
2. 多段サイクロトロンシステムRBFの挑戦
(独)理化学研究所仁科加速器研究センター
加速器基盤研究部 福西 暢尚
福西講師からは理化学研究所で稼働中の大型実験施設RIビームファクトリで行われている研究について紹介をしていただいた。
20世紀は大型加速器の発展に伴って原子核に関する成果が理論的にも実験的にも飛躍的に得られた世紀であり、非常に多くのノーベル賞の対象となった研究がなされた。その結果、核物理学は十分に発展した分野であり、主要な知見はすでに得られており、今や大きな課題は残されていないのではないかと言われた時期もあった。しかしながら、1980年代になって、谷畑らが11Liを生成して、その原子核半径を測定したところ、安定なLiに比して、異常に大きい半径を有することが分った。元来、原子核の密度はその陽子数、中性子数に依存せずに一定であり、非圧縮性の液滴のように振舞うと考えられていたので、この発見は従来の考え方を大きく変えることとなった。11Liの場合には緩く束縛された2個の中性子が内側の中性子に比して5倍程度広がっていることが分り、同様の実験結果がその他の短寿命のRIにおいて次々と得られるに至り、新しい原子核ルネッサンスの幕開けになった。
短寿命RIの研究は宇宙での元素生成の機構を解明する上に重要である。現在の宇宙論では宇宙は140億年前のビッグバンから始まったとされている。ビッグバン直後の宇宙には水素、ヘリウムなどの軽い元素のみが存在した。その後、恒星内での核融合反応により、段階的に重い元素が生成されていったと考えられているが、この過程では鉄までの元素しか形成されない。それよりも重い元素は中性子を吸いながら核反応によってゆっくりと生成されていくが、この過程では鉛までしか作られない。地球にはウランのような極めて重い元素が存在することから、科学者は長い宇宙の歴史の中で、超新星爆発によって発生した大量の中性子による短時間の核反応によってそれらの重い元素が誕生したと考えている。これは短時間の反応であることからからrapidのrをとって r-processと呼ばれている。このような元素の生成過程を実証しようとするのもRIビームファクトリの一つの大きな目的である。
現在、報告されている元素は113種、自然界では270種の原子核が安定に存在することが知られているが、理論的に有限の寿命を有する原子核は8000程度あるとされている。
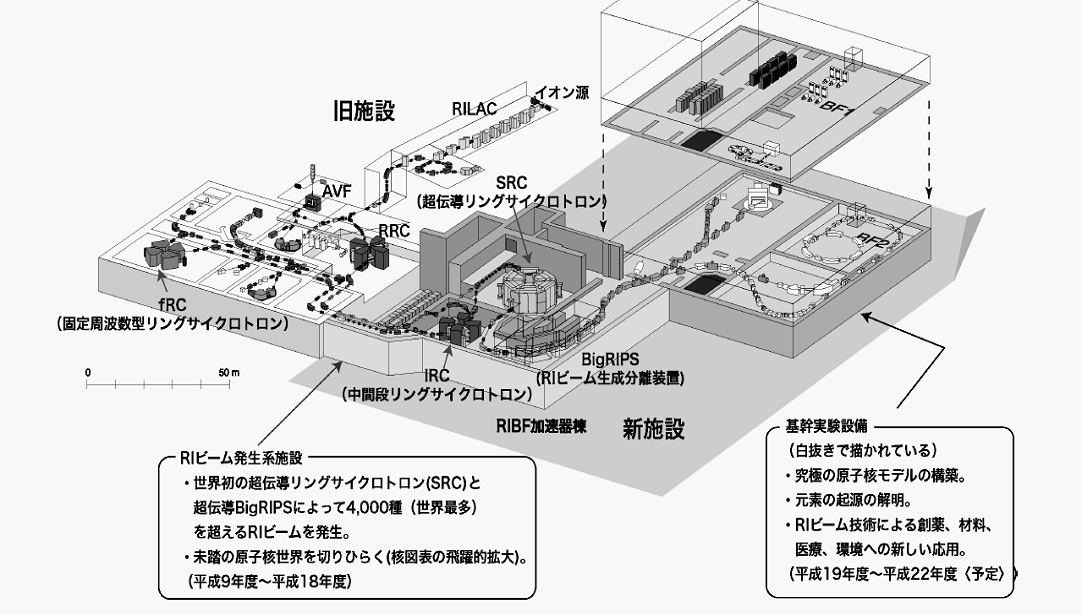
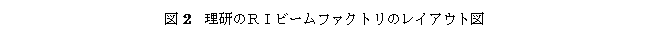
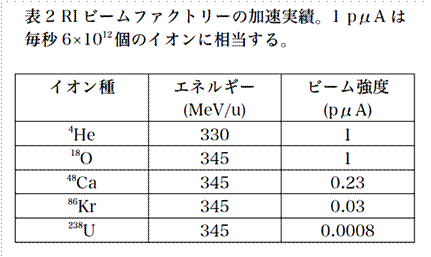
自然界に安定に存在しないRIは加速器を用いて生成することが出来るが、生成された原子核は化学的に分離した後、それから出る放射線の測定により同定するため、対象となる核種は数10分程度の比較的長い寿命のものに限られていた。1960年代にはISOL(Isotope Separation On Line)という手法により、数秒程度の寿命を持つRIまでに対象が広がったが、取扱えるRIに条件があり限界があった。さらなる加速器の性能向上により高エネルギー重イオンビームの利用が可能になると、それを標的原子核に衝突させて入射核破砕反応を起こさせることによって、関与する原子核の一部の陽子、中性子が剥ぎ取られて、確率は低いが、自然界には存在しないRIが生成される。このビームを分析器下流側の標的原子に衝突させてそのビームの性質を調査することが可能となった。この手法では効率的に短寿命RIビームを得るためには入射ビームの重イオンのエネルギーが大きくしかもその量も多いことが要求され、また安定な原子核から離れたRIの生成確率は離れるにつれて減少するため、RIビームファクトリの加速器システムはこれらの条件を満たすことが必要となる。
さらに軽い元素からウランに至る重い元素までをRIビームが得られる条件にまで加速することが要求される。これら種々の条件を検討した結果、図に示されるような複合加速器施設となるレイアウトとなった。その結果、この施設では(1)可変エネルギーモード、(2)固定エネルギーモード、(3)AVF入射モードの3種類の加速モードで研究を行うことが出来る。RIビームファクトリ計画は1997年にプロジェクトがスタートし、2006年12月に核子当たり345MeVのアルミニウムイオンの取り出しに初めて成功した。
当初はまだビーム強度が弱かったがその後の改良によって、現在では表に示したように軽い元素イオンでは設計性能通り、中程度のカルシウムでは目標値の1/4程度となったが、ウランではまだ千分の一程度である。ウランの強度が弱いのはまだ適当なイオン源を使用していないことと初段の加速器が古くビーム強度ロスが大きいためである。現状でも生成能力としては世界最強度であり、現在最終目標達成に向けた大幅な改良プログラムを進行中とのことであった。建設中の新型イオン源とウラン加速用の新入射器が間もなく稼動予定であり、数年以内には現在の50倍程度まで強度を上げられる予定である。
施設ではすでに様々な成果が得られており、ウランビーム実験ではPdに125Pdと126Pdの新しいRIが発見された。その後の実験では45種類の新しいRIが発見され、その結果は本年6月にプレスレポートされている。それ以外でも次々と新しい成果が得られており、世界をリードしているが、欧米においても同様の施設の建設フェーズに入っている。米国ではまだ予算がついていないが、EUではすでに予算がついて建設段階に入っており、国際競争が一層熾烈になることが予想される。現状のままでは新しい施設に立ち後れることは自明であるので、理研としても的確な施設のアップグレードを継続して行っていく予定である。
理研ではこの施設を用いて元素の起源の解明と原子核モデルの構築という基礎研究だけでなく、新規のRIビーム技術による創薬、材料、医療、環境への新しい応用を探索している。
多数の加速器を活用してシステム化出来る理研の技術力と資金力を再認識させられたというのが正直な印象である。(以上 大嶋記)
3. 陽電子による照射環境下に生ずる格子欠陥のその場観察
京都大学大学院工学研究科附属量子理工学
教育研究センター(兼 原子核工学専攻)
准教授 土田 秀次
土田講師は、原子分子・放射線物性研究の専門家であるが、最近、固体材料が放射線によってどのようなエキゾチックな変化を示すかといった立場からの研究にも力を入れている。その研究経歴から、いろんな実験手法を用いての「その場」測定は大変得意とするところであり、今回の発表も、まさにその得意技を活用した照射効果「その場」測定に関するものであった。
放射線が物質に照射されたときに物質に生ずる様々な変化(照射効果)の研究は古くからおこなわれていて、まずその歴史的背景の紹介があった。放射線照射により、電子状態や格子状態は高い励起状態になるが、その状態を照射環境下で観測することが、照射効果の理解においては不可欠である。そのような観点から、1970年代にイオン照射での照射効果を電子顕微鏡観察する手法が取り入れている。本講演では、照射によって生成される格子欠陥のうち、最も基本的な原子空孔を調べるのに適した陽電子消滅法を照射環境下の欠陥プローブに応用し、照射環境下での格子欠陥生成の初期過程を調べた実験結果が紹介された。当日、学生の参加者も多くいたため、まず、陽電子の基礎的な性質に関して説明があった。陽電子は電子の反粒子であり、互いに出会うと対消滅して高エネルギーの光(ガンマ線)を出す。この光は、陽電子の消滅相手の電子の運動量に関する情報をもっている。陽電子が原子空孔にとらえられた場合は、ガンマ線の運動量の広がりは狭くなるため、この広がりの指標であるSパラメータを測定すれば、照射中に物質に存在する原子空孔の情報が得られるということが丁寧に解説された。次に東海村の東大原子力施設で実施された実験についての説明があった。Na線源からでた陽電子のエネルギーを整え、イオン加速器と直結した照射チェンバー内に導き、イオン照射中のSパラメータを測定する。実験では、ターゲットにニッケル、イオンビームとして2.5MeVのカーボンイオンを用いた。実験結果の1部を図に示す。
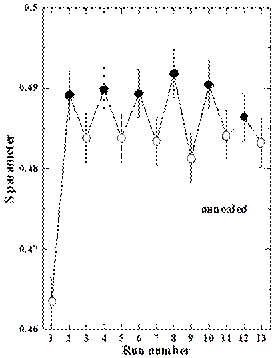
図3 熱処理したNi試料におけるSパラメータの経時変化
図は熱処理したニッケルターゲットで得られた結果である。黒丸がイオンビーム照射時のSパラメータ、白丸がイオンビームを止めた状態でのSパラメータである。イオンビームを照射開始するとSパラメータは一気に増加する。これは、イオン照射することにより、ニッケルターゲット中に多量の原子空孔が導入されたためである。ビームを止めると、Sパラメータは減少し、空孔数が減少したことがわかる。つまり、この実験結果は、まさに照射中にのみ存在する多量の原子空孔をとらえたものであり、照射後に照射効果を観察する通常の方法では見ることができなかったものである。照射を止めてもSパラメータは照射前の値にはもどらないが、これは、残留する空孔が物質内に蓄積していくためであろう。講演では熱処理したニッケルにおける結果と併せて、ナノ結晶材としてのニッケルをターゲットとして用いた結果についても示された。この場合は、イオン照射中と止めた後でのSパラメータの値にあまり変化はない。これは、ナノ結晶材では、結晶粒界の割合が多く、それが空孔の消滅を促進するため、照射中でも空孔濃度は大きくならないことを意味するものである。すなわち、ナノ結晶材料は、照射欠陥が蓄積されにくい、高い耐放射線特性を有した材料であることが示された。
以上の講演から、イオン照射時に同時に陽電子測定を行うことは、照射下における照射欠陥の挙動を観測するのに大変有効な手段であることが示された。今後は、本方法を用いた実験データの積み重ねにより、照射効果のさらなる定量的理解につながることが期待される。
4.実験室天体物理―高速重イオンによる高温高密度科学の展開―
東京工業大学・大学院総合理工学研究科
創造エネルギー専攻 堀岡一彦
堀岡講師は、最近、木星など巨大ガス惑星内部の高温高密度の物質(Warm Dense
Matter, WDM)の状態を再現するために、高速重イオン加速器による精度の高い1次元領域エネルギー付与を利用するというアイデアを提案されている。これは高エネルギー重イオン加速器の利用における新たな展開だと思われる。本放射線科学研究会、特にエキゾチックビームシリーズでの講演テーマとして最適であると考え、講演をお願いしたものである。
固体の密度でしかも数千度と言う高温にある物質(WDM)の状態は、巨大ガス惑星の中心部のコアで実現される状態であり、これを解明することは、太陽系の起源あるいは惑星形成理論の立場から大変重要なことである。しかしWDM状態は、従来のプラズマ物理学ではカバーできない領域であり、また、相変化や解離・電離などの複雑な現象を伴うことや、輸送方程式の定式化が難しいため、実験的にも理論的にもまだ十分解明されていない。木星のコアの評価のカギを握るのが水素の状態方程式である。特に水素分子から金属水素に遷移する領域が良く分かっていない。
そこで、この高圧状態を再現するために高強度レーザーを用いた衝撃圧縮実験が行われている。しかし、レーザー加熱は、物質への吸収過程が複雑で不確定であり、また衝撃圧縮は散逸が大きく温度が上がりやすいといった問題点がある。一方、GeV領域のエネルギーをもつ重イオンで固体水素標的を照射し、高密度・高温水素状態を生成するという方法が考えられる。しかし、重イオンビームで水素原子を単に6000Kまで加熱するだけでは200GPaの圧力を達成できない。そこで、あらかじめ水素標的を圧縮しておいてからイオンビームで加熱するという方法をとる。ここでは、金属ライナー内に閉じ込めた固体水素をパルス大電流により予備圧縮し、さらにイオンビームで追加熱する方法を提案する(図4参照)。
さて、状態方程式を決めるには、3つの状態量を測定する必要がある。まず、重イオンビームで投入された内部エネルギーは十分な精度で求めることができる。密度は、標的径の挙動を時分割測定することで求まる。あとは温度か圧力を測定すれば良い。これを直接測定することは難しいが、逆解析的に圧力を求めたりイオンのエネルギー損失量からの温度の推定も検討している。
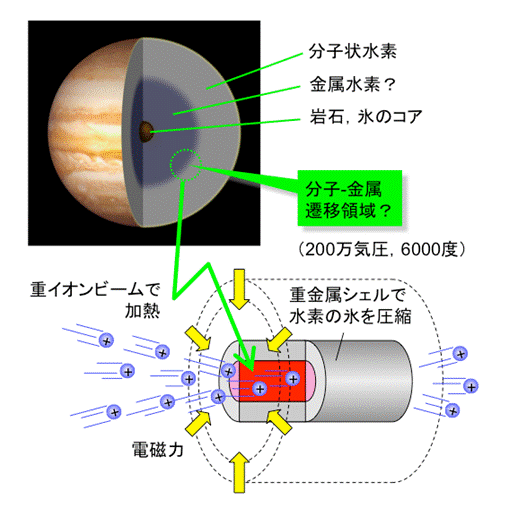
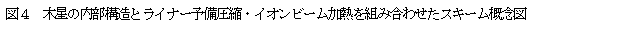
次に、具体的なイオン種とエネルギー値を用いて検討する。例えば核子あたり100MeVの金イオンビームを0.2mmの径に絞り、固体密度の10分の1の密度をもつ標的を照射することで、エネルギー換算で0.6eV程度の温度にまで加熱でき、状態方程式の不定性が大きいWDM領域に到達することが可能であることがわかった。以上のことから、GeV領域の重イオンは固体内で飛程が大きく、物質の大体積、均一加熱に適していることがわかる。また、物質へのエネルギー付与密度を正確に予測できるのも利点の1つである。このように、予備圧縮した水素標的をGeV重イオンビームによって照射することにより、木星など巨大ガス惑星内部の高密度水素の状態方程式を高精度で計測し、惑星の形成過程の解明に大きな手がかりをもたらす可能性が大きい。
以上が講演の概要であるが、重イオンビーム照射によって固体材料中に高密度態、熱的非平衡状態を作り出し、今までにはなかった新しい物質を作ったり、新たな機能を付加させたりすることを夢見ている筆者にとって、堀岡講師の研究は、固体内高密度励起と緩和過程といった新しい物理を開拓できる可能性を、全く異なった研究領域から示していただいているものだと、講演を通じて確信した。これからも同じ高速重イオンビームユーザーの仲間として議論を交わしていきたいと思っている。(以上 岩瀬記)