��S�O����ː��Ȋw������u�L
������͕���21�N10��16���i���j13:30����17:30�܂ŏZ�F�N���u�i���s����]�˖x�j�ŊJ�Â����B����̍u�t�͉͐����j���i�i�Ɓj���{���q�͌����J���@�j�A�ΐX�L���i�i�Ɓj���{���q�͌����J���@�\�j�A���Έ�掁�i(���j���{����w)�A���{�^�玁�i�|�j�[�H��(��)�j�̂S���̕��X�ł������B
(��)���{���q�͌����J���@�\��[��b�����@�Z���^�[�E�z�d�q�r�[�����������O���[�v
�@�O���[�v���[�_�[�i�����劲�j�@�͐��@���j
�d�q�̔������ł���z�d�q�͎��R�E�ɂ͈���ɑ��݂��Ă��Ȃ����ARI���邢�͉�����𗘗p���ē��邱�Ƃ��o����B�z�d�q�͎��R�E�ɑ�ʂɑ��݂���d�q�ƑΏ��ł��āA���̍ۗ��҂̏�ԂɑΉ��������Ń�������o����B���̃���������ƕ������̗l�X�Ȓm���������邱�Ƃ���A���R�Ȋw�̑��l�ȕ���ŗ��p����Ă����B�͐��u�t�͗z�d�q�̊�{�I��������ŋ߂̐�[�ޗ��ւ̉��p�܂ŗz�d�q�Ɋւ�鑽�ʂ���߯����Z���Ԃɗv�̂悭�Љ���B
�@�u���ł͂܂��z�d�q�]���@�̌����A�������@�Ɨ��_�v�Z�ɂ��ĊT��������A�ߔN���q�͌����J���@�\�₻�̑��̎{�݂Ő��͓I�ɍs���Ă���z�d�q�r�[���̊J���ɂ��ďڂ������������B�]���͗z�d�q���Ƃ��Ă�Na, Ge, Cu�ȂǗz�d�q�G�~�b�^�[�ł���RI�𗘗p���Ă��邪�A�ޗ���������ł͔�������G�l���M�[�̊ϓ_����i�g���E��22���ł��悭�g�p����Ă����B�ߔN��RI��������̗z�d�q����U�����ނ�ʂ�����A�ēx��������V�X�e�����g�����ƒP�F���o����G�l���M�[�σr�[�������p�����悤�ɂȂ�A�܂��r�[�����i�邱�Ƃ��\�Ȃ��Ƃ���A������p�����z�d�q�������A�S���ˉ�ܖ@�Ȃǂ̐V�K�̎�@�ɂ����ɕ\�ʏ�Ԃ̉�͂Ȃǂ̋Z�p���i�W���Ă����B�����̋Z�@�͓��ɕ\�ʏ�Ԃ┖���̕]���ɂ�����Ă��邱�Ƃ����F�ł���B�\�͗z�d�q�r�[���𗘗p�����]���Z�p���܂Ƃ߂����̂ł���A���l�ȕ]���Z�p�Ƃ��ĉ��p�\�ł��邱�Ƃ�����B
�z�d�q�𗘗p����]���Z�p�̎���Ƃ��āA�u�t��1.�R���d�r�d�������A2.���f�z�������A3.�����̃h�[�s���O�A4.�X�e�����X���͕��H����A5.�i�q���ו������Ƃ肠���Đ��������B
�R���d�r�̐S�����Ƃ�������d���������ɂ����Ă̓v���g���̃z�b�s���O�`���ɂ�锭�d�\�͂Ɠd�ɂȂǂ���̃K�X���[�N�ɔ����R�����X�Ɋւ���m���邱�Ƃ��d�v�ł���B���ݑ�\�I�d�������Ƃ���Nafion�ƌĂ�鍂���q�������p����Ă��邪�A���̖��͎卽�̃|���e�g���t���I���G�`�����iPTFE)�ɑ����Ƃ��ăX���z���_������\���ŁA�������w�I���萫�ƓK�x�ȃv���g���`������L���邪�A�����R�X�g�������Ƃ����Z��������B���ƂȂ�ˋ�PTFE���͔��\�����Ɍ������̗̈悪���U���đ��݂��Ă���A�O���t�g�����ɂ�茋�����̈�ɃX���z������C�I��������Ƃ��Ă������̂�d�������Ƃ��Ă���B���̖��ɂ��ėz�d�q���Ŏ���������s�����Ƃ���A���d�����̓K�X���[�N�̌����ƂȂ�����R�̐ς̍��قɊW���邱�Ƃ��������B���f�z�������͐��f�����Ԃ̊J���Ɍ������Ȃ��ޗ��Ƃ��Ē��ڂ���Ă��邪�A�J���ۑ�Ƃ��Ă͒����e�ʁA�ϋv���A�������x�A���o���x�̐���Ȃǂ��������Ă���B���ڂ���Ă���TiCr�n�����̗z�d�q���Ŏ�������̌��ʂł͍ޗ��̐��f�z���\�͂̒ቺ�ɔ����ėz�d�q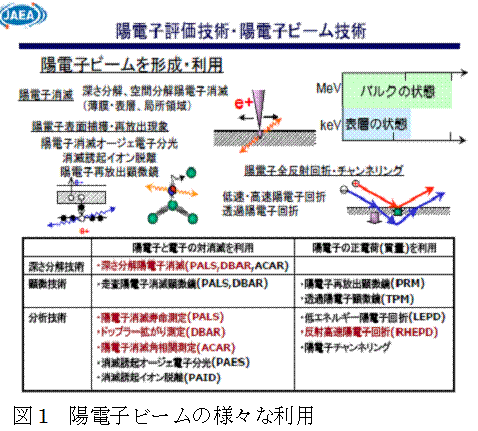 �����̐L�����ώ@����A�܂��w����܃s�[�N�̔��l���̑���������ꂽ�B�����œ���ꂽ�z�d�q�����l�͍ޗ��̌��q��E��{�C�h�̐����ł͐����o���Ȃ����Ƃ��猟���̌��ʁA���f�����̐����ɂ��̐ϖc�����ɘa���邽�߂ɓ]�ʂ���������A���f���������艻���ċz���ʂ�����Ă��邱�Ƃ������Ă����B���������ē]�ʖ��x�̐��䂪�傫�ȃt�@�N�^�[�ł��邱�Ƃ����������B
�����̐L�����ώ@����A�܂��w����܃s�[�N�̔��l���̑���������ꂽ�B�����œ���ꂽ�z�d�q�����l�͍ޗ��̌��q��E��{�C�h�̐����ł͐����o���Ȃ����Ƃ��猟���̌��ʁA���f�����̐����ɂ��̐ϖc�����ɘa���邽�߂ɓ]�ʂ���������A���f���������艻���ċz���ʂ�����Ă��邱�Ƃ������Ă����B���������ē]�ʖ��x�̐��䂪�傫�ȃt�@�N�^�[�ł��邱�Ƃ����������B
�����d�ɖ��̓^�b�`�p�l���ȂǕ\������ōL�����p����Ă���ޗ��ł���B���̈��ZnO�ł���AAl���h�[�v�����ޗ��ɂ��Ē��������BAl���C�I���������邱�Ƃɂ��ZnO�̔����������邪�A���̌��600���ē݂ł̓}�C�N���{�C�h���������Ă���A900���ē݂ł̓{�C�h���ׂ̉������i�������サ�����Ƃ��A�z�d�q��������Ŗ��炩�ƂȂ����BSiC�͍����p�̔����̍ޗ��Ƃ��Ċ��҂���Ă���B�ǎ��̍ޗ��̈琬�ƂƂ��ɁASiC-MOSFET�̎��p���ɂ͊E�ʏ��ʂ̒ጸ���K�v�ł���B���̂��߂ɂ͎_�f�Ǘ��d�q����E�^���ׂ̒ጸ���L���ł��邱�Ƃ��������B�z�d�q�r�[���𗘗p���鑕�u�Ƃ��ėz�d�q���������J�������B�����p���ăX�e�����X�|�̉��͕��H����̃N���b�N��[����2.7�����~1.9�����̗̈�ɂ���0.1�����X�e�b�v�Ńr�[���������s���A�T����[���ɂ͒P���E���`������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�܂��A�����ł̌��q��E�̐U�镑�������炩�ɂȂ��Ă��Ȃ�Si�ɂ��ėZ�_�܂ł̑�����s�����Ƃ���Z�_�����ł�S�p�����[�^���}���ɑ�������X�����ώ@���ꂽ�B�z�d�q�r�[���̉��p�Ƃ���10�`100keV�̑S���˗z�d�q��ܑ��̎B�e�ɐ��������B���̎�@�͕\�ʑ��w�̏����邱�Ƃ������ł���B
�ߔN��PET�f�f�ŗz�d�q�̖��O���@��͑������A���炭��b�Ȋw�̕���ɂƂǂ܂��Ă����z�d�q���p���Y�ƕ���ł��L���g����悤�ɂȂ��Ă������Ƃ��ĔF�����邱�Ƃ��o�����B
�Q�D�l�`�����Z�p�Z���^�[�̌���Ƃ��ꂩ���i����y�[�W )
���{���q�͌����J���@�\�l�`�����Z�p�Z���^�[�E���S�Ǘ���
�������劲�@�ΐX�@�L
1955�N11���ɉ��R���ƒ��挧�̌����ɂ���l�`���ŃE�����z����������A���̗��N�ɂ͌��q�R�����Ђ��ݗ�����A1957�N8���Ɍ��q�R�����Аl�`���o�������J�݂��ꂽ�B���̌�A���͘F�E�j�R���J�����ƒc�A�j�R���T�C�N���J���@�\�ȂǑg�D�̉��ς͂��������A40�N�ȏ�ɂ킽���ăE�����T�z�A�̍z�A���B�A�]���A�Z�k�Z�p�Ƃ����j�R���T�C�N���̃t�����g�G���h�Z�p�J�������{���Ă����B�����̐��ʂ͖��Ԃւ̋Z�p�ړ]���i�߂��A���݂ł͂��̎g�����قډʂ����Ƃ���A�֘A�{�݂̔p�~�[�u����эz�R�Ց[�u�����{����Ƌ��ɁA����j�R���T�C�N���m���ɕs���Ȋj�R���{�݂̔p�~�[�u�Z�p�J���̂��߂̃t�����g�����i�[�̖�ڂ�S���Ă���B�ΐX�u�t�͐l�`�����ʂ����Ă��������̐��ʂƌ���A����ɍ���̓W�]�ɂ��ĊȌ��ɍu�����s�����B
 �Z���^�[���s���Ă����Z�p�J�����ʂɂ��Ă͂܂������E�����̐���𖾂炩�ɂ���Ƌ��Ɏ��ӂɂ����閄���ʂ̊m�F���s�������Ƃ���������B�����ŎY�o����z����́u�l�`�v�iNingyoite�j�i�g��:CaU(PO�S)�Q�1-2H�QO�j���V�z���Ƃ��Ĕ������ꂽ�B���̒n��̎�v�z���͐l�`�Ȃ�тɗӊD�E�������iautunite�j�ł���A�����̍z�̍̍z�ɌW�鎎���E���B�@�̊m���A�z�Ώ��������A�����y�ъ����E�������B�Ɋւ���Z�p�J�����s�����B�l�`�����ӂ̖����ʂ͂��悻2470�g���ƌ��ς����A���{�ɂ͂��̑����������Z�n���4600�g�����܂�������đS���ł͂��悻U�RO�W���Z��7700�g���̖����ʂ�����B�������Ȃ���O���Y�ɔ�ׂăE�����i�ʂ��Ⴂ���߁A1970�N��㔼����͒T�z�����̒��S�͊C�O�Ɉڂ��Ă��܂����B
�Z���^�[���s���Ă����Z�p�J�����ʂɂ��Ă͂܂������E�����̐���𖾂炩�ɂ���Ƌ��Ɏ��ӂɂ����閄���ʂ̊m�F���s�������Ƃ���������B�����ŎY�o����z����́u�l�`�v�iNingyoite�j�i�g��:CaU(PO�S)�Q�1-2H�QO�j���V�z���Ƃ��Ĕ������ꂽ�B���̒n��̎�v�z���͐l�`�Ȃ�тɗӊD�E�������iautunite�j�ł���A�����̍z�̍̍z�ɌW�鎎���E���B�@�̊m���A�z�Ώ��������A�����y�ъ����E�������B�Ɋւ���Z�p�J�����s�����B�l�`�����ӂ̖����ʂ͂��悻2470�g���ƌ��ς����A���{�ɂ͂��̑����������Z�n���4600�g�����܂�������đS���ł͂��悻U�RO�W���Z��7700�g���̖����ʂ�����B�������Ȃ���O���Y�ɔ�ׂăE�����i�ʂ��Ⴂ���߁A1970�N��㔼����͒T�z�����̒��S�͊C�O�Ɉڂ��Ă��܂����B
�l�`���̎{�݂ł�1956�N����܂������Z�p�J���Ɏn�܂�A�����Đ��B�E�]���A�Z�k�Z�p�J���Ɛi�݁A���݂͊��ۑS�Z�p�J�����s���Ă���B�N�����猩���1956�N�T�z�E�̍z����X�^�[�g���A1964�N����V�R�E�������B�E�]���A1979�N9���ɂ̓E�����Z�k�p�C���b�g�v�����g�iOP-1A�j�̉ғ��A1982�N�ɉ���E�����]�����p�������A1988�N�̓E�����Z�k���^�v�����g���X�^�[�g�����B�]����2009�N�͉䂪���ŏ��߂ăE�����Z�k���n�܂��Ă���30�N�ڂ̋L�O���ׂ��N�ƂȂ��Ă���B�܂��A1979�N�ɂ͉䂪���͍��ۊj�R���T�C�N���]��(INFCE)�ɂ����ăE�����Z�k�Z�p�ۗL���Ƃ��Ă̍��ۓI�n�ʂ��m�������B���̂��Ƃ͋ߔN�̖k���N��C�����ɑ��鍑�ۏ���ӂ݂�ƁA�s�퍑�̉䂪�����F�m���ꂽ���Ƃ͉���I�ł������Ƃ�����B���̌㉓�S�����@�Z�k�v�����g�̐M�����A�o�ϐ��Ɋւ���f�[�^�ƃv�����g�̐v�A���݂Ɋ֘A����m�E�n�E�ƃv�����g�̉^�]�Ɋւ��Z�p�̒~�ς��s���A���^�v�����g�iDOP-2�j�̌��݂ւƐi�B���^�v�����g�ł�1988�N�����13�N�Ԃɂ킽��قڃ[���g���u���̉^�]���s���A���S�����@�̎����̏ᗦ���N0.7���Ƃ����ڕW�l���B���ł����B���̊Ԃɐ��������Z�k�E�����ʂ͖�353���ŁA����53���͉���E������Z�k�������̂ł������B���̌�̕����ޗ�����]���Ɏg�p�������u�̎��p�K�̓J�X�P�[�h�����ł́A����Ɍ�����1.5�{�܂ŏグ�邱�Ƃɂ����������B�����̋Z�p�͓��{���R�i���j�֖��Ԉړ]���ꂽ�B���S�����Z�p�͍��ۓI�ɍō��@���ɑ�����Z�p�ł���A�u���Ŏ����ꂽ�ʐ^����͑S�̑�������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���A�M�҂��ȑO�ɘZ�������Ŏ{�݂����w�����ۂɂ����d�ɃK���X�Ŏd��ꂽ���w�ʘH����ꕔ�������邾���ł������B
���S�����ɂ����Ă͊Ǘ����ɂ�������ː��Ǘ��A�{�݂�����o�����r�C�E�r���Ǘ��A���Ӓn����O�̊Ď����s���Ă����B���ʂ̓t�b�f�̑���Z�p�A�v���g�j�E���̊Ď��Z�p�A�E�����z�R�Ղ̃��h���Ɋւ��錤���ł���B�v���g�j�E���Ɋւ��Ă͐l�X�̊S��S�z������A���Ӓn��̃v���g�j�E���̕��z���������A�قƂ�ǂ��t�H�[���A�E�g�ɂ����̂ł��邱�Ƃ��������B���h���̕��͍͂��x�̋Z�p��v���邪�A�V��������@��̊J�������������{�������ʁA���ӊ��ւ̉e���͋ɂ߂ď��������Ƃ����炩�ƂȂ�A���̋Z�p�𗘗p���č����̃��h������ɌW��W�����Ɋ�^�����B
2001�N�܂łɏ����ɖڕW���B�����ꂽ���Ƃɔ����A�{�݂̔p�~�[�u�y�єp���������̋Z�p�J�������݂̎�v�ȋƖ��ƂȂ��Ă���B��̓I�ɂ͇@�ؗ��E���������E����Z�p�J���A�A���S�����@�����Z�p�J���A�B�t�b�����n�������̗��p�Z�p�J���A�C��̃G���W�j�A�����O�̊m���A�D�z�R�Ց[�u�ł���B���łɏq�ׂ��悤�ɇA�̏ꍇ�͋@�����ێ��̊ϓ_���d�v�ł���B�����ɉ����Ēn��Ƃ̋�����ڎw�������ƂƂ��āA��������i���F���쒬�j�ɂ�����E�����K���X���Ɖ��ւ̋��͂��s���A���ݓ��n�Ő�������Ă���E�����K���X���i�͌��q�F���K���@�̑ΏۊO�ƂȂ�A���p�i�Ƃ��Ĉ�ʂɔ̔�����Ă���B���̑����R��w�Ƃ̋��������Ƃ��ă��h������̓K���ǂ̌��Ƃ��̋@�\�𖾁A���h���̑̓����Ԃ̌����Ȃǂ��s���Ă���B2008�N�x�ɂ́u�O�����h�����ʌ����{�݁v���J������A��K�͂ȃ��h���z���������J�n����A���v�I�ɂ��m�����̍����������ʂ���������̂Ƃ��Ċ��҂���Ă���Ƃ̂��Ƃł������B
�u���͌��ݓ����Ə����̔����J�n���������K�̏Љ�Œ��߂�����ꂽ�B���̃����K�͍z�R�̎c�y����Đ����ꂽ���̂��ꖇ90�~�Ŕ̔����ł���Ƃ̂��Ƃł���B���ݕ��ȏȂ̓�����̉Ԓd�ɂ����łɎg�p����Ă���A�����̂�����͂��Г����ɂ��₢���킹�������������B
�R�D����ʕ��ː��ɂ��K�������̋@�\�ɂ����i����y�[�W
)
���{����w�Y�w���A�g�@�\��[�Ȋw�C�m�x�[�V�����Z���^�[
���ː������Ȋw�������@�����@���@���
�@����ʂ̕��ː�����̐l�̂ɑ���e���ɂ��ẮA�l�X�ȕ��Ȃ���Ă���B��ʐl�ւ̕��ː�����h��̊ϓ_����́A���炩�ɉe���̌�������ʈ悩�����ʈ�ɑ��Ē����������̗p����Ă��邪�A���Ƃ̊Ԃł͑����̈٘_����o����Ă���B
�@���u�t�͂܂��\��̕��ː��K�������Ƃ͂����Ȃ錻�ۂł��邩���T��������A�זE���x�����猩���ꍇ�̕��ː��K�������A����Ɍ̃��x�����猩�����ː��K�������ɂ��ďq�ׁA�����ĕ��ː��K�������ɂ����鍜�����זE�̖�����������A�Ō�ɍ���̉ۑ�ƃq�g�ւ̉��p�Œ��߂��������B
�@1982�N��Russel��͗Y�}�E�X�̐��B�זE�ɕ��ː��Ǝ˂��s���A���̈��`�q��������̓ˑR�ψٕp�x�ׂ�ƁA�������ː��ʂł��������ː���Z���ԂɏƎ˂����ꍇ�Ǝア���ː����ԏƎ˂����ꍇ���r�������ʁA�ア���ː��Ǝ˂ł͂��̓ˑR�ψٕp�x���͂邩�Ɍ������邱�Ƃ�����B����ȑO�ɂ������̏Ǝ˂̏ꍇ��ቷ���炳�ꂽ��ł̓}�E�X��b�g�̎��������т邱�Ƃ�����Ă����B���ː���Q�h��̗��ꂩ��͌��ݒ����������̗p����Ă��邪�A����ʈ�ł͂ނ��됶���������h������Ƃ����u���ː��z���~�V�X�v�̍l�����x�����錤�����ʂ���������Ă���B�זE���x���ł͑咰�ۂł͎��O�̏Ǝ˂ɉ�����SOS�����n�����݂��A�����ł͗\�߃g���`�E���������{�����ꍇ�ɂ͐��F�ُ̈�̌y�����������邱�Ƃ����ꂽ�B�����̌��ʂ��܂Ƃ߂��
1�j�זE���x���ł͊m���ɓK�������͑��݂���B2�j�����̎h���͕��ː��łȂ��Ă��U���ł���B3�j�זE�����Ɉˑ��I�ɋN����B4�j�V�K�̃^���p�N���������K�v�ł���B5�jp38MAPK�APARP�A�����p53��`�q���K�v�ł���B6�jp53��`�q�̊������͓��ɏd�v�ł���
�Ȃǂ���������B
���Ɍ̃��x������݂��ꍇ�ɂ́A�����{����w��[�Ȋw�������̕��V�ɂ�邢����u���V���ʁv���m���Ă��邪�A���̌�̌������ʂł͌̃��x���ƍזE���x���̕��ː��K�������͈قȂ��Ă��邱�Ƃ�������Ă���B���Ȃ킿�זE���x���̓K�������̎������Ԃ́A�Ǝ˂̐����Ԍォ��A1���ԁA�������������Ԃł���̂ɑ��āA�}�E�X�̂ł́A�Ǝː��ʂɂ���ĈقȂ邪�A0.3�`0.5Gy�ł͏Ǝ˂�9���ォ��17����܂ł�9���ԁA0.05�`0.1Gy�ł�2�����ォ��2��������܂ł̔����Ԏ��������B�Ǝ˕��ʂ̓��ِ�������Ȃǂ̓��������o���ꂽ�B
��������ː��K�������ɂ����鍜�����זE�̖����ɂ��Ă����ׂ��Ă���B�Ǝ˂ɔ����}�E�X���B���̕ω��������B���̌��ʁA���O�Ǝ˂����}�E�X�ł͑����@�\�̉̎w�W�ƂȂ�������R���j�[�̉�����ꂽ�B���̗��R�Ƃ��Ắ@1.�������זE�̑��B�\�͂����A�ďƎˌ�ɐ����c�������זE�̉����i����Ă���\���A�Q�D�������זE�̕��ː���R����U�����A�ďƎˌ�A���זE�����������c���Ă���\���A�R�D��L�̗�����U�����Ă���\�������邪�A������p53��`�q�ɂ�鐧����Ă���\�����������ꂽ�B
�@����Ȃ�����̌��ʂł͑������זE�̕��ː���R����U�����A�ďƎˌ�A���זE�����������c���Ă���\���������ꂽ�B�������Ȃ���A0.5Gy�̎��O�Ǝˌ��8�������14�����7Gy�Ǝ˂̌��ʁA������B���R���j�[�̌`���̏㏸�͌���ꂽ���̂́A14����̂��̂ɂ̂ݍ������}���̌��ʂ����������B�܂��������ꂽ�}�E�X�̔]�ɂ͔]�ɂ�����o���}�����ώ@���ꂽ�B�����I�Ɍ����̌��ʁA�K�������ɂ�p53��`�q����т��̉�����`�q�̉������d�v�ł��邱�Ƃ����������B
����͍������זE���B�@�\�̈�[�͖��炩�ɂ��ꂽ���A�Ȃ����������}������邩���܂����炩�łȂ��A�}�E�X�K�������̃��J�j�Y���̂���Ȃ�𖾁A���݁A�K�������U���ɗp���Ă���0.5Gy�͒���ʂƂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����w�E������A�ʂ����Ă��Ⴂ���ʗ��œK�������͋N����̂��Ƃ����ۑ肪�c����Ă���B����Ȃ�傫�ȉۑ�͂���܂ł̌��ʂ͂͂����ăq�g�ɂ����Ă͂܂�̂��A���Ȃ킿�q�g�ɓK�����������邩�Ƃ������Ƃ��c����Ă���B
���R���v�g���U���@�ɂ���j���@�i����y�[�W
)
�|�j�[�H��(��)�c�Ɩ{�����{�����@�@���{�@�^��
�@���g�̕�����Ȃ��p�b�P�[�W�̒��������@�Ƃ��āA�w�����ߖ@�͓���݂̂��錟���@�ł���B���̕��@�͕����̂w���̋z���̍��قɂ��z���R���g���X�g�𗘗p���Ă���̂ŁA�z���̑傫�������Ȃǂ����m����ɂ͗D��Ă��邪�A�y���f�ō\������Ă��镨���̌��m�ɂ͌����Ă��Ȃ�
�v���X�`�b�N���e�▃��̌��o�@�̈�Ƃ��āA�|�j�[�H�Ƃł̓R���v�g���U���𗘗p�����V������j���@���J�����āA���ۓI�ɑ傫�Ȑ��ʂ������Ă���B�R���v�g���U���@�ł͂w����Ώە��ɏƎ˂��Č���U�����Ă���w�����x���X�L�������đΏە��̎U���R���g���X�g����@�ł���B���̎�@�ɂ��A���ߋz���@�ł͂قƂ�ǃR���g���X�g�̂��Ȃ��y���f����\������Ă�������Ȃǂ̕����ɑ��Ă����͂Ƃ͖��炩�ɔ��ʂ����R���g���X�g����B
���ߎ��ƌ���U�����̈Ⴂ�́A�ʏ퓧�߂���w�����摜������̂ł͂Ȃ��A�R���v�g���U������X�����摜�����邱�Ƃɂ���B�R���v�g���U���w���͎�ɔ� �����̐����ł���L�@�����Ƒ��ݍ�p�ɂ���đ����������邱�Ƃɂ���ĉ摜�ɔ�����������ĕ\�������̂������ł���B
�����̐����ł���L�@�����Ƒ��ݍ�p�ɂ���đ����������邱�Ƃɂ���ĉ摜�ɔ�����������ĕ\�������̂������ł���B
�}4�͓��ߖ@�ƌ���U���@�ɂ���āA����̑Ώە����B�e�����ۂ̔�r�ŁA����U���@�ł͌y���f�ō\������镨�̂��ǂ�����B�]���Č���U�����w���Ɠ��ߎ��w���𑊕�I�ɗ��p���邱�Ƃɂ��A�����E�������^�i���̌����\�͂��啝�ɍ����Ȃ�A�傫�Ȑ��ʂ���������悤�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł���B�Ƃ��ɎԂ̃o���p�[�ɑ�ʂɔ铽����Ė��A����悤�Ƃ�������̓E�����ȂǑ����̎ʐ^����g���āA�f���炵�����ʂ̏�����Љ�Ă����������B�@�@�@�i�哈�L�j�@