第36回放射線科学研究会聴講記
表記研究会はエキゾチックビームシリーズの第6回として平成20年7月18日(金)13:30から17:30まで住友クラブ(大阪市西区)で開催した。今回の講師は西畑保雄氏((独)日本原子力研究開発機構)、神原正氏((独)理化学研究所)、森田健治氏(名城大学)、庭瀬敬右氏(兵庫教育大学)の4名の方々であった。
1.インテリジェント触媒の放射光による自己再生機構の解明(会員ページ )
(独)日本原子力研究開発機構・量子ビーム応用研究部門・放射光科学研究ユニット
X線量子ダイナミックス研究グループ
グループリーダー 西畑 保雄
自動車用排ガスの浄化用としてPd,Pt,Rhなどの触媒用貴金属の需要は大きい。自動車用排ガス触媒は1970年代に実用化されて以来、今日まで30年間にわたって改良が加えられてきた。従来の触媒はアルミナなどのセラミックス表面に貴金属をナノメートルサイズで分散されたものが使用されてきたが、高温の排ガスに曝されている間に粒成長をおこして、全表面積が減少して性能劣化を生じていた。従来は自動車の法定使用期間内における排ガス濃度の基準をクリアするように、この劣化を補償する手段として、予め初期に余分の貴金属を投入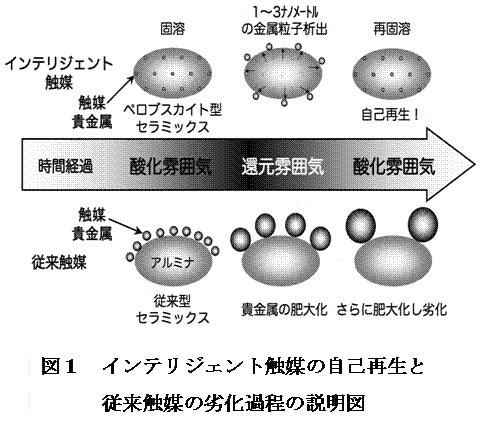 する手法がとられてきた。
する手法がとられてきた。
西畑講師らは排ガス中の酸素濃度の揺らぎを触媒材料そのものが察知し、自らの構造を変化させて、その時の環境に最適な機能を発揮する材料として、貴金属複合ペロブスカイト型酸化物を開発した。この開発の結果、Pd, Pt, Rhの使用量は従来型触媒に比べて、それぞれ9割、7割、5割もの削減が可能になったとのことである。この酸化物の代表的な組成はLaFe0.57Co0.38Pd0.05O3,
LaFe0.95Pd0.05O3, CaTi0.95Pt0.05O3,
CaTi0.95Rh0.05O3等であり、一般的なセラミックス製法では合成出来ず、アルコキシド法という方法で初めて合成することが出来た。合成した粉末を乾燥・焼成して作成した酸化物の酸化・還元雰囲気中での貴金属原子の振舞いを放射光の様々な手法を用いて調べた。粉末X線回折パターンでは酸化・還元雰囲気変動を通じてペロブスカイト構造は安定であった。ただ、還元処理試料では格子定数が伸び、Laの酸化物、水酸化物の反射が現れたので、構造の一部が壊れたと考えられるが、再酸化処理試料の回折パターンは復元しおり、平均構造の変化は可逆的であると結論される。
Pdはペロブスカイト型構造には固溶させにくいと考えられていたので、確認するためにX線異常散乱によって、Pdの固溶状態を調べた。この結果、Pdは酸素八面体の中心となるBサイトを占めており、金属や酸化物としてペロブスカイト酸化物に付着しているのではないことが明かとなった。PtやRhについても同様の結論が得られた。さらにLaFe0.95Pd0.05O3粉末を大気中酸化→還元(水素10%)→大気中再酸化をそれぞれ800℃、1時間の熱処理を施し、PdとFeのBサイト元素の吸収端でXAFS(X線吸収スペクトル)の測定を行った。この測定ではX線吸収原子の電子状態、周囲の局所構造がわかる。この測定の結果、酸化処理によってPdは高原子価状態に移っていることが分かり、バンド理論計算の結果では、このBサイトのPdは+3価という異常原子価を持ち、還元処理ではPdは金属状態をとっていた。還元処理の状態ではPd粒子及びPd+Fe粒子が混在していると解釈出来た。更に次の再酸化処理によってPdの原子価は元に戻った。一方のFeの原子価については+3のままで変化が認められなかった。
これらの観察結果を従来触媒の振舞いと比較して示したのが図1である。ペロブスカイト型酸化物では、酸化雰囲気中ではPdは酸化物中でBサイトに固溶しており、還元雰囲気では析出して金属状態となっている。この構造変化は雰囲気の変化に呼応して可逆的である。この触媒の自己再生作用は高速で機能することが、放射光を用いた実験で明らかにされた。
2.パルス重イオンビーム照射による固体内からの弾性波(会員ページ
)
(独)理化学研究所・仁科加速器研究センター
加速器応用研究グループ
グループディレクター 神原 正
GeV領域のエネルギーを有する高速イオンビームを固体中に打ち込むと、イオンは固体の原子を電離・励起しつつ固体中を進行し、数mm程度の深さで停止する。この時にイオンが進む距離当たりで失うエネルギーを阻止能と呼んでいる。阻止能はイオンの種類、速度及び固体の種類によって決まっている。入射イオンが固体中で停止する直前の深さで阻止能はピークを示し、これをブラッグピークと呼ぶ。このブラッグピーク周辺ではイオンから固体の原子系に与えられるエネルギー密度が大きく、励起、電離、欠陥の形成、その結果としての構造変化などの照射効果が大きいと考えられるが、固体表面から数mm程度の深さでの現象の直接観察は容易ではない。この時、固体中で照射によって短時間の間に密度や構造の変化が生ずると、歪みと応力変化により超音波領域の弾性波が発生する。弾性波は固体中を良く伝播するので、その波を固体表面で観測できるはずである。その波形や伝播時間を地震学や非破壊検査の手法で解析することにより、固体内の照射効果の情報がマイクロ秒以下の実時間で得られると考えられる。
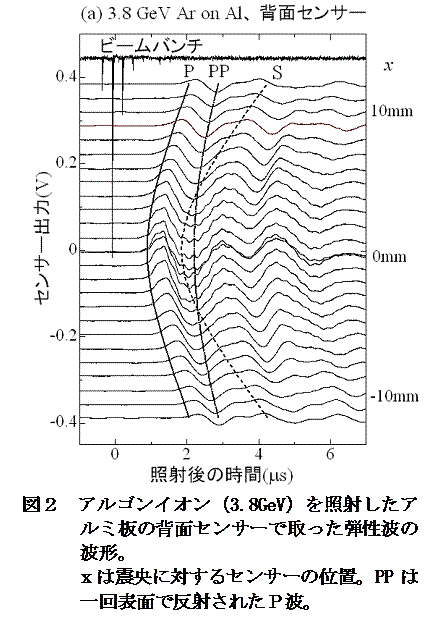 神原講師は理研の重イオン加速器リングサイクロトロンで加速した高速のアルゴンイオン(3.8GeV)及びキセノンイオン(3.5GeV)を、色々な固体試料に照射し、発生する弾性波を試料表面にて観測した結果を報告した。試料は4cm角・厚さ1cmの正方形の板状のものを用いて、その板面に垂直にイオンビームを真空中で照射した。ビームの入射面の裏側中央と側面中央に市販の圧電型超音波センサーを固定した。それぞれを背面センサーと側面センサーと呼ぶ。超音波センサーと試料は一体として、全体をビームに対して垂直方向に移動して、試料面での照射位置を変えつつ測定を繰り返した。図2は測定結果の一例である。これはアルゴンビームで多結晶金属アルミ板を照射した場合の背面センサーでの観測結果である。図においてx=0が震央に対応しており、そこからxが変化するにつれて、震央からのセンサーまでの距離が大きくなるため、伝播時間が長くなっている。図中Pと記されている実線は震源の深さを5.82mmとしたときの、P波の到達予想時刻であり、波の立ち上がりと良く対応する。一方点線Sは同じ条件でのS波の到達予想時刻を示しているが、構造は見られない。PPは表面で一回反射した後に、背面に到達したP波である。地震においてはP波よりもS波のほうが振幅が大きいので、本実験の場合との相違は震源の運動の違いと関係している。
神原講師は理研の重イオン加速器リングサイクロトロンで加速した高速のアルゴンイオン(3.8GeV)及びキセノンイオン(3.5GeV)を、色々な固体試料に照射し、発生する弾性波を試料表面にて観測した結果を報告した。試料は4cm角・厚さ1cmの正方形の板状のものを用いて、その板面に垂直にイオンビームを真空中で照射した。ビームの入射面の裏側中央と側面中央に市販の圧電型超音波センサーを固定した。それぞれを背面センサーと側面センサーと呼ぶ。超音波センサーと試料は一体として、全体をビームに対して垂直方向に移動して、試料面での照射位置を変えつつ測定を繰り返した。図2は測定結果の一例である。これはアルゴンビームで多結晶金属アルミ板を照射した場合の背面センサーでの観測結果である。図においてx=0が震央に対応しており、そこからxが変化するにつれて、震央からのセンサーまでの距離が大きくなるため、伝播時間が長くなっている。図中Pと記されている実線は震源の深さを5.82mmとしたときの、P波の到達予想時刻であり、波の立ち上がりと良く対応する。一方点線Sは同じ条件でのS波の到達予想時刻を示しているが、構造は見られない。PPは表面で一回反射した後に、背面に到達したP波である。地震においてはP波よりもS波のほうが振幅が大きいので、本実験の場合との相違は震源の運動の違いと関係している。
側面センサーにおいてもP波は観測されたが、S波については変化が見られなかった。
天然の地震は地下の断層のすべりによっておこされるため、横波であるS波の振幅のほうが縦波であるP波のそれよりも大きくなる。一方、本研究の場合はP波のみが顕著に観察されたことから、震源での運動はずれ運動ではなく、膨張収縮運動であることを示している。このことを示唆する実験結果として熱膨張率の極めて小さいアンバー合金と溶融シリカにおいては弾性波が観察されなかった。石英や瑪瑙では弾性波が観測されるので、弾性波の発生には物質のマクロな熱的性質が重要であることが明かである。一方、同じ試料でもイオンの種類、エネルギーの変化により、弾性波の様子は変化する。震源の広がり方と表面との関係、照射によるひずみの発生過程など今後の検討課題である。
3.イオンビームによる水蒸気分解・水素生成酸化物セラミックス触媒の研究(会員ページ
)
名城大学理工学部 教授 森田 健治
森田講師は名古屋大学大学院工学研究科で永年にわたってエネルギー材料の照射効果を研究されてきた。今回の講演では核融合材料などにおける水素同位体の振舞いの研究の中から発見された材料中に注入された重水素(D)が、大気中で短時間の間に軽水素(H)に置換される興味ある現象についてであった。
森田講師らはこの現象がBaCeO3のようなペロブスカイト型酸化物セラミックスの水分解水素ガス生成の触媒効果であることを明らかにしてきた。BaCe0.95Y0.05O3-δでは水蒸気と接触する試料表面積が500m2の場合には、水素ガス放出速度は1Nm3/hrであった。水素の製造装置として使用するためには、触媒機構の解明と水素放出速度のより大きい材料の開発が必要となる。
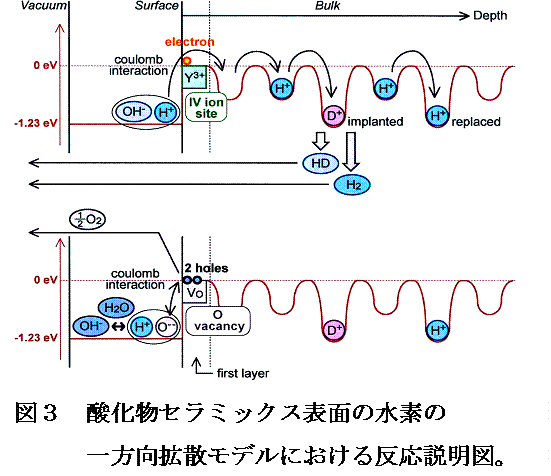 最初に材料表面で起こる現象が逆の置換を行った場合にどうなるかを検証した。しかしながら材料中への注入Hは重水蒸気中のDとは殆ど置換しないことが分かった。D-H置換とH-D置換の違いを一方向拡散モデルで説明した。すなわちD-H置換は表面で水が分解され形成されたH+が酸化物内部に拡散し、イオン注入されたDと再結合してDHガスとして放出され、Dが抜けた格子点に別のH+が捕獲される。この機構によれば放出されるガスはDHに限定されることなく、H+もまたH2ガスとして放出されるので、水素注入酸化物セラミクスが水分解水素ガス放出触媒機構を有することを示している。
最初に材料表面で起こる現象が逆の置換を行った場合にどうなるかを検証した。しかしながら材料中への注入Hは重水蒸気中のDとは殆ど置換しないことが分かった。D-H置換とH-D置換の違いを一方向拡散モデルで説明した。すなわちD-H置換は表面で水が分解され形成されたH+が酸化物内部に拡散し、イオン注入されたDと再結合してDHガスとして放出され、Dが抜けた格子点に別のH+が捕獲される。この機構によれば放出されるガスはDHに限定されることなく、H+もまたH2ガスとして放出されるので、水素注入酸化物セラミクスが水分解水素ガス放出触媒機構を有することを示している。
DV-Xaクラスター法によるこのペロブスカイト酸化物のエネルギー準位の計算と系統的な実験の結果から、この現象は次の反応によるものであることが分かった。関与するのは四価イオンと置換された三価イオンによって形成される価電子帯近傍のアクセプター準位と三価元素のドープに伴う伝導帯近傍のドナー準位を形成する酸素空格子である。
(1)Ce4+サイトのY3+イオンにおける反応:
YCe− + H2O + E1 −Ed → H+ + OH−
(1)
(2) VO2+
サイトにおける反応:
VO2+ + H2O + E2−Ed → H+ + OH− + 2 holes + OH−(neibgh.)
→ (1/2)O2 + H2O
(2)
ここでE1(〜2eV)、E2(〜8eV)はそれぞれクーロン相互作用による放出エネルギー、Edは表面におけるH2Oの解離エネルギー(1.23eV)である。
これらのクーロン相互作用の結果、格子欠陥の電荷は中和され、酸素空格子にはドナー電子が戻り、 YCe−には正孔が戻り、消滅するので、水分解と水素ガス生成の持続のためには、格子欠陥が定常的に熱的に電離、帯電しなければならない。そのためにはドナー、アクセプターのエネルギー準位が伝導帯、価電子帯に近いことが必要である。
実験ではバルク材と薄膜材についてD-H置換速度の三価添加元素濃度依存や温度依存性についても調べた。第一原理計算によるドナー、アクセプターのエネルギーの値を用いると上記の実験結果を説明することが出来ることから、今後水素ガス放出速度の大きいセラミックスの設計が可能になりそうである。
この結果を利用した水素製造装置の実現には、酸化物セラミックスの薄膜化技術の開発とそれから放出される低温・低圧水素ガスを効率よく吸蔵・放出する材料開発が求められるとのことである。
4.粒子ビーム照射による物質ナノ構造の破壊と創製(会員ページ
)
兵庫教育大学 自然・生活教育学系
物理教室 教授 庭瀬 敬右
近年のナノテクノロジーの進展に伴い、マクロ的には構造の破壊にいたる粒子線照射や衝撃圧縮などの手法が、ナノサイズの視点からは有益な機能や新物質創成へ繋がる可能性を秘めていると考えられる。庭瀬講師はそのような例として 1)低温電子線照射によるナノ構造の自己組織化、2)黒鉛の照射誘起アモルファス化とウイグナー欠陥、3)C60フラーレンの衝撃圧縮による炭素空洞球とアモルファスダイヤモンドの創成 の三つのテーマについて講演を行った。
1)金属薄膜に高エネルギー電子線を照射すると、電子線出射側表面の原子がスパッターされて、表面原子空孔が形成され、温度に依存してこれら原子空孔が相互反応を起こす。照射の継続により、相互作用の結果として、様々なナノパターンが形成される。金の(001)薄膜に100Kで360-1250keVの電子線照射を行うと、照射方向の違いによって異なる構造が形成される。すなわち[001]方向では[100],[010]に沿う幅1から2nmのナノサイズの溝、[011]方向では[100]方向のナノサイズの溝が形成されるのに対して、[111]方向からの照射では溝は形成されない。形成された溝は室温まで温度を上げると消失するので、原子の表面拡散が関与していることは明かである。照射による究極の構造はナノワイアである。
2)黒鉛は最初の原子炉であるシカゴパイルにおいて中性子減速材として使用されて以来、多くの原子炉で使われており、それに伴って照射損傷の研究も1942年のウイグナーの予言に始まる長い歴史がある。それにもかかわらず現在においても研究者の間で必ずしも共通の理解は得られていない。室温でHOPG黒鉛に1dpa程度の高エネルギー粒子線の照射を行い、TEMでc軸方向から観察すると、その電子回折像はハローとなり、非晶質化したことが示唆される。同じ試料のc軸に垂直な方向からの高分解能電顕像には明瞭な積層構造が見られたことから、この非晶質化はc面内だけで生じていると結論された。庭瀬講師はこれまでに黒鉛の照射欠陥に関してTEMやラーマン分光法による多くの論文を発表しており、c面内での非晶質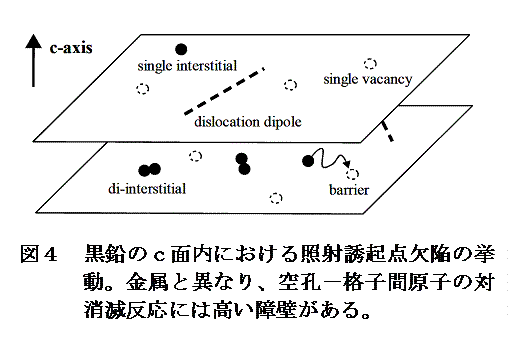 化の過程を説明した。照射に伴う欠陥形成の素過程は原子の弾き出しによるフレンケル欠陥(空孔−格子間原子対)の生成であるが、多くの金属では形成されたフレンケル対は簡単に対消滅を起こし、また移動しやすい格子間原子は表面シンクに逃げて材料中には留まりにくい。庭瀬講師の解析によると黒鉛では照射によって形成された空孔と格子間原子の対消滅には大きなバリアがあり、また欠陥はc面内に留まるため、各c面内での生成欠陥には保存則が成り立つ。図4はc面内に存在する欠陥種を示している。この結果、c面内の空孔濃度は7%にも達し、非晶質化は空孔の蓄積による黒鉛−非晶質相転移であると結論される。また非晶質構造は複空孔が関与するc面内での炭素原子の5角形−7角形対による転位双極子の形成が関係していると結論した。この5角形−7角形対の存在はナノチューブで著名な飯島らのグループのHRTEMで報告されているそうである。
化の過程を説明した。照射に伴う欠陥形成の素過程は原子の弾き出しによるフレンケル欠陥(空孔−格子間原子対)の生成であるが、多くの金属では形成されたフレンケル対は簡単に対消滅を起こし、また移動しやすい格子間原子は表面シンクに逃げて材料中には留まりにくい。庭瀬講師の解析によると黒鉛では照射によって形成された空孔と格子間原子の対消滅には大きなバリアがあり、また欠陥はc面内に留まるため、各c面内での生成欠陥には保存則が成り立つ。図4はc面内に存在する欠陥種を示している。この結果、c面内の空孔濃度は7%にも達し、非晶質化は空孔の蓄積による黒鉛−非晶質相転移であると結論される。また非晶質構造は複空孔が関与するc面内での炭素原子の5角形−7角形対による転位双極子の形成が関係していると結論した。この5角形−7角形対の存在はナノチューブで著名な飯島らのグループのHRTEMで報告されているそうである。
講演の最後には時間がなくなってしまったので、庭瀬講師らが近年行っているC60フラーレンの50〜60GPaでの衝撃圧縮実験の興味ある結果だけを披露した。徐冷試料においてはμmオーダのピンポン球のような中空の黒鉛球が形成され、急冷材ではダイアモンド結合を示すが、構造的には非晶質に見える材料が出来た。中空の黒鉛球は超高温に耐えるマイクロカプセルとして使えそうとの話であった。
第6回となる今回のエキゾチックビームシリーズでも、様々なビーム利用の講演を取り上げることが出来た。これは岩瀬委員長はじめ企画部会の委員の方々のお陰である。また、交流会ではすべての講師の方に残っていただき、参加者と有意義な交流の場をもつことが出来たことを主催者として感謝したい。 (大嶋記)