��R�R����ː��Ȋw�������E���G�L�]�`�b�N�r�[���V���[�Y�i5�j����
�\�L������̓G�L�]�`�b�N�r�[���V���[�Y�̑�5��Ƃ��ĕ���19�N�V���P3���i���j13:30����17:30�܂ŏZ�F�N���u�i���s����j�ŊJ�Â����B����̍u�t�͕ۓc�p�m���i�_�ˑ�w��w�@�H�w�����ȁj�A��؊���iSPring-8�j�j�A�哹���s���i���{���q�͌����J���@�\�j�A�؉����N���i�d�͒����������j�̂S���̕��X�ł������B
�P�D
�d�q��N�ɂ��i�m���q�̑������Ƃ��̕]���i����y�[�W )
�@�@�@�@�_�ˑ�w��w�@�H�w�����ȁE����
�ۓc�@�p�m
�ۓc�u�t�͑���w�ݔC������d�q�������i�ȉ��d���j���ɕ����̏������������^�̏������u��g�ݍ��݁A�l�X�ȍ����i�m���q��d�����ō쐬���A���̐U�����̂��̏�ώ@���s�������i�m���q�̎������قȋ����𖾂炩�ɂ��Ă����B����̍u���ł͇V�|�X�������������̂̈�ł���GaSb�����グ�A���`���⑊�]�ڂɋy�ڂ��d�q��N���ʂɂ��Ă̌n���I�Ȍ������ʂɂ��ču�������B
�����͓d���̊ώ@���ɕێ����ꂽ���J�[�{������\�������}�C�N���O���b�h��Ɏ�����Ga�����Sb���������ăi�m���q���쐬�����B���J�[�{����ŗ��҂͋}���ɔ�������GaSb���������`�������B�����������573K�A3.6ks�̋ψꉻ�ē݂��s���Ă���d�q��N�����ɋ������B�d�q��N�����̓G�l���M�[�F25�`200keV�A�t���b�N�X�F5�~1020�`5�~1021e/m2s�A���x�F293�`573K�͈̔͂ōs�����B
��N�G�l���M�[��75keV�̏ꍇ�̌��ʂ�͎��I�ɐ}1�Ɏ������B
���ʂ͎��̂悤�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B
�i�P�j GaSb�i�m���q�͓d�q��N�ɂ���đ�������A�����t�@�X�����A�����͉��x��T�C�Y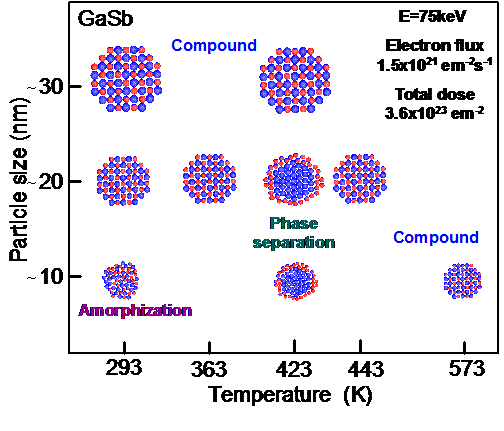 �ɑ��Ĕ���`�ȉ����������B�܂��A�d�q��N�U�N�������͓d�q���ʂ���ѓd�q�����x�̑���ɂƂ��Ȃ����i����A���ꂼ��A�������Ԃ₵�����l�����݂���悤�ȋ��͌��ۂƂ��Ă̂ӂ�܂��������B
�ɑ��Ĕ���`�ȉ����������B�܂��A�d�q��N�U�N�������͓d�q���ʂ���ѓd�q�����x�̑���ɂƂ��Ȃ����i����A���ꂼ��A�������Ԃ₵�����l�����݂���悤�ȋ��͌��ۂƂ��Ă̂ӂ�܂��������B
�}1�@��N�G�l���M�[�@75keV�A�t���b�N�X�y�ѐ��ʂ��e�X1.5�~1021e�m-2s-1�C3.6�~1023e�m-2
s-1�̏ꍇ��GaSb���q�̑��]�ډ����̖͎��}
(�Q)�d�q��N�U�N�������̃v���Z�X�Ƃ��āA�i�m���q�����Ƀ{�C�h���`�������ƂƂ��ɁAGaSb�̊i�q�萔�����傷�邱�Ƃ���A�d�q��N�ɂ���ăi�m���q�����Ɍ`������錴�q��E��i�q�Ԍ��q�����q�ړ��Ɋ֗^���A�\�ʂȂǂ̃V���N�ւ̏��ł���эČ����ɂ���đ��������x�z�����B�܂��A�����͉��x�ɂ���ĕω����邾���łȂ��A�T�C�Y�ɂ���Ă��ω�����B
�i�R�j�i�m���q�ɂ�����d�q��N�U�N�������́A��N��Ԃł̕s���艻�쓮�́A�����x��N��ԁA�M���t�A�i�q��A�_���ړ��̑��x�ߒ����̃V�i�W�F�e�B�b�N�Ȍ��ʂɎx�z�����B
�u���ł�GaSb�������q�������ɂ��A���l�ȗl�����������Ƃ��d�����A��ܑ��Ŏ�����A�i�m�T�C�Y���������قȕ������������邱�Ƃ��o�����B
�Q�D���P�x�Ό�X����p���������̌����i����y�[�W )
�i���j���P�x���Ȋw�����Z���^�[�E
���p�������i����@�劲�������@��@�
��؍u�t��SPring-8�̓������\���Ɋ��p�����V�������C����������Љ���BSPring-8���瓾������ˌ��́A�ʏ�̊Nj����瓾����X����10���{�̋P�x������A�������g���ϐ���Ό�������L����D�ꂽ�����ł���B���Ƃ���X���͎����̌����ɂ͌����Ă��Ȃ��������A�h�C�c�̌����҂ɂ���ĉ~�Ό�X���ɑ���z���X�y�N�g���������ɂ���ĈقȂ�X�����C�~��F��(X-ray magnetic circular dichroism:XMCD)����������A���P�x�̕��ˌ���p���邱�Ƃɂ���āA�V�������C�����@���\�ƂȂ����B���̕��@�̑傫�ȓ����͌��f�I��I�Ȏ��C���肪�s���邱�Ƃł���B
��؍u�t�͏��߂ɕ��ˌ��̓����␢�E�ɂ������\�I�ȕ��ˌ��{�݂ɂ��ďЉ�Ă���A�{��̎��C�����@�ɂ��ču�������B
X���̃G�l���M�[���z������銄���͌��f���ƂɈقȂ�B����͌��f�̃G�l���M�[���x���ƊW���Ă���A�����z�������G�l���M�[�����f�z���[�ƌĂ�ł���B���f�z���[�̃G�l���M�[�͌��q�ԍ��ɔ�Ⴕ�đ傫���Ȃ�A�dX���̈�łׂ͗荇�킹�̌��q�Ő�100eV������Ă��邱�Ƃ���A�ړI���f�̋z���[�ɍ��킹���z���X�y�N�g���𑪒肷�邱�Ƃɂ��A���f�̓d�q��Ԃ�m�邱�Ƃ��o����B
XMCD�̑���ɂ͉~�Ό������G�l���M�[�ς�X����p���āA�E���A�����ɕΌ�������X���������ɏƎ˂��A���̋z���W���̈Ⴂ���玥���̕����ƃ��[�����g�̑傫�������߂���B�}2�͂��̑���@�̖͎��}�ł���BSPring-8��XMCD�r�[�����C���ł̓_�C�A�����h�������ڑ��q�Ɏg�����Ƃɂ�蒼���Ό�X�����~�Ό�X���ɕς��Ă���B���̕��@�Ō��ݕΌ��x���ق�100���̉~�Ό��������邻���ł���B
����̎���Ƃ��ăn�[�h�f�B�X�N�Ȃǂ̎��C�L�^�����ɗp�����Ă���Co���听���Ƃ���CoCrPtB�̂悤�ȍ����ɂ��Ă�Pt�̌��ʂ��܂��������BPt�͒P�̂ł͋��������������Ȃ����A��������Co�ƍ������`�������ۂɂ́ACo�Ƃ̊E�ʂɑ��݂���Pt�͌��q������0.6��B�Ƃ����傫�ȗU�N���C���[�����g�������Ƃ����������B�ʂ̗�Ƃ��ăi�m�T�C�Y��Au�����q�ɗU�N����鎥���ɂ��ďЉ���B�o���N��Au�͔����������Ƃ��Ēm���Ă��邪�A���a�����i�m���[�g���ȉ���Au�i�m���q���������������Ƃ̌��ʂ�SQUID�����ɂ���Ď������ꂽ�B�������Ȃ���SQUID�ł̐M���͎ォ�������߁A�͂��߂�Fe�Ȃǎ����s�����̎����ւ̍������^��ꂽ���AXMCD�ɂ����Au�z���[�ׂ�Ɩ��ĂȐM�����m�F�ł����B���������ăi�m�T�C�Y��Au�����q�͋������I�Ȏ�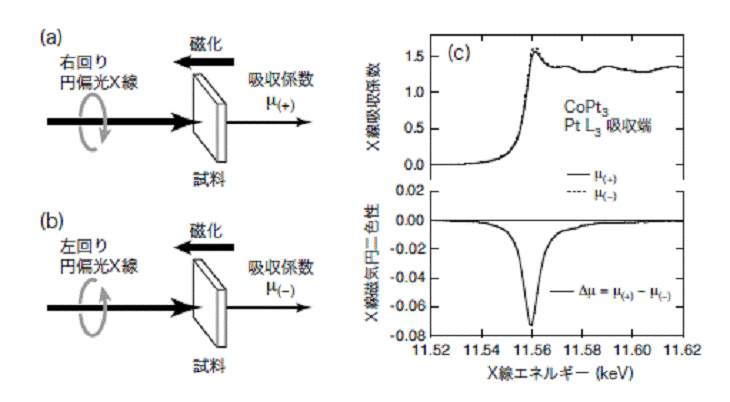 �C�ɂ��������Ƃ����炩�ƂȂ����B
�C�ɂ��������Ƃ����炩�ƂȂ����B
���̂悤��XMCD�͎��������̃c�[���Ƃ��č��͊m�����Ă���A�����ΏۂƂ��Ă̓i�m�\�������ޗ��A���C�L�^�f�o�C�X�A���q�����̕���ő�z�������ʂ��������Ă���B�܂��A�����@�ɂ͌���XMCD,������XMCD,�������ł�XMCD�Ȃǂ�����A����̔��W�����҂ł���̂ŁA�������]����ꍇ�ɂ͐ϋɓI�ɉۑ�\�����ė~���������ł���B
�}2�@X�����C�~��F��(XMCD)����̖͎��}
�R�D�����x���[�U�[�쓮���G�l���M�[�z�q�����̊J���Ƃ��̗��p�����i����y�[�W )
���{���q�͌����J���@�\�E�����Ȋw������
�ʎq�r�[�����p��������@������ȁ@�哹���s
�哹�u�t�͊����Ȋw�������̏Љ�Ɠ����Ŋ����ɍs���Ă��郌�[�U�[�쓮�z�q���̌����J���̌���Ƃ��̗��p�����ɂ��Ă̍u�����s�����B
�ߔN�̒��Z�p���X�����x���[�U�[�Z�p�̐i�W�ɂ��A���^�̃��[�U�[�쓮�����킪���������Ă����B���j�I�ɂ͂��̎�@�͓c���i�������Ȋw���������j�A�h�[�\���ɂ����1979�N�ɒ�Ă��ꂽ���̂ł���A���̌��^�Y�_�K�X���[�U�[�ɂ�鍂���d�q�E�����C�I���̔������o��1990�N��ɂ͕č��̃��[�����X���o���A��������60MeV�z�q���̔����ɐ������Ă���B
�t�F���g�b�̋ɒZ�p���X�̍����x���[�U�[�^�[�Q�b�g�ɏƎ˂���ƁA�ɂ߂Ē������̗ǂ����G�l���M�[�z�q����������B���̔����@�\�͎��̂悤�ɐ��������B�܂����[�U�[�d��ɂ���d�ׂ̑傫���d�q���^�[�Q�b�g���Ń��[�U�[�i�s�����ɋK���I�ɉ�������A�^�[�Q�b�g�\�ʂ̐��d�ׂƂ̊Ԃ̓d�E���x�������Ă����B�₪�Ă��̒����d�E�ɂ��^�[�Q�b�g���ʂɌ`������Ă��鐅�f��������ł��y���C�I���ł���z�q�����X�ɏW�c���������B���[�U�[�@�ł�1�~�N�����̒���������100���d�q�{���g���x�̉����d�ꂪ����ɐ�����Ƃ̂��Ƃł���B���[�U�[�@�̓����͗z�q���̔����̈悪10�~�N�����Ə������A�������鎞�ԕ������s�R�b�ȉ��ƒZ���������̗ǂ��z�q�����L����p10�x���x�œ`�d����B�܂�ɒZ���ԂɏW�������勭�x�z�q���邱�Ƃ��o����Ƃ����̂��ő�̓����ƂȂ��Ă���B�����Ȋw���ł̌������ʂƂ��ď]���̉�����ɂ����@�����͂邩�ɕi���̍����r�[����������悤�ɂȂ����B���ݗz�q���̎��ԕ���1ps���x�ł��̒���108�`1010�̗z�q���l�܂��Ă���ƌ��ς�����B�}3�͌��݂܂ł̗z�q���Ɠ���ꂽ�ō��G�l���M�[�̐��ڂ��������B
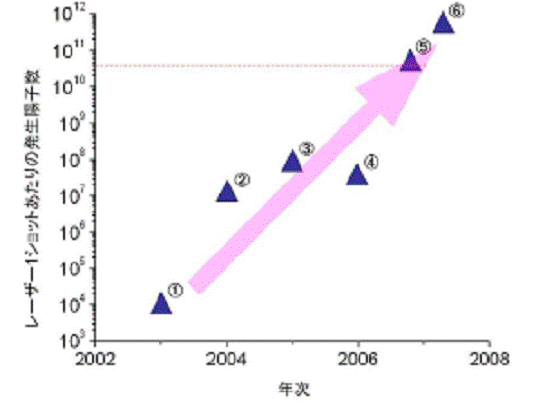 ���p�����̈�̗�Ƃ��ėz�q�����W�I�O���t�B�̏Љ�������B�����^�[�Q�b�g�Ƀ��[�U�[�Ǝ˂��邱�Ƃɂ��g�U�z�q���r�[���邱�Ƃ��ł���B���̃r�[�����g���ēd�q�������̎����Œ�Ɏg�p����郁�b�V���̎B�����s���A��ԕ���\�Ƃ���10�ʂ��̑����B�邱�Ƃ��o�����B�܂��A���[�U�[�쓮�v���Y�}�𗘗p�����ꍇ�ɂ͗z�q���̑��ɂw���A�e���w���c�g�ɉ����Ē����q���Ȃǂa������m���琔10��m���x�̋����̈悩��̎��ԓ��������ۏ��ꂽ����ނ̃r�[���邱�Ƃ��o���邱�Ƃ���}���`�r�[���n�����p�����C���[�W���O���\�ƂȂ�B�����ł͍ō��G�l���M�[2.4MeV�őS�G�l���M�[�o���h�ɂ�����8�~1010��/shot�̗z�q���Ɠ���K�������܂�2�~1019���q/sr��X�����g���ď�L���l�d�q�������p���b�V���̓����B�����s�����B���̎��ɂ͗z�q���ł̓��b�V���ɂ�����12��m�̕��̑����N���ɓ���ꂽ���AX���ł̓t�H�g�������s�����Ă��邽�߂��N���ȑ��͎B��Ȃ������B�����X�����w�f�q�̓����ɂ���Č��q���W�߂đN���ȑ��̎擾��}��Ƃ̂��Ƃł���B
���p�����̈�̗�Ƃ��ėz�q�����W�I�O���t�B�̏Љ�������B�����^�[�Q�b�g�Ƀ��[�U�[�Ǝ˂��邱�Ƃɂ��g�U�z�q���r�[���邱�Ƃ��ł���B���̃r�[�����g���ēd�q�������̎����Œ�Ɏg�p����郁�b�V���̎B�����s���A��ԕ���\�Ƃ���10�ʂ��̑����B�邱�Ƃ��o�����B�܂��A���[�U�[�쓮�v���Y�}�𗘗p�����ꍇ�ɂ͗z�q���̑��ɂw���A�e���w���c�g�ɉ����Ē����q���Ȃǂa������m���琔10��m���x�̋����̈悩��̎��ԓ��������ۏ��ꂽ����ނ̃r�[���邱�Ƃ��o���邱�Ƃ���}���`�r�[���n�����p�����C���[�W���O���\�ƂȂ�B�����ł͍ō��G�l���M�[2.4MeV�őS�G�l���M�[�o���h�ɂ�����8�~1010��/shot�̗z�q���Ɠ���K�������܂�2�~1019���q/sr��X�����g���ď�L���l�d�q�������p���b�V���̓����B�����s�����B���̎��ɂ͗z�q���ł̓��b�V���ɂ�����12��m�̕��̑����N���ɓ���ꂽ���AX���ł̓t�H�g�������s�����Ă��邽�߂��N���ȑ��͎B��Ȃ������B�����X�����w�f�q�̓����ɂ���Č��q���W�߂đN���ȑ��̎擾��}��Ƃ̂��Ƃł���B
�}3�@�����ɂ�����z�q���ƍō��G�l���M�[�̔N�����ڍō��G�l���M�[�F�@1MeV�A�A0.9MeV�A�B1.4MeV�A�C2.2MeV�A�D3.8MeV�A�E4MeV
���[�U�[�쓮�z�q���������u�ł͏��^�̑��u�ɂ�荂���x�̗z�q���������邱�Ƃ���A���̈�×p�ւ̉��p���傫�����҂���Ă���B���łɁu����v�Ȃǂ̗��q�����Â��߂��������[�U�[�쓮���u���݂̌v�悪���A�ƁA�p�A�āA�؍��Ŏn�����Ă���B���p�Ɏ���܂łɂ͂܂�10�N���x�̃X�p�����K�v�Ƃ̂��Ƃł��������A���E�I�Ɂu����v�ɑ��闱�q�����Â͑傫�ȗ���ɂȂ��Ă���̂ŁA����Ȃ錤���̐i�W�����҂��������̂ł���B
�S�D�j����Ǝˉ��̔R���ޗ��ӂ�܂��ƒ����������ւ̓W�]�i����y�[�W )
�d�͒����������E���q�͋Z�p�������@��Ȍ������@�؉��@���N
���q�͔��d�̌���ł̖��̈���A�R���̌��������邱�ƂȂ��A���q�F�����܂ł��^�]�ł��邱�Ƃł���B���݂̌��q�͔��d���̔R���͕��ς���5�N�Ԍ��q�F���ł̔R�Ă��\�ł��邪�A�����2�{�ȏ��10�`15�N�g�p�o���钴�������R���̎������҂���Ă���B���q�F�����̗��ꂩ��A����͕s�\�ł͂Ȃ����A�ޗ��Ɋւ���m�����܂��s�\���ł���B�H�w�I�Ȋ�{�v���Ƃ��Ă͇@�j�������Ă��̐ϖc�����������Ȃ����ƁA�A�j�����������ł����K�X�i���Xe�j��R���y���b�g���ɕ����߂Ă������Ƃ�2�_�ł���BUO2�����̗v�������Ă��邱�Ƃ͕������Ă��邪�A���̋@�\�ɂ��Ă͕s���ŁA��b�����Ƃ��Ďc���ꂽ�ۑ�ƂȂ��Ă���B
���q�͈ψ���ł�2005�N����5�N�Ԃ́u�V�N���X�I�[�o�[�����v�Ƃ��ăg�b�v�_�E�������Łu�ƎˁE�����ʗ̈�̍ޗ���������̂��߂̐V�����G���W�j�A�����O�v�𗧂��グ�A�؉��u�t�̓v���W�F�N�g���[�_�[�̈�l�ł���B���̃v���W�F�N�g�ł͑S�̂�6�ۑ�ɕ����ē��{���q�͌����J���@�\�������A������w���������{�̃R���g���[���Z���^�[�ɂ����A���O��3�����@�ւ̋��͂����Ȃ���i�߂邱�ƂɂȂ��Ă���B���{����w�����_�̈�Ƃ̂��Ƃł���B�}4�ɂ��̊T�v���������B
�v���W�F�N�g�ł͂܂�1980�N��Ɍ��������E������7�����R�Ă������ɏo������R���Z���~�b�N�X�����̍ח����i100nm�a�j����уJ���t�����[�g�D�i�L���t���N�^���j�̔����@�\�ɒ��ڂ����B�t�����X�ɂ�����f�[�^�Ƃ��āA���R�ĉ���j�Q���錴���Ƃ��ĔR���y���b�g�̍ŊO�����ɏo���������ȑg�D�i�����g�D�j���w�E���ꂽ�B���̑g�D�̓����͌������ח����Ƒe��C�A�̐����ł���B�e��C�A�ɂ͍����̊j����������K�X���܂܂�Ă���B�ח��������������ɂ͓]�ʂ͑��݂����A�Ǝ˂ɔ����������C������v���Z�X�������I�ɐ��������Ƃ��������Ă���B���̂悤�Ȍ����ȑg�D�̕ω���������ȑO�Ɍ����\�ʂɂ�
�@�@�@�}4�@�V�N���X�I�[�o�[�����̌����v��T�v
�o111�p�ϑw���ׂƌ�����i�q���ׂƃy���b�g�����ɋ̔������ώ@���ꂽ�B�����̊ώ@���ʂ܂��ĐV�N���X�I�[�o�[�����ł͉�����ƌv�Z�Ȋw�Ƃ�g���킹�A�y���F�R���i�Ƃ��ɂl�n�w�R���j�̍��R�ēx����j�Q�����Ƃł���Ƃ���́A
�gUO2�Z���~�b�N�X�̍ח����h���Č����A���́g�V�������@�h�ɂ���ċZ�p�J�����ł��邱�Ɓi�T�N�Z�X�X�g�[���[�j���������Ƃ����B��@�Ƃ��Ă�
���F���g�D�ω��̍Č���������Ŏ������邱�ƁB
������Ǝˁ{���q�X�P�[������E�ώ@�{�v�Z�Ȋw�̃V�~�����[�V�����Z�p���J�����A���q�F�Ǝˁ{�Ǝˌ㎎���iHBRP�Ȃǁj���ւ���B����ɂ�莎���̂P�T�C�N�����A���N��v����Ƃ�����A�P�����`�T�ʼn\�ł���i�`1000�{�̉����j�B
���v�Z�@�̒��ŘF���g�D�ω����Č�����
��ꌴ���v�Z�{���q���͊w�^�����e�J�����@�@�ŁA�Ǝˉ��̑g�D�ω����Č�����B���q�X�P�[�����ׁi�N���X�^�[�j�ɑΉ��ł���|�e���V����������B�ۑ�Ƃ��Ă͂��d�q�n���ꌴ���Ŏ�舵���_������B
�����̌����ɂ�UO2�̖͋[�����Ƃ��Č����n�Ȃǂ��ގ����Ă���CeO2��p���ă����g�D�̌`�����ǂ̂悤�ȏ������ōČ��o���邩�ׂ����ʁA
1.���q�F�O�ʼn������p���A���R�ēx�R���̍ח����i�����g�D�̌`�����J�j�Y���j���͋[�ށiCeO2�j�ōČ��o���邱�Ƃ��A���炩�ɂȂ����B
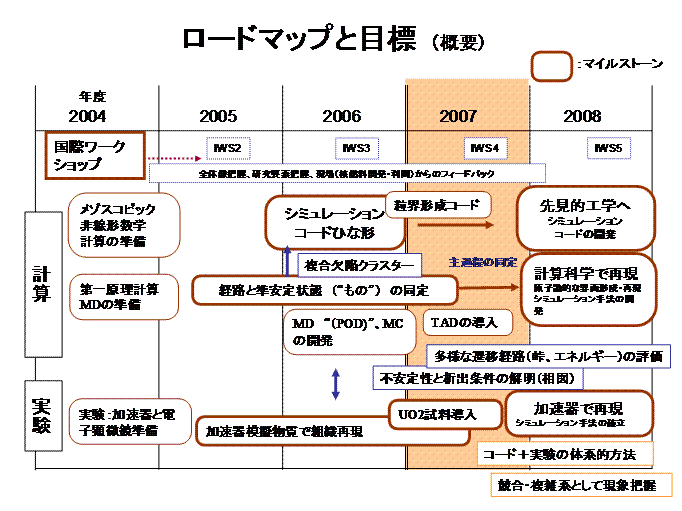 2.��ꌴ���v�Z�ɂ���āAUO2+X�i�q���ŁA�Q�̎_�f���q�����q�idimer, [O2] �j������A���̕Њ����U4O9�̎_�f�z�u�Ƃ��Ēm���Ă���Willis��O�Q�ʒu�ɑΉ����邱�Ƃ������B
2.��ꌴ���v�Z�ɂ���āAUO2+X�i�q���ŁA�Q�̎_�f���q�����q�idimer, [O2] �j������A���̕Њ����U4O9�̎_�f�z�u�Ƃ��Ēm���Ă���Willis��O�Q�ʒu�ɑΉ����邱�Ƃ������B
�����̐��ʂ܂��āAUO2�ł̍Č��ɒ��풆�Ƃ̂��Ƃł���B
�Ō�ɔ��d����ł̊j�R�������������̃V�i���I���A����������ƌv�Z�Ȋw�I��@��g�ݍ��킹���ޗ��J���ɂ������������悤�w�͂𑱂��Ă���Ƃ̌��ӂ�\�킳��ču������߂��������B
�G�l���M�[�����ɖR�����䍑�Ƃ��ẮA����A�j�R����@���ɗL�����p���Ă������͍��̃G�l���M�[�Z�L�����e�B�Ƃ��ďd�v�ȉۑ�ł���A���̂悤�Ȓ����Ȏ�@�œ�肪����������Ă������Ƃ����҂������Ɗ������B
��5��ƂȂ鍡��̃G�L�]�`�b�N�r�[���V���[�Y�ł��A�l�X�ȃr�[�����p�̍u�������グ�邱�Ƃ��o�����B����͊␣�ψ����͂��ߊ�敔��̈ψ��̕��X�̂��A�ł���B�܂��A�𗬉�ł͉��H�������炨�o�ł����������؉��u�t���܂߂Ă��ׂĂ̍u�t�̕��Ɏc���Ă��������A�Q���҂ƗL�Ӌ`�Ȍ𗬂̏�������Ƃ��o�������Ƃ���Î҂Ƃ��Ċ��ӂ������B�@�@�@�@�@�@�@�@�i�哈�L�j