�@
�@
��Q�V����ː��Ȋw������u�L
�J�ÁF�����P�V�N�V���P�T���@���F�Z�F�N���u
�@�\�L������́A�G�L�]�`�b�N�r�[���V���[�Y�̑�R��Ƃ��ĕ���17�N7��15���i���j13:30����17:30�܂ŏZ�F�N���u�i���s����j�ɂ����āA�@�A�~�]���i���G�l���M�[�����팤���@�\�E�������j�A��ʐ����i���s�H�|�@�ۑ�w�E�����j�A�X�ь��ᎁ�i�����E���������E����C�������j�A�������l���i����w�E���C�����j�̂S���̍u�t�̕������������ĊJ�Â����B
1.�@�����Z����RI�r�[����p�����ő̓����`�E���g�U���ۂ̌����i����y�[�W )
���G�l���M�[�����팤���@�\�E�f���q���q�j�������@�������@�A�@�~�]
�@RI�r�[����p�������������ɂ��ẮA�G�L�]�`�b�N�r�[���V���[�Y�̑�2��ŋ��s��w���q�F�������̐쐣�����ɂ��u�������肢�������A����̂��u���͂���ƊW�̐[�����̂ł������B�쐣�����̍u���͒Z����RI�����s��w���q�F�Ő��������ꍇ�ł��������A����͉�����𗘗p��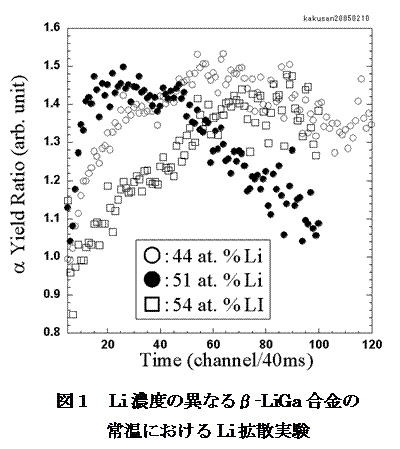 ���Z����RI�r�[���̐����Ƃ��̉��p�ɂ��čŋ߂̌�������Љ���������B���G�l���M�[�����@�\�E�f���q���q�j�������ƌ����i���F���{���q�͌����J���@�\�j�E���C�������Ƃ͋����Ō����E���C�������ɐݒu����Ă���^���f��������{�݂ɒZ�����j�r�[�������������u�iTRIAC: Tokai Radioactive Ion
Accelerator Complex�j�����ݒ��ŁA���݂��̈���H�����I�����āA�ŏI�I�Ȓ����i�K�ɂ���B�j�q������100keV����1MeV�̒Z�����j�r�[���������̃G�l���M�[����\�œ����AU��W�I�Ƃ����ꍇ�ɂ�Fe����Tb�܂ł̌��q��105/s���x�̊����ō��i���̃r�[���Ƃ��Ď��o����B���̑��u�̋������p���܂��Ȃ��J�n�����Ƃ̂��Ƃł������B�߂�������2���v��ł͒��`�����j�A�b�N�Ƒg�ݍ��킹�Ċj�q������5MeV�ȏ�܂ʼn����\�ł��������i���̃r�[����ڎw���Ă���B
���Z����RI�r�[���̐����Ƃ��̉��p�ɂ��čŋ߂̌�������Љ���������B���G�l���M�[�����@�\�E�f���q���q�j�������ƌ����i���F���{���q�͌����J���@�\�j�E���C�������Ƃ͋����Ō����E���C�������ɐݒu����Ă���^���f��������{�݂ɒZ�����j�r�[�������������u�iTRIAC: Tokai Radioactive Ion
Accelerator Complex�j�����ݒ��ŁA���݂��̈���H�����I�����āA�ŏI�I�Ȓ����i�K�ɂ���B�j�q������100keV����1MeV�̒Z�����j�r�[���������̃G�l���M�[����\�œ����AU��W�I�Ƃ����ꍇ�ɂ�Fe����Tb�܂ł̌��q��105/s���x�̊����ō��i���̃r�[���Ƃ��Ď��o����B���̑��u�̋������p���܂��Ȃ��J�n�����Ƃ̂��Ƃł������B�߂�������2���v��ł͒��`�����j�A�b�N�Ƒg�ݍ��킹�Ċj�q������5MeV�ȏ�܂ʼn����\�ł��������i���̃r�[����ڎw���Ă���B
���̑��u�̉��p�̈��Ƃ��ĒZ�����j8Li���g���[�T�Ƃ���ő̓��g�U�̎������s�����B�]���̃g���[�T�g�U�����ł͒�����RI�������\�ʂɃR�[�e�B���O��A�M���������������o���Ă��̕��˔\�𑪒肷���@����ʓI�ł������B���������Ē������̓K����RI�����݂��Ȃ�Li�̂悤�ȏꍇ�ɂ͓K�p�ł��Ȃ��̂ɑ��āA�{�����ł͔�j��Ŋg�U���肪�\�ł���B���̌����ł͌����^���f�������킩��7Li�r�[����9Be�W�I�ɓ��˂��ē�����8Li�i������0.84���j�̃G�l���M�[�����Ď����ւ̑ō��ݐ[���𐧌䂷��B8Li�̓�����8Be�̑���N��ԂƂȂ蒼����2�̃����q�ɕ���̂ŁA�����q�̋��x�̎��ԕω��𑪒肷�邱�Ƃɂ��A8Li�̎��Ԗ��x�ω������߂Ċg�U�W�������肷��B��-LiAl�͏퉷�ł�Li�C�I���g�U���������Ƃ���Li�C�I���d�r�̓d�ɍޗ��Ƃ��Ē��ڂ���Ă��������ł���B���̌n�̋����ԉ������iLiAl,LiGa,LiIn�j�͉����NaTl�\���������A���w�ʘ_�g���𒆐S�ɂ��āALi���q��E��������ȃ������`�����Ă���BLiAl�����ł�Li���q��EVLi�AAl�ʒu��Li���q����߂��u���^�i�q����LiAl����т�����2��ނ̌��ׂ�����������������VLi-LiAl��3��ނ̊i�q���ׂ����݂��Ă���A�����̌��ׂ�Li�̊g�U�ƊW���Ă��邱�Ƃ�����Ă���B����A���m��̃�-LiGa�̎����ł͒P���E�ɂ��Li�g�U�ɔ�ׂĕ������𑽂ׂ��܂ލ��������̏ꍇ��Li�g�U�̑������Ƃ����炩�ƂȂ����B
���̎�@�͏]���@�ł͕s�\�ł������n�ł̊g�U�������������ቷ��܂ʼn\�Ƃ���_�ʼn���I�ł��邪�A��^���u��K�v�Ƃ���̂ł���Ȃ錤���Ώۂ��L���Ă����K�v������Ƃ̋�����ۂ����B
2.�@�����C�I���r�[���A���ˌ���p�������q���q�����̐��E�i����y�[�W )
���s�H�|�@�ۑ�w�E�H�|�w���E�����H�w�ȁ@���� ��ʁ@��
�@�P�Ƃ̌��q�͗z�q���Ɠd�q�����������d�C�I�ɒ����ł���B���̌��q����d�q����邱�Ƃɂ��A�C�I�����������邪�A�����̓d�q�����Ή�����2���ȏ�̑����C�I���ƂȂ�B�����C�I����1920�N��ɐ^����d�Ō`�����ꂽ�v���Y�}���ɒ���Sn���q����20�ȏ�̓d�q���������ꂽ�����̃C�I�������݂��邱�Ƃ������������Ƃ��ŏ��ł���B�����͑����C�I���Ƃ����͓̂���ȏ�ɂ̂ݑ��݂���ƍl�����Ă������A�����C�I���̕����w�I�f�[�^���~�ς�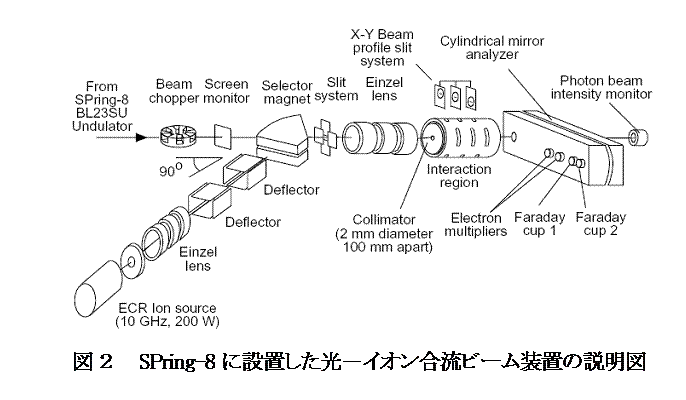 ��Ă����ɂ�A���z�R���i�Ŋώ@�����X�y�N�g����Ca�AFe�ANi�̑����C�I���̑J�ڂ��܂܂�邱�Ƃ���������āA���R�E�ɂ����݂��Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B���̌ネ�P�b�g��F���q���𗘗p�����F����Ԃł̒Z�g���X�y�N�g�����̊ϑ��ɂ�葽���C�I���̌������}���ɔ��W�����B�����C�I���͊j�Z���v���Y�}���ł��d�v�Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃ��m���A�����̏Փˉߒ��A�Č����A��N�E�d���A�d�ړ��Ȃǂ̌������L���s���Ă����B���݂ł͎������n�ɂ����ėl�X�ȑ����C�I�������J������A�g�|�C�I������t92+�C�I���Ɏ��鑽���̃C�I���킪�����o����悤�ɂȂ�A��b���牞�p�ɂ킽��Ȋw�E�Z�p�̓���Ƃ��Č����E�J���ɗ��p�����悤�ɂȂ��Ă���B
��Ă����ɂ�A���z�R���i�Ŋώ@�����X�y�N�g����Ca�AFe�ANi�̑����C�I���̑J�ڂ��܂܂�邱�Ƃ���������āA���R�E�ɂ����݂��Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B���̌ネ�P�b�g��F���q���𗘗p�����F����Ԃł̒Z�g���X�y�N�g�����̊ϑ��ɂ�葽���C�I���̌������}���ɔ��W�����B�����C�I���͊j�Z���v���Y�}���ł��d�v�Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃ��m���A�����̏Փˉߒ��A�Č����A��N�E�d���A�d�ړ��Ȃǂ̌������L���s���Ă����B���݂ł͎������n�ɂ����ėl�X�ȑ����C�I�������J������A�g�|�C�I������t92+�C�I���Ɏ��鑽���̃C�I���킪�����o����悤�ɂȂ�A��b���牞�p�ɂ킽��Ȋw�E�Z�p�̓���Ƃ��Č����E�J���ɗ��p�����悤�ɂȂ��Ă���B
�F����Ԃɂ����鑽���C�I���̐����ɂ͌��i���O���A�w���j�̋z���ɂ����̂ƁA�d�q�A�C�I���A���q�Ȃǂ̏Փ˂ɂ����̂Ƃ�2��ނ����邪�A�����̏ꍇ�͌��z���ɂ����̂ł���B����ɑ��Ēn��ł̃v���Y�}�����ɂ͕��d�ɂ��d��ʼn������ꂽ�d�q�̏Փ˂����p����Ă���B�������q�̌��d���̌����͈ȑO���瑽���Ȃ���Ă��邪�A���q�C�I���������ł�����x�ɏW�߂悤�Ƃ���ƃN�[�����˗͂Ŕ�юU���Ă��܂����߁A���d���̎����͊i�i�ɍ���ƂȂ�B���̂��ߑ����C�I���r�[�������A�����Ɍ����Ǝ˂���Ƃ�����@���l����ꂽ���A���̏ꍇ�ł��C�I���̕W�I���x�͒������q�ɔ䂵��6�`7�����Ⴂ���x���������Ȃ��B��������P���邽�߂Ɍ��̃r�[���ƃC�I���r�[���̌����𑵂��ďd�ˍ��킹�đ��点�A�Փˋ@���������u�����r�[���@�v���J�����ꂽ�B
��ʍu�t���SPring-8�ɐ}�Ɏ����悤�Ȍ��|�C�I�������r�[���������u��ݒu���āA�����C�I���̌��z���ߒ����n���I�ɒ��ׁA�����C�I���̊���ԁA��N��Ԃ̓d�q�\���⍂��N�����C�I���̒E��N�ߒ��Ȃǂ̒m���悤�Ƃ����B���̑��u��ECR�C�I�����A�W�I�C�I���̉��������߂邽�߂�90�x�Z�N�^�[�d���A���ƕW�I�C�I�������������鑊�ݍ�p�̈�A�����Ō��d���ߒ��ɂ�萶�����������C�I���͂���2�d�����^�Ód�A�i���C�U�[����\������Ă���B���ݍ�p�̈�Ƀl�I����_�f�K�X�����ĕ�����̃G�l���M�[�Z�����s�������ʁA540eV�ɂ����ā}0.5eV�ł������BO+�C�I���̎����ł�O+�̊���ԁi1��22��22��3�j�͌��̋��z���ɂ���N���O+�i1s2s22p4�j�ƂȂ�A���̗�N��Ԃ���Auger�ߒ��ɘa�ɂ��O2+�̊���ԁi1��22��22��2�j�ƂȂ�ƍl����ꂽ�B����ɓ��j�n��Ne+�ANe2+�ANe3+�C�I���̓��j��N���d���ߒ��ⓙ�d�q�n��Ne3+�AO+�C�I���̓��j��N���d���ߒ��ɂ��Ă����炩�Ƃ����B�܂��A�����C�I���̕����Ƃ̑��ݍ�p�̌����Ƃ��Ă͍��������C�I�����Y�f�����߂���ۂ́A�C�I���̓d�q��Ԃɂ��Ē������A�o�ˉדd���z�̖����ˑ����A���˃C�I���̃G�l���M�[�A�דd�ˑ����Ȃǂɂ��Ă����炩�ɂ��Ă����B
3.�@�����x���[�U�[�쓮���ː����̌���ƓW�]�i����y�[�W )
���{���q�͌��������������E���ʎq�Ȋw�����Z���^�[
���ʎq�V�~�����[�V���������O���[�v �X�с@����
�ߔN�A�����x�̃t�F���g�b���[�U�[���ő̕\�ʂȂǂɏƎ˂��邱�Ƃɂ��AX���A�����d�q�A�����C�I���Ȃǂ̗ʎq�r�[����������悤�ɂȂ����B�����E�����������ʎq�Ȋw�����Z���^�[�ł̓t�F���g�b�p���X��PW�i1015W�j���̃s�[�N��L����Z�p���X�����x���[�U�[�̊J�����s���A����ɂ�����ő̕\�ʂȂǂɏƎ˂��ē�����X���A�����d�q�A�����C�I���̕��ː��̊J���y�ї��p������i�߂Ă���B
 �X�є��m�͂܂����ʎq�Ȋw�Z���^�[�̑S�̑��ɂ��ďЉ�ꂽ�B�����E���������͕���7�N10���ɐݒu����A���ʎq�Ȋw�Z���^�[�̂���ؒÒn��̎{�݂͕���11�N6���ɏv�H�����B����ɔ������n��̑�w�̌����҂̏Ǝˎ����ɒ��N�ɘj���ċ�����Ă��������E�Q���쌤�����͕���13�N�x�ł��̖������낵���B���q�͌������͕���17�N10���Ɋj�R���T�C�N���J���@�\�Ɠ������ē��{���q�͌����J���@�\�Ƃ��ďo������\��ɂȂ��Ă��邪�A���̌������͌��ʎq�E���ˌ��A�����q�A�דd���q�ERI�̕��ː����p�Z�p�̍��x����ڎw���������J����ʂ��Č��q�͗��p�̐V���ȗ̈���J�A�Ȋw�Z�p����̔��W�ƎY�Ɗ����̑��i�ɂ�荑�������̎��̌����ڎw�����Ƃ�ڕW�Ɍf���Ă���B���ݍs���Ă��錤���́i1�j���ʎq���̊J���Ɓi2�j���ʎq���p�����ɑ�ʂ����B�i1�j�̐��ʂƂ��Ă͏��^�Ő��E�ō��o��850TW�i�p���X��33fs�j�̋ɒZ�p���X�����x���[�U�̊J���ɐ������AX�����[�U�Ƃ���8.8nm�܂ł̒Z�g���������������B�܂����p�����Ƃ��čŋߑ傫�Ȓ��ڂ𗁂тĂ���d���q���K�����×p���u�̏��^���A��R�X�g����ڎw���ď��^�̗z�q�E�d�C�I���V���N���g�����̂��߂̃��[�U�C�I�����̊J����S�����Ă����B�i�m�e�N����ł͋��U�d��BaTiO3�̑��]�ړ_122��C�ߖT�ł̕\�ʔ��\���̕ω����s�R�b�ő����A�����Cs���q�̋ߐڏ��ʂւ�2���q��N�ƌu������ɂ���Ċe���ʂւ̗�N�m���̑���ɐ��������B���̎�@�͋M�d������댯�����̑I�𒊏o��n��Ȃǂ̐V�Z�p�ɂȂ���Ǝv����B
�X�є��m�͂܂����ʎq�Ȋw�Z���^�[�̑S�̑��ɂ��ďЉ�ꂽ�B�����E���������͕���7�N10���ɐݒu����A���ʎq�Ȋw�Z���^�[�̂���ؒÒn��̎{�݂͕���11�N6���ɏv�H�����B����ɔ������n��̑�w�̌����҂̏Ǝˎ����ɒ��N�ɘj���ċ�����Ă��������E�Q���쌤�����͕���13�N�x�ł��̖������낵���B���q�͌������͕���17�N10���Ɋj�R���T�C�N���J���@�\�Ɠ������ē��{���q�͌����J���@�\�Ƃ��ďo������\��ɂȂ��Ă��邪�A���̌������͌��ʎq�E���ˌ��A�����q�A�דd���q�ERI�̕��ː����p�Z�p�̍��x����ڎw���������J����ʂ��Č��q�͗��p�̐V���ȗ̈���J�A�Ȋw�Z�p����̔��W�ƎY�Ɗ����̑��i�ɂ�荑�������̎��̌����ڎw�����Ƃ�ڕW�Ɍf���Ă���B���ݍs���Ă��錤���́i1�j���ʎq���̊J���Ɓi2�j���ʎq���p�����ɑ�ʂ����B�i1�j�̐��ʂƂ��Ă͏��^�Ő��E�ō��o��850TW�i�p���X��33fs�j�̋ɒZ�p���X�����x���[�U�̊J���ɐ������AX�����[�U�Ƃ���8.8nm�܂ł̒Z�g���������������B�܂����p�����Ƃ��čŋߑ傫�Ȓ��ڂ𗁂тĂ���d���q���K�����×p���u�̏��^���A��R�X�g����ڎw���ď��^�̗z�q�E�d�C�I���V���N���g�����̂��߂̃��[�U�C�I�����̊J����S�����Ă����B�i�m�e�N����ł͋��U�d��BaTiO3�̑��]�ړ_122��C�ߖT�ł̕\�ʔ��\���̕ω����s�R�b�ő����A�����Cs���q�̋ߐڏ��ʂւ�2���q��N�ƌu������ɂ���Ċe���ʂւ̗�N�m���̑���ɐ��������B���̎�@�͋M�d������댯�����̑I�𒊏o��n��Ȃǂ̐V�Z�p�ɂȂ���Ǝv����B
�����Ă����g������Ă����鍂���x�Z�p���XX�����ɏƎ˂����ۂɐ����鑽�d���k��N�̃V�~�����[�V�����ɂ��ču�����ꂽ�B�p���X���̓t�F���g�b����A�g�b�p���X�̎���ɓ����Ă����B�A�g�b�p���X�̐����@�͈ȑO������Ă������A���肪�\�ɂȂ����̂�21���I�ɓ����Ă���̂��ƂƂ̂��Ƃł���B�ÓT�I�Ȑ��f���q���ɂƂ�Ɠd�q�����q�j�̂܂������鎞�Ԃ�150�A�g�b�ł���A���ݎ�������Ă���p���X��250�A�g�b�ł���B�Z�p���X���[�U�̍����x���i��1020W/cm2�j�̔��W�ɔ����āA�����x�Z�p���XX���̒Z�g�������\�ƂȂ�A�i1�j���̂ɂ����钴�����ߒ��̊ϑ��A�i2�j���ː��ɂ��DNA�����E�C���ߒ��̎��ԕ��𑪒�A�i3�j���k�t�H�g���~�l�b�Z���X�̎��ԕ��𑪒�A(4)�����x���E��Ԃ̌`���ɂ�锼���̂Ȃǂ̌��q���q����A�i5�j���d���v���Y�}�̖͋[�����Ȃǂ̌����֑傫�Ȋ�^�����邱�Ƃ����҂���Ă���B�u���ł͓���Si�̏ꍇ�ɂ��āA���k��N��ԁA���d���k��N��Ԑ����Ƃ���ɊW����X�������ߒ������グ��ꂽ�B
�Z�p���XX�����̔��W�ɂ�萶�́E�ő̂̌��q�E���q���x���̗l�X�Ȕ����ߒ�����A�F���ɂ�����v���Y�}�̔����ߒ��ɂ�����L�͈̗͂̈�ł̑f�ߒ������炩�ɂȂ��Ă����傫�Ȋ��҂�������Ă���B
4.�@�d���f�E���f���܂ދÏW�n�̊j�����|�퉷�j�Z����������16�N���o�߂��ā|�i����y�[�W )
����w���C�����@�����@���l
�@1989�N����1990�N��ɂ����Đ��E���̌����҂̒��ڂ����т������Ɂu�퉷�j�Z���v������B�����̌����҂ɂ���Ēǎ����s���A�吨�Ƃ��Ģ�퉷�j�Z����͔ے肳�ꂽ���A���̌���ˑR�Ƃ��Č����𑱂��Ă���O���[�v������B����͍ŏ��̕���16�N���o�߂������݂ł��A�����̉ߒ��ɂ����Ĕے肵�������ُ픽�����������ʂ���X������ꍇ������A�����̑������قȂ錤���҂̌��ʂɂ����Ē萫�I�Ɉ�v���邩��ł���B�������m�����N�ɂ킽���Ă��̕���̑��l�҂Ƃ��Č������p�����Ă���ꂽ�B�������m�ɂ��A�ߔN�̎������ʂ͏퉷�̏d���f�E�y���f���܂ދÏW�n�ŁA�퉷�j�Z���Ƃ͈قȂ�i1�j�N���[���Ȋj�Z���A�i2�j�N���[���Ȋj�ϊ������炩�ɐ����Ă��邱�Ƃ������Ă���A�ÏW�̕����i�ő̕����j�̗��ꂩ��V�K�̊j�����ߒ����l�@����K�v��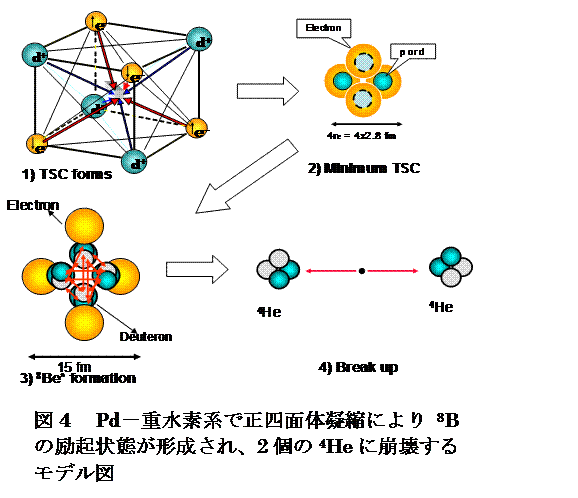 ���������Ă���B
������������B
�퉷�j�Z���̔��[��1989�N��Fleischmann-Pons�ɂ��Pd�d�ɂ��g�p�����d���d�C���������ʼnߏ�M���ώ@�����Ƃ������̂ł��������A���̌�A�K�X�A�v���Y�}�A�r�[���A���[�U�A�����g�Ȃǂ̔����⏕��i�ƃi�m�\���̋����E���f�i�d���f�j������p�����l�X�Ȏ��������݂��Ă����B�����̌��ʂŏd�v�Ȃ��̂�d-d�����̌��ʁA4He�̐����Ɖߏ�M�̔�������Ƃ������̂ł���A�����̌����҂ɂ���ĕ���Ă���B2002�N�ɂȂ��ĎO�H�d�H���̊⑺��̓i�m���H����Pd���w���̕\�ʂ�Cs��Sr�����āAD2��H2�K�X�߂�����������s�����Ƃ���AD2�K�X�̏ꍇ�ɂ̂݁ACs��Pr�ASr��Mo�̊j�ϊ������������Ƃ�����B���̌��ʂ͍��Ȃǂ̒ǎ��ɂ���Ă��m�F����A���q�͔��d�ɂ����钷�������p���������ł�����Z�p�ɂȂ���ƒ��ڂ���Ă���B�������Ȃ���A�ő̕����n�ɂ����Ēm���Ă��锽���ߒ��ł�4He���吶�����Ƃ���j�Z���⌴�q�ԍ��̑傫�ȋ������q�j�̊j�ϊ��Ȃǂ͓�������ł��Ȃ��B
�����u�t�͂��̃��f���Ƃ��Đ��l�ʑ̋Ïk�iTSC�FTetrahedral Symmetry Condensation�j���f��������B���̃��f���ł͏d���f4�Ɠd�q4���l�ʑ̑Ώ̂�ۂ��Ȃ���A��_�Ƀ{�[�Y�Ïk����Ƃ��Ă���B���̌��ʂƂ��Ă܂���N��Ԃɂ���8Be*���`������A���ꂪ2��4He�ɕ���Ƃ������̂ł���B���̃��f���ł�TSC�͓d�ׂ�������10fm�̍ŏ����a�̋[�����q�Ƃ��Ď�舵���Ă������������q�̂悤�Ƀz�X�g�������q�̓d�q�_�������ʂ��āA���q�j�ƒ��ڔ������\�ɂȂ�Ƃ��Ă���B���̃A�C�f�B�A�ł͊⑺��̊j�ϊ��������\�Ƃ̂��Ƃł���B
�������Ȃ���A�����u�t�����g���R�����g���ꂽ�悤�ɁA�������_�Ǝ������ʂ͂��Ȃ�����т�����v����������̗̂��_�͂܂������I�ł���A�X�Ȃ錵���Ȏ�舵���Ƃ�萸�k�Ȏ����I��@�ɂ��𖾁E�������K�v�Ɗ������B
�G�L�]�`�b�N�r�[���V���[�Y����3��ƂȂ�A����͓��e�I�ɂ��Ȃ荂�x�ŁA���������x�̔Z�����̂ł������B�����̎Q���҂������ł������Ƃ̂��ӌ������̂ŁA�����ǂƂ��Ă͊e�u�t�̐搶���ɂ�蕽�Ղɂ��b���Ă��������悤���肢�����ׂ��ł������Ɣ��Ȃ��Ă���B�������Ȃ���u�t�̕��ɂ͌�����̌�A���e��ɂ����c�肢�������A���ł͎���o���Ȃ������ׂ��������܂ŎQ���҂Ɛe�����c�_�����Ă����������B�Q�����Ă������������ɂ͗L�Ӌ`�ȓ��ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B
�@