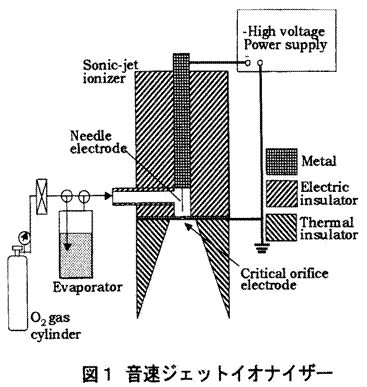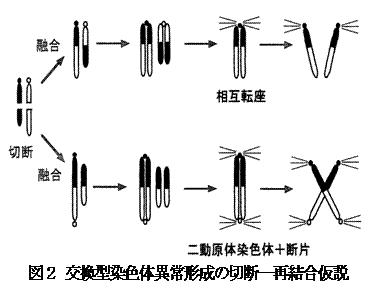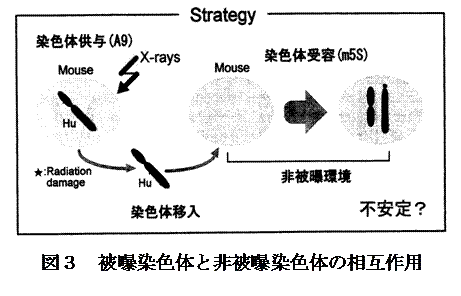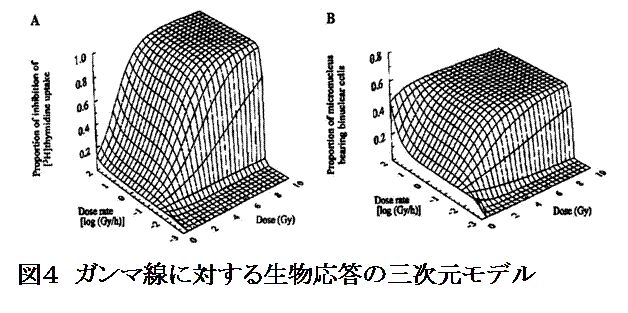|
||||
|
第23回放射線科学研究会聴講記 表記研究会は新年度間もない平成16年4月23日(金)14:00より、17:00まで住友クラブ(大阪市西区)で、3名の講師をお招きして開催した。今回の研究会においては最近何かと話題になっているマイナスイオンについての基本的な理解から発生装置、実際への応用までの広い範囲にわたって足立元明氏(大阪府立大学先端科学研究所基礎科学部門)にご講演をしていただいた後、放射線の生物学的影響に関して児玉靖司氏(大阪府立大学先端科学研究所放射線科学センター)、馬替純二氏(財団法人産業創造研究所生物工学研究部)、緒方裕光氏(国立保健医療科学院)に最新の話題についてご講演をお願いした。 1.マイナスイオンの発生と工学的応用(会員ページ ) 大阪府立大学先端科学研究所 足立元明 法令で規定されている放射線は直接あるいは間接的に電離作用を有する電磁波や粒子線であるから、放射線が空気に照射されると電離作用によって正イオンと負イオンが対となったいわゆる両極イオンが生成される。一方、放電場では放電極に印加される電圧によって空間に残留するイオンが決まる。負電圧の 足立氏らは上述の音速ジェットイオナイザーで水クラスターマイナスイオンを発生させ、酵母菌を撒いた培地にそれらを暴露させて、培養器中で培養効果に及ぼす影響を調べた。その結果、マイナスイオンによる殺菌効果が確実に観察されたが、それがマイナスイオン効果であると結論づけることには慎重であった。最近北大の研究者によってマイナスイオンが交感神経を安定化させる効能があるとの信頼すべき結果が得られていることも報告されたが、それらの機構については今後のさらなる研究が必要であるとの強い印象であった。 2.放射線によって誘発される遅延性の染色体異常(会員ページ ) 大阪府立大学先端科学研究所 児玉靖司 放射線の生物学的効果の典型的な例として細胞の染色体異常は良く知られている。この異常は放射線照射によるDNA鎖の切断とその修復過程に関係していることから、切断されたDNA末端が修復されない場合や誤った修復が行われた場合に染色体異常が発生するという「切断−再結合モデル」が広く知られている(図2)。しかしながら、最近になり放射線被曝後、長時間経過した場合においても、異常が生成される場合があることが明きらかとなった。このような遅延性の異常発生の生成機構については、これまではあまり議論されていない。児玉氏らは遅延性染色体異常の発生の原因を探るため、被曝したヒト染色体と被曝していないヒト染色体の一本をそれぞれ被曝していないマウス細胞と被曝したマウス細胞に移入して、ヒト染色体に異常が発現するかどうかを調査し、何れの場合においても異常が現れることを明きらかにした。図3は被曝させたヒト染色体を被曝していないマウス染色体に移入後に現れるヒト染色体異常の様子を示している。このことから、放射線被曝を受けた染色体にはなんらかの被曝の刻印がおされており、それと健全な染色体間に相互作用によって、その刻印が細胞分裂においても継承されていくため、染色体異常の頻度が増すと結論している。どの箇所に刻印がなされているかについて児玉氏らは染色体末端部(テロメア)に着目して研究を継続している。これらの実験は発ガン機構の本質の解明に迫る非常に重要な研究であるとの強い印象を受けた講演であった。
3.培養細胞を用いた低線量・低線量率放射線のリスク評価(会員ページ ) 財団法人産業創造研究所 馬替純二 馬替氏と緒方氏は低線量・低線量率放射線の照射を受けた場合のリスク評価について講演を行った。放射線防護の立場からは安全サイド側へ放射線による確率的生物影響はしきい値がなく、被曝総線量と単純に比例関係にあるという直線無閾値(LNT)仮説が採用されている。馬替氏らはこの仮説には二つの大きな問題があると考えている。一つはこの仮説は被曝総線量のみを考えており、線量率・照射時間という概念が欠落しているということである。地球上に生物が出現してから数10億年にわたって、生物は自然放射線の環境下で様々に進化をとげてきた。この過程で放射線被曝により切断されたDNAは分程度の時間内に修復され、一方では放射線照射によって生体に加えられたダメージによって生ずるストレスを緩和する蛋白質が生体内に誘導されることが知られている。このことは極めて低い線量率での放射線被曝では高い線量率での被曝の状況とは異なる事象となることを強く示唆している。さらなる問題点は今日、低線量あるいは低線量率での信頼すべき実験データが絶対的に不足していることである。 このような問題点を解決するために、馬替氏らは可能な限り広い範囲でデータを蓄積し、線量率と照射時間を包含した新規の統計モデルを構築することを志向した。氏の言葉を借りれば、「閾値は統計的な言葉を用いて、定量的に照射時間(線量率)の関数として表現すべき値」ということである。実験としては低線量率での実験では、その効果はバックグラウンドに埋没してしまうおそれがあるので、測定系として可能な限り単純で、かつ定量性に優れたものを選択する必要がある。試料としての細胞にはガン細胞ではあるが、正常細胞を反映した応答を示し、しかも増殖が速く性質の安定しているヒト骨肉腫U2OS細胞を用いて、ガンマ線の照射条件を系統的に変化させ、小核形成率と増殖阻害効果を調査した。実験結果を指数関数で近似したMOE(Modified exponential) モデルによってフィッティングしたものが図4である。このモデルでは対数を用いていることにより、限りなく小さな線量・線量率に対しても適用できる大きな特徴を有している。生物学的リスクは統計的な手法で検定され、5%以下の危険率で有意水準とされており、これによって閾線量・閾線量率を調べた結果、閾線量は照射時間と比例関係にあるが、閾線量率は照射時間が長くなると一定値に近づくことが示され、何らかの生物学的効果が関与することが示唆された。MOEモデルは照射時間と線量率との関数によって、リスクを定量的に評価できる点で極めて有用ではあるが、これはあくまでも培養細胞を用いたリスク評価であり、ヒトの発ガンのリスク評価とはまだ距離があることを馬替氏は強調された。
今回の研究会では日本保健物理学会が4月22,23日の両日神戸大学海事科学部(元神戸商船大学)で開催された関係で、日頃は距離的制約のためにご出席の困難な関東地区や西日本地区からかなりの方に参加をいただき、大変活発な研究会であった。何人かの方には交流会にも出席していただき、講師の方々と親しく議論をしていただけたことは極めて有意義であった。その上、東京地区にはこのようなすばらしい研究会はないとのお褒めの言葉を頂き、協会としては日頃の苦労も吹き飛ぶ一日であった。 (大嶋記) |
||||