(1)「3次元蛍光X線分析装置の開発とその応用研究」
辻 幸一氏
大阪市立大学大学院工学研究科・教授
今回の辻幸一氏の業績は大学の研究室レベルで、SPring-8のような大型施設にひけをとらないような三次元蛍光X線分析装置を開発したことである。
X線の応用としては、一般になじみのある医療用X線撮影や空港の手荷物検査のような内部構造の知見を得る手法と励起作用を利用した元素分布の可視化による化学分析が代表的である。元来、蛍光X線分析法(XRF)は、大気圧下(高真空を使用しない)で非破壊的(プローブによるダメージが少ない)に元素分析が可能であるというユニークな特徴を有する。これは、真空を要する電子線やイオンビームを励起プローブとする元素分析法に対しての利点である。検出感度を高める全反射条件を利用した全反射蛍光X線分析法(TXRF)も含めて、XRF法は半導体、プラスチック材料、鉄鋼材料などの工業材料だけでなく、土壌、エアロゾルといった環境試料、プランクトンや人・動物の臓器や毛髪、血液などの生物・医学試料、美術品や考古学試料、犯罪捜査試料などきわめて広い試料への適用例が報告されている。然しながら電磁レンズによってビームを絞ることが出来る荷電粒子線に対して、X線では適当な集光素子がなく微小領域での分析は電子線に比べて立ち遅れていた。近年になって極めて細いガラス管を数万本束ねたポリキャピラリーレンズが開発されX線でも10μm程度の集光が可能になってきた。この集光素子を利用すれば立体角の大きい発生X線のビームを微小領域に集光が可能であり、実験室レベルで高強度のビームが得られる。さらに発生側だけでなく検出側においても同様のレンズを使用し、両者の幾何学的配置を最適化し試料の移動機器と組み合わせることで3次元の情報を得ることが可能となる。この共焦点3次元X線分析法のアイディアは1993年に初めて発表されたが、実験が行われるようになったのは2000年以降であり、深さ方向の分析は2003年に報告された。講師の研究グループでは2008年に最初の手作りの装置を立ち上げた。当時のビームは30μmだったそうである。その後、数台の装置を研究室で試作しながら性能の向上につとめ、最近になり空間分解能15μmの世界トップクラスの性能を有する装置を完成させた。この装置の利点は微小試料片の三次元分析が可能であることである。例示として科捜研からの依頼による自動車事故現場から採取した塗膜片の分析、マイクロSDカードの多層構造の分析(図1)を挙げたが、その他興味ある応用として界面構造の化学分析がある。反応界面での元素分布の変化の追跡は雰囲気を問わずにすむX線が有利であろうと感じた。さらなる発展を期待したい。
(大嶋 記)

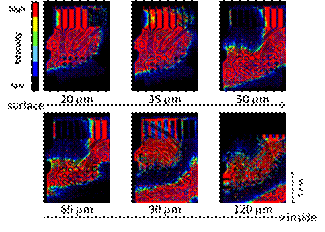
写真1 講演中の辻教授 図1 microSDカードの深さ方向での
Cu−X線強度変化