戞侾俆夞曻幩慄棙梡憤崌僔儞億僕僂儉挳島婰
奐嵜擔帪 暯惉侾俉擭侾寧俀俈擔丂応強 廧桭僋儔僽
侾丏僈僗僴僀僪儗乕僩傪弰傞嵟嬤偺榖戣-婎慴尋媶偐傜揤慠僈僗桝憲丒悈慺挋憼媄弍傑偱-
戝嶃戝妛戝妛堾婎慴岺妛尋媶壢丂戝奯
堦惉
嵟弶偺榖戣偼嵟嬤擱偊傞悈偲偟偰拲栚傪廤傔偰偄傞僈僗丄摿偵悈慺乮俫俀乯丄儊僞儞丄偦偟偰擇巁壔扽慺乮俠俷俀乯偺僴僀僪儗乕僩偱偡丅
傑偢丄僴僀僪儗乕僩偩偑丄偙傟偼壏搙丄埑椡偺偁傞忦審傪枮偨偣偽丄悈偑悈慺寢崌偵傛偭偰饽峔憿傪嶌傝丄偦偺拞偵偄傠偄傠側暘巕傪庢傝崬傓惈幙偑偁傞偲塢偆傕偺偱丄偦偺拞偱暘巕偼扨撈偱偄傞偺偲偼堘偭偨暔惈傪帵偟丄埨掕偵懚嵼偡傞偺偱丄偄傠偄傠側墳梡偑峫偊傜傟傞丅
 饽偺婎杮峔憿偼恾俀偺傛偆側傕偺偱丄嵟傕彫偝偄俽働乕僕偼惓俆妏宍偺侾俀柺懱丄悈暘巕偑俀侽儢偐傜側傞丅仜偱帵偟偨偲偙傠偑巁慺尨巕丄椗慄偺拞怱偵悈慺尨巕偑埵抲偟丄撪晹偵侽丏係値倣傎偳偺嬻娫偑偁傞丅偙傟偵榋妏宍偺柺偑擇偮壛傢偭偨侾係柺懱偺俵働乕僕丄偝傜偵丄傕偆擇偮壛傢偭偨侾俇柺懱偺俴働乕僕側偳偑偁傝丄幚嵺偵偼偙傟傜偑偄偔偮偐慻傒崌傢偝偭偨暋崌峔憿偱懚嵼偡傞偑丄偄偢傟偺峔憿傕廮傜偐偔丄揔摉側壏搙偲埑椡偑偁傟偽丄偄傠偄傠側暘巕偺擖偭偨忬懺傪梕堈偵嶌傟傞丅
饽偺婎杮峔憿偼恾俀偺傛偆側傕偺偱丄嵟傕彫偝偄俽働乕僕偼惓俆妏宍偺侾俀柺懱丄悈暘巕偑俀侽儢偐傜側傞丅仜偱帵偟偨偲偙傠偑巁慺尨巕丄椗慄偺拞怱偵悈慺尨巕偑埵抲偟丄撪晹偵侽丏係値倣傎偳偺嬻娫偑偁傞丅偙傟偵榋妏宍偺柺偑擇偮壛傢偭偨侾係柺懱偺俵働乕僕丄偝傜偵丄傕偆擇偮壛傢偭偨侾俇柺懱偺俴働乕僕側偳偑偁傝丄幚嵺偵偼偙傟傜偑偄偔偮偐慻傒崌傢偝偭偨暋崌峔憿偱懚嵼偡傞偑丄偄偢傟偺峔憿傕廮傜偐偔丄揔摉側壏搙偲埑椡偑偁傟偽丄偄傠偄傠側暘巕偺擖偭偨忬懺傪梕堈偵嶌傟傞丅
僈僗僴僀僪儗乕僩偺懚嵼忬懺傪尒傞幚尡椺偲偟偰丄俽偲俵偐傜惉傞偁傞暋崌偺饽峔憿偵丄偁傜偐偠傔堦掕妱崌偺儊僞儞偲僄僠儗儞偺崿崌暔傪擖傟偰偍偒丄儔儅儞僗儁僋僩儖偱娤嶡偟側偑傜僄僠儗儞傪壛偊偰峴偔偲丄僄僠儗儞偑俵働乕僕偱憹壛偟丄偦傟偵偮傟偰儊僞儞偺俽働乕僕偱偺暘晍偑憹壛偟偰備偔條巕偑尒傜傟傞丅僄僠儗儞偺戙傢傝偵傕偆彮偟戝偒側暘巕偺僔僋儘僾儘僷儞傪巊梡偡傞偲丄偦偺憹壛搑拞偵丄撍慠丄饽偺暋崌峔憿偑暿偺峔憿偵揮壔偡傞憡揮堏尰徾傕尒傜傟傞丅
嵟嬤偱偼傛傝戝偒側婎杮峔憿傕敪尒偝傟偰偄傞偑丄偦傟傜偐傜峔惉偝傟傞暋崌峔憿偺僞僀僾偼偐側傝惍棟偝傟偰偄傞丅柺敀偄尰徾偲偟偰丄僔僋儘僆僋僞儞偺傛偆側戝偒側暘巕偑丄僛僲儞乮倃倕乯傗儊僞儞偺傛偆側彫偝側暘巕傪俽働乕僕偵擖傟傞偙偲偱丄傛傝戝偒側饽偵擖傝丄僴僀僪儗乕僩傪宍惉弌棃傞偙偲偑偁傞丅偟偨偑偭偰丄偙偙偱偼丄偳偙傑偱戝偒側暘巕偑擖傟傞偐偑丄暋崌峔憿偲娭學偟偰堦偮偺嫽枴偁傞尋媶懳徾偲側傞偑丄堦曽丄摨帪偵儊僞儞傪媗傔傞偨傔偺埑椡偑悢廫婥埑傕掅壓偡傞帠幚偑敽偆偨傔丄偙傟傪儊僞儞偺挋憼偵棙梡偡傞壜擻惈偑偁偭偰丄偦偺柺偐傜傕丄桳梡側尋媶懳徾偲側偭偰偄傞丅
儊僞儞僴僀僪儗乕僩偵偮偄偰偼丄壏搙偑掅偄傎偳丄掅偄埑椡偱埨掕偵懚嵼偟摼傞偙偲傪昞偡丄偄傢備傞憡恾偑昤偐傟傞偑丄亅俀侽亷晅嬤偵偦偺嬋慄偐傜戝偒偔棧傟偰丄戝婥埑偱庻柦偺塱偄丄傑偩棟桼偑枹夝柧側摿堎椞堟偑偁傞丅偙偺曈傝偺栤戣偑棟夝偝傟傟偽塼懱拏慺壏搙偱揤慠僈僗偺桝憲偑壜擻偲側傝丄拞彫偺僈僗揷偱傕儁僀偡傞僔僗僥儉偑嶌傟傞偲峫偊傜傟偰偄傞丅
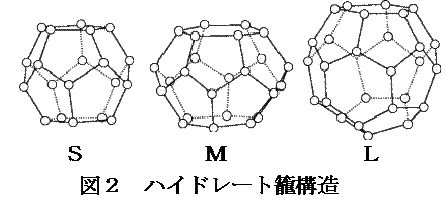 僴僀僪儗乕僩忋偱俠俷俀偲俫俀僈僗傪嫟懚偝偣傞帪丄俫俀偺妱崌偼侾侽侽婥埑偱俇侽%掱搙偱偁傞偑丄偙偙偵娐忬僄乕僥儖偺俿俫俥偲尵偆暔幙傪悈偺俆%掱搙壛偊傞偲侾侽乣俀侽婥埑偱俉侽僷乕僙儞僩傪挻偡偙偲偑弌棃傞丅
俠俷俀偑側偔偰傕俉侽婥埑側傜摨偠掱搙偺擹搙偑摼傜傟傞丅偨偩丄偙偺掱搙偱偼丄儌儖悢偵偡傞偲悈慺媧憼崌嬥偲彑晧偵側傜側偄偑丄棟榑揑偵偼俽働乕僕摉偨傝俀暘巕擖傞傋偒偲偙傠偑傑偩侾暘巕偱丄偟偐傕丄偦偺俀侽亾偵偟偐夁偓側偄偺偱丄椺偊偽傾儈儞側偳丄揧壛暔傪峀偔扵嶕偡傟偽夵慞偺梋抧偑婜懸偝傟傞丅
僴僀僪儗乕僩忋偱俠俷俀偲俫俀僈僗傪嫟懚偝偣傞帪丄俫俀偺妱崌偼侾侽侽婥埑偱俇侽%掱搙偱偁傞偑丄偙偙偵娐忬僄乕僥儖偺俿俫俥偲尵偆暔幙傪悈偺俆%掱搙壛偊傞偲侾侽乣俀侽婥埑偱俉侽僷乕僙儞僩傪挻偡偙偲偑弌棃傞丅
俠俷俀偑側偔偰傕俉侽婥埑側傜摨偠掱搙偺擹搙偑摼傜傟傞丅偨偩丄偙偺掱搙偱偼丄儌儖悢偵偡傞偲悈慺媧憼崌嬥偲彑晧偵側傜側偄偑丄棟榑揑偵偼俽働乕僕摉偨傝俀暘巕擖傞傋偒偲偙傠偑傑偩侾暘巕偱丄偟偐傕丄偦偺俀侽亾偵偟偐夁偓側偄偺偱丄椺偊偽傾儈儞側偳丄揧壛暔傪峀偔扵嶕偡傟偽夵慞偺梋抧偑婜懸偝傟傞丅
嵟屻偵曻幩慄棙梡偺揰偐傜丄榖戣傪採嫙偡傞偲丄僴僀僪儗乕僩偵徠幩偟偰惗惉偡傞儔僕僇儖偺庻柦偼旕忢偵挿偔丄饽偑惗懚偡傞尷傝惗懚偡傞偲偄偆偙偲偑暘偐偭偨丅偙偺惈幙傪棙梡偡傟偽丄堦偮堦偮偺儔僕僇儖傪惂屼偟側偑傜丄塅拡嬻娫偱偺桳婡暔惗惉偺撲偵敆傟傞偲婜懸偝傟傞丅傑偨丄偙偺挿庻柦儔僕僇儖偺暘夝懍搙傪夝愅偡傞偲亅俀侽亷晅嬤偱妶惈壔僄僱儖僊乕偑曄壔偟丄偦傟偧傟丄昘偲僈僗偍傛傃夁椻媝偺悈偲僈僗偵暘夝偡傞抣偲堦抳偡傞偺偱丄偙偺曈傝偐傜僴僀僪儗乕僩偺堎忢側埨掕揰傊偺夞摎偑摼傜傟偦偆偩丅
偙傟傜偺媄弍偺愭偵偼僀儞僩儘僟僋僔儑儞偱徯夘偝傟偨傛偆偵丄悈慺僈僗偺桝憲傗怺奀掙傊偺俠俷俀挋憼庤抜偲偟偰偺妶梡偑偁傝丄偝傜偵偼儊僞儞僴僀僪儗乕僩憌偵娐嫬栤戣偺俠俷俀傪憲傝崬傫偱儊僞儞傪庢傝弌偡偲尵偆憇戝側柌傕偁偭偰妝偟傒偱偡丅
俀丏嬤峕偺屆戙惢揝偵偮偄偰
俶俥俠僙儞僞乕屭栤丂揷晹丂慞堦
廧桭寉嬥懏偱摵傗傾儖儈偺晠怚傪挿擭尋媶偝傟丄戅怑屻偵丄嬤峕偺惢揝堚愓傪挷傋偰偍傜傟傞揷晹愭惗偵丄揝偲擔杮楌巎偺曄慗偼壢妛偲楌巎偺岎揰丄偲傕尵偊傞嫽枴怺偄榖傪偟偰捀偄偨丅
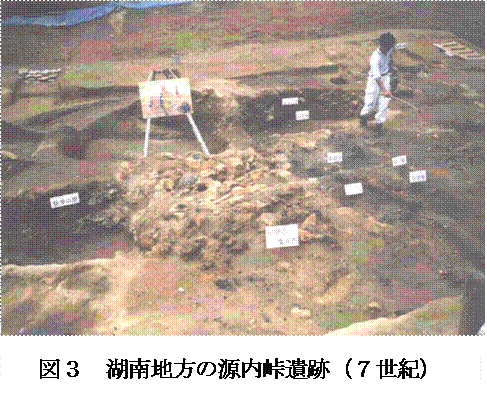 暥柧偵偼嘆晉偺曃嵼丄嘇暥帤偺惉棫嘊嬥懏偺巊梡偲尵偆嶰偮偺忦審偑昁梫偱偁傞偲尵傢傟傞丅偮傑傝丄嘆偵傛偭偰旕惗嶻幰奒媺偑敪惗偟嘇偵傛偭偰惌懱偑惍偄丄嘊偱愴偄傪惂偡傞偙偲偱殸偑惉棫偡傞丅偦偙偐傜暥柧偑巒傑傞偺偱偁傞丅
暥柧偵偼嘆晉偺曃嵼丄嘇暥帤偺惉棫嘊嬥懏偺巊梡偲尵偆嶰偮偺忦審偑昁梫偱偁傞偲尵傢傟傞丅偮傑傝丄嘆偵傛偭偰旕惗嶻幰奒媺偑敪惗偟嘇偵傛偭偰惌懱偑惍偄丄嘊偱愴偄傪惂偡傞偙偲偱殸偑惉棫偡傞丅偦偙偐傜暥柧偑巒傑傞偺偱偁傞丅
揝偼丄屆偔偼俛俠侾俆侽侽乣俀侽侽侽擭偵僸僢僞僀僩偑丄摉帪傾僫僩儕傾抧曽偱惙傫偩偭偨棸壔摵偐傜偺摵偺惢楤帪偵嬼慠尒偮偗偨偲偄傢傟偰偄傞丅偮傑傝丄 俠倳俽偲俥倕俷偺娨尦揹埵偑斾妑揑嬤偄偙偲偐傜丄惛楤梡偵僿儅僞僀僩傪壛偊偨帪偵揝偑惗偠偨偺偱偁傠偆偲尵偆丅嶰悽婭偺弶傔偺幾攏戜崙偵怗傟偨榘巙榒恖揱偵偼揝偺婰弎偑側偄偑丄摨悽婭偺屻婜丄俙俢俀俉俋擭崰丄嶰崙巙榘彂偺搶埼揱偵丄挬慛敿搰偺曎扖乮屻偺擟撨乯抧曽偵揝傪嵦傝偵峴偭偰偄偨傜偟偄婰弎偑偁傞丅
係悽婭丄尰嵼戝庤慜戝妛偑敪孈拞偺暷尨偵偁傞掕擺堚愓偱敪尒偝傟偨娀偺撪懁偱偼丄摢晹偑庨偱懌晹偑巁壔揝偺儀儞僈儔偑巊傢傟偰偄傞丅偙偺巁壔揝傪巊偭偰揝傪嶌偭偨偺偼扤偐丅偦傟偼俆悽婭偵戝嶃暯栰偺忋挰戜抧偵嫃傪抲偒昐愩屆暛孮傪偮偔傝丄廧擵峕傗摉帪偁偭偨壨撪屛偵峘傪嶌偭偰妶摦偟偨榒偺屲墹偺帪戙偲峫偊傜傟傞丅梇棯偲偝傟傞屲墹嵟屻偺晲偑乽愄傛傝慶擧鏩傜峛檋傪娧偒丆嶳愳傪骐徛偟偰丆擩強偵纭偁傜偢乿偺桳柤側嬪偱愭戙傗愭乆戙偑檋傗奪傪拝偰暯掕偵曕偄偨偙偲傪婰偟偰偍傝丄偦偺帪偺晲婍傪嶌偭偨偺偑妧尨偵偁傞堚愓偱丄弌搚昳傕弌偰偄傞丅偙傟偼俁侽侽乣俋侽侽倫倫倣偺摵傪娷傫偱偍傝丄愙怗岎懼峼彴偐傜嶻偡傞峼愇傪巊偭偨偲尵偆堄枴偱尨椏偼嬤峕偺惢揝偺壜擻惈偑崅偄丅偙偺摵傪娷傓揰偑嵭偄偟偰屻擭丄拞悽埲崀偺搧偺抌憿側偳偵偼尨椏傪拞崙抧曽傗搶杒抧曽偺嵒揝偵堏偟偰偄偭偨偺偱偁傞偑丄偄偢傟偵偟偰傕丄偙偺屻丄墇慜偐傜棃偰傢偢偐俀侽擭偱惌尃偵廇偄偨宲懱揤峜偑抋惗偟偨偺偼揝惢晲婍偺偍堻偩偲尵傢傟偰偄傞丅
偟偐偟丄婨撪惌尃帪戙丄揝峼偺嶻抧偵偼庒峕丄廧峕側偳峕偺偮偔挰傗捗偺偮偔挰偑懡偔丄峾嵽偼挬慛敿搰偐傜偺桝擖偑庡偩偭偨偲尵偆偺偑掕愢偱丄幚嵺偵壗帪偛傠偐傜揝偺惢楤偑峴傢傟偨偐偲側傞偲擄偟偄丅暥壢宯偺恖偼栱惗帪戙丄棟宯偺恖偼屆暛帪戙側偳偲尵偆偑丄幚嵺偵偼俇悽婭埲慜偺惢揝堚愓偼尒偮偐偭偰偄側偄偺偱偁傞丅
尰嵼丄帬夑導偵偼嬤婨嵟懡偺俇侽悢儢強丄惢揝堚愓偑偁傞偑偦偺嵟屆偺堦偮偱寋懌帥嫬撪偺傕偺偱偼巁壔揝娷検偑俋係丏俆亾偺峼愇傪巊偄側偑傜丄峼熸偵俈侽乣俉侽亾傕巆偭偰偄傞嵟埆偺儗儀儖偱偁偭偨丅偦傟偑俇俈侽擭揤抭揤峜偺帪戙偵偼乽悈塐傪憿傝偰揝帯偡乿偲偺婰弎偑偁傝丄悈幵傪巊偆傛偆偵側偭偰媄弍偑恑傫偩傛偆偱丄儘僗偑俆侽乣俇侽亾偲壓偑偭偰偄傞丅
撧椙帪戙偵擖傞偲屛撿抧曽偺憪捗偵棫柦娰戝妛偑愊嬌揑偵曐懚偟偰偄傞栘塟尨堚愓偑偁傝丄惢揝偱偼擔杮嵟戝偺栰楬彫栰嶳堚愓偑偁傞丅慜幰偼暥壔挕悇慐偺堚愓側偺偱嬤偔傊峴偐傟偨傜戝妛偵惡傪偐偗偰丄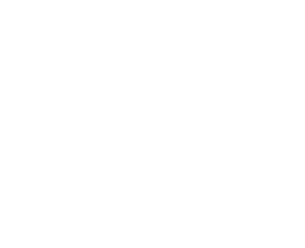 偤傂偛棗捀偒偨偄丅屻幰偼憪捗偺嫵堢埾堳夛偑敪孈傪恑傔偰偄傞傕偺偱丄偙傟傑偱侾係偺巤愝偑偑孈傝弌偝傟丄傑偩傑偩峀偑偭偰偄傞偺偱丄偙傟偐傜偝傜偵偳傟偩偗弌傞偐丄俀侽傪挻偊傞偐傕抦傟側偄丅偦偆側傞偲儘乕儅傪椊偖悽奅堦偺丄崙曮媺偺惢揝堚愓偵側傞偑丄偙傟傎偳偺戝婯柾側傕偺偼崙壠尃椡偑夘擖偟側偗傟偽抸偒摼側偐偭偨偲峫偊傜傟丄幚嵺丄懕擔杮婭偵偼嬤峕偺揝偵娭楢偡傞暥彂偑悢懡偔擖偭偰偄傞丅敪孈娭學幰偼偙偙偱乪摜傒傆偄偛乫傜偟偒傕偺偑弶傔偰弌偰棃偨偺偱婌傫偱偄傞丅
偤傂偛棗捀偒偨偄丅屻幰偼憪捗偺嫵堢埾堳夛偑敪孈傪恑傔偰偄傞傕偺偱丄偙傟傑偱侾係偺巤愝偑偑孈傝弌偝傟丄傑偩傑偩峀偑偭偰偄傞偺偱丄偙傟偐傜偝傜偵偳傟偩偗弌傞偐丄俀侽傪挻偊傞偐傕抦傟側偄丅偦偆側傞偲儘乕儅傪椊偖悽奅堦偺丄崙曮媺偺惢揝堚愓偵側傞偑丄偙傟傎偳偺戝婯柾側傕偺偼崙壠尃椡偑夘擖偟側偗傟偽抸偒摼側偐偭偨偲峫偊傜傟丄幚嵺丄懕擔杮婭偵偼嬤峕偺揝偵娭楢偡傞暥彂偑悢懡偔擖偭偰偄傞丅敪孈娭學幰偼偙偙偱乪摜傒傆偄偛乫傜偟偒傕偺偑弶傔偰弌偰棃偨偺偱婌傫偱偄傞丅
嵟嬤丄敪孈偵嵺偟偰弌偰棃傞峼愇乮帴揝峼乯偵偮偄偰偺拞惈巕曻幩壔暘愅朄偵傛偭偰崿嵼偟偰偄傞嬌旝検偺尦慺偑倫倫倐僆乕僟乕傑偱應傜傟丄偲偔偵惢楤帪偵嬥懏揝偵堏峴偡傞尦慺偱偁傞徨慺偲傾儞僠儌儞偺憡娭惈偐傜惢朄傗嶻抧偺摨掕偵寢傃偮偗偰峫嶡偝傟傞傛偆偵側偭偰棃偨丅偦偺堦偮偺惉壥偲偟偰屛杒偺惸棅捤屆暛偐傜弌偰棃傞揝偼擹弅搙偑俀寘傕偁傝丄堄奜偵崅偄惢朄偱嶌傜傟偰偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅偙偺曈傝偺堚愓偼彮側偔偲傕俆悽婭埲屻偺傕偺偱丄偟偨偑偭偰傗偼傝丄俆悽婭偵偼揝偺惗嶻偑柍偐偭偨偲寢榑晅偗傜傟偨丅擭戙應掕偵娭偟偰偼扽慺侾係偺懚嵼斾傪棙梡偡傞曽朄傕恑傫偱偍傝丄偦傟偧傟惛搙偑岦忋偡傟偽丄楌巎偺夝庍傕傛傝怺傑偭偰備偔偲峫偊傜傟傞丅
俁丏抧媴忋偺戝堎曄偺尞傪偵偓傞偺偼嫄戝暘巕塤偲偺憳嬾偐丠旝検尦慺暘愅傪捠偟偰壖愢傪専摙偡傞
嫗搒戝妛柤梍嫵庼丂錗壓丂丂怣
偙傟偼尦悢妛幰偑塅拡娐嫬偺拞偱抧媴戝曄摦傗惗暔愨柵偺楌巎傪榑偠傞憇戝側榖偱偡丅
悢妛偱偼偄傠偄傠側悢妛揑庤朄傪塅拡偺尰徾偵墳梡偟偰尒傞偙偲偑偁傞偑丄愄丄廳悈慺傪敪尒偟偰僲乕儀儖徿傪栣偭偨儐乕儗僀攷巑偵渁惎偑抧媴偵傇偮偐偭偨傜偳偆側傞偐傪峫偊偰尒側偄偐偲桿傢傟偨偙偲偑偁傞丅偦偺帪偼庒偐偭偨偺偱抐偭偨偺偩偑丄屻偵攷巑偑彂偄偨丄僋儗乕僞乕偺戝偒偝偐傜妱傝弌偟偨戝抧偺壏搙傗奀悈偺壏搙偵偮偄偰偺榑暥偵怗敪偝傟偰丄僴儗乕渁惎偑抧媴偵傇偮偐偭偨帪偺僄僱儖僊乕偼侾儊僈僩儞偺悈慺敋抏俆壄屄偵憡摉偟丄偨傑偨傑抧媴偺昞柺愊偑俆壄暯曽倠倣偱偁傞偙偲偐傜侾暯曽倠倣摉偨傝偵侾屄偢偮棊偪傞傛偆側傕偺偩丄偲偺寁嶼寢壥傪榑暥偵彂偄偨丅偦傫側宱尡偐傜抧媴忋偱偼僇僞僗僩儘僼傿乕偑偟偽偟偽婲偒偰偍傝丄惗暔偺愨柵側偳傕偦傟偑尨場偩偲巚偆傛偆偵側偭偨丅
屆偄榑暥偺拞偱乽懢梲宯偑惎娫僈僗偺拞偵擖偭偨傜丄惎娫暔幙偑懢梲偵棊偪偰峴偭偰柧傞偝偑憹偡偨傔丄昘壨婜偑棃傞乿丄乽抧媴偺壏搙偑忋偑傞偲奀悈偺忲敪偑憹偊丄嬌抧偺昘愥偑憹偊傞丅偦傟偑昘壨婜偺棃傞棟桼乿側偳偺愢傪撉傫偱嫽枴傪帩偭偨偺偱丄偁傞塸崙恖偲堦弿偵抧媴忋偺曄摦偵偮偄偰峫嶡傪巒傔丄懢梲宯偑惎娫僈僗偵撍擖偟偨偙偲偑偝傑偞傑側僇僞僗僩儘僼傿乕傪傕偨傜偡尨場偵側偭偨偲尵偆壖愢傪榑暥偵偟偰塸崙偺俷倐倱倕倰倴倎倲倧倰倷帍偵搳峞偟偨丅
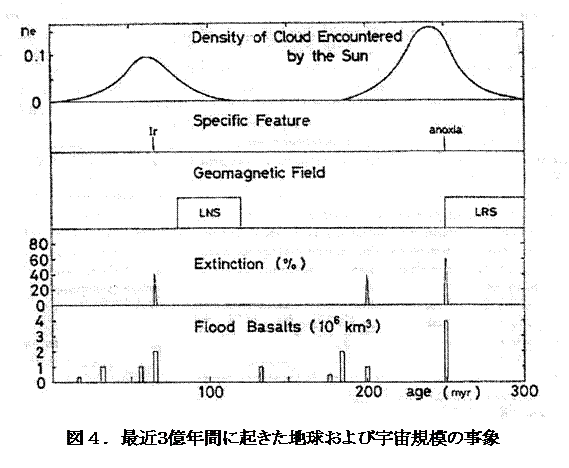 偮傑傝丄懢梲宯偼俀壄擭偺廃婜偱嬧壨宯傪岞揮偟偰偄傞偑丄嬧壨宯偼嬒堦偱偼側偔丄枾搙偺擹扺偑偁傞丅塓姫偒柾條偺柧傞偄偲偙傠偵偼侾棫曽們倣偁偨傝 侾侽俁乣侾侽俆屄偺悈慺暘巕偑偁傞丅懢梲宯偑偦傫側暘巕塤偺拞偵撍擖偡傞偲僈僗偑懢梲偵堷偒婑偣傜傟偰傾僋儕僔僆儞乮崀拝憹戝乯側傞尰徾偑婲偙傝丄偦偺棳傟偺拞偵偄傞抧媴忋偵傕丄惎娫僈僗傗僠儕偑崀傝拲偖偙偲偵側傞丅偦偺寢壥丄師偺俀偮偺岠壥偑尰傟傞偲尵偆偺偑崪巕偱偁傞丅嘆戝婥拞偺巁慺検偑尭彮偡傞丅偦偺寢壥丄巁寚偵庛偄唳拵椶傗崺拵偼愨柵偵捛偄崬傑傟偨偑丄歁擕椶偼桪傟偨攛傪帩偭偰偄傞偺偱惗偒墑傃傜傟偨偲峫偊傜傟傞丅嘇僠儕偵傛偭偰懢梲岝偑幷傜傟丄姦椻壔偑婲偒傞偲嫟偵丄僠儕偵娷傑傟傞抧媴偵彮側偄尦慺偑傕偨傜偝傟傞丅偙傟偐傜昘壨婜傗僀儕僕僂儉偺懲愊偑愢柧偝傟傞丅
偮傑傝丄懢梲宯偼俀壄擭偺廃婜偱嬧壨宯傪岞揮偟偰偄傞偑丄嬧壨宯偼嬒堦偱偼側偔丄枾搙偺擹扺偑偁傞丅塓姫偒柾條偺柧傞偄偲偙傠偵偼侾棫曽們倣偁偨傝 侾侽俁乣侾侽俆屄偺悈慺暘巕偑偁傞丅懢梲宯偑偦傫側暘巕塤偺拞偵撍擖偡傞偲僈僗偑懢梲偵堷偒婑偣傜傟偰傾僋儕僔僆儞乮崀拝憹戝乯側傞尰徾偑婲偙傝丄偦偺棳傟偺拞偵偄傞抧媴忋偵傕丄惎娫僈僗傗僠儕偑崀傝拲偖偙偲偵側傞丅偦偺寢壥丄師偺俀偮偺岠壥偑尰傟傞偲尵偆偺偑崪巕偱偁傞丅嘆戝婥拞偺巁慺検偑尭彮偡傞丅偦偺寢壥丄巁寚偵庛偄唳拵椶傗崺拵偼愨柵偵捛偄崬傑傟偨偑丄歁擕椶偼桪傟偨攛傪帩偭偰偄傞偺偱惗偒墑傃傜傟偨偲峫偊傜傟傞丅嘇僠儕偵傛偭偰懢梲岝偑幷傜傟丄姦椻壔偑婲偒傞偲嫟偵丄僠儕偵娷傑傟傞抧媴偵彮側偄尦慺偑傕偨傜偝傟傞丅偙傟偐傜昘壨婜傗僀儕僕僂儉偺懲愊偑愢柧偝傟傞丅
僇僞僗僩儘僼傿乕偵娭學偡傞帠暱偲偟偰偼丄惗暔偺戝愨柵丄僋儗乕僞乕偺惗惉昿搙丄壩嶳暚壩丄抧帴婥偺曄摦丄旝検尦慺丄懢梲宯偺塣摦側偳偑偁傝丄偙傟傜傪儗價儏乕偟偰峴偒側偑傜丄暘巕塤憳嬾偺寢榑偵帩偭偰峴偔偙偲偵側傞丅
幚嵺丄夁嫀偵懢梲宯偑偄偨応強傪寁嶼偡傞偲丄惗暔愨柵偑婲偒偨俲/俿嫬奅傗丄偝傜偵俆壄擭慜偵傕塓忬榬偺拞偵偄偨偙偲偵側傞丅儔僂僗摍偑帵偟偨傛偆偵丄
俇俆侽侽枩擭慜偺嫲棾愨柵帪乮敀垷婭偲戞嶰婭娫丄俲/俿嫬奅乯傗俀壄俆愮枩擭慜乮儁儖儉嶰忯婭娫丄俹/俿嫬奅乯偲俆壄擭慜偺傕偺傪戙昞偲偟偰丄偄偔偮偐偺奀梞惗暔愨柵偺僺乕僋偑偁傞偙偲偼崱偱偼傛偔抦傜傟偰偄傞丅抧媴忋偺僋儗乕僞乕偵偮偄偰偼丄儊僉僔僐丒儐僇僞儞敿搰偺戝僋儗乕僞乕偺惗惉偑嫲棾偺愨柵偟偨帪婜偵傎傏堦抳偟偰偄傞丅抧妛揑偵偼俇俆侽侽枩擭慜偵僀儕僕僂儉偺懲愊偑偁傝丄俀壄俆愮枩擭慜偵偼奀偱戝婯柾側巁寚偑偁偭偨偲偝傟偰偄傞丅惗暔妛幰偼偙偺俙値倧倶倝倎偑愨柵偺尨場偲峫偊偰偄傞偑丄幚嵺丄偙偺擭戙偵憡摉偡傞僋儗乕僞乕偼捈宎係侽倠倣偱丄偲偰傕慡抧媴愨柵傑偱偼峴偒偦偆偵柍偄丅傑偨丄僀儕僕僂儉偺専弌偝傟傞憌偲戝徴撍偺徹嫆偲偝傟傞儅僀僋儘僥僋僞僀僩旝棻巕憌偺娫偵偼俁侽枩擭偺偢傟偑偁傝丄傛偔尵傢傟傞傛偆側場壥娭學偼偐側傜偢偟傕寢榑偝傟側偄丅偨偩丄懠偵傕侾侽侽屄埲忋偺僋儗乕僞乕偑敪尒偝傟偰偄傞偑丄惗惉偟偨擭戙偵廃婜惈偑擣傔傜傟傞丅
戝暚壩偵偮偄偰偼丄偦偺婯柾偑俀昐悢廫枩棫曽 倠倣偲偄偆嫄戝側僀儞僪偺僨僇儞崅尨偵偁傞傕偺偑俲/俿嫬奅偵堦抳偟丄俀壄俆愮枩擭慜偵傕僔儀儕傾偱戝偒側暚壩偑婲偒偰偄傞丅堦曽丄抧媴帴応偼撿杒偺媡揮傪孞傝曉偟偰偄傞偑丄偦傟偑慡偔尰傟側偄僗乕僷乕僋儘儞偲尵傢傟傞帪婜偑偁傝丄偦傟偑廔傢偭偰偟偽傜偔偡傞偲惗暔偺愨柵偑尒傜傟傞丅帴応偺曄摦偼抧妅峔憿偺曄壔偲娭學偡傞傛偆偩偑丄抧媴偑姦椻壔偟偰嬌抧曽偺昘偑憹偊傞偲姷惈擻棪偑壓偑偭偰帺揮懍搙偑懍傑傝丄拞怱晹暘偲偺懍搙嵎偑惗傑傟傞丅偙傟偑撪奜峔憿偺嫬奅偱偐偔棎傪堷偒婲偙偡梫場偲側偭偰僾儕儏乕儉傪敪惗偝偣丄戝婯柾側壩嶳妶摦傪傕偨傜偡儊僇僯僘儉偑偁傞偐傕抦傟側偄丅俆壄擭慜偵婲偒偨偲偝傟傞慡抧媴搥寢傕丄嵟嬤丄暷崙偺壢妛幰偑傑偝偵傾僋儕僔僆儞偵傛傞偲弎傋偰偄傞丅
偄偢傟偵偟偰傕丄巹偺壖愢偼丄偡傋偰偺妛幰偵庴偗擖傟傜傟偰偼偄側偄偐傕偟傟側偄偑丄堦墳嵏撉偺偁傞嶨帍偵嵹偭偨偺偱丄媍榑偺僥乕僽儖偵偼忔偭偨偲峫偊偰偄傞丅崱屻偙偺愢偼抧媴忋偱懢梲宯奜偺暔幙偺懚嵼傪専徹偡傞偙偲偱徹柧偝傟傞偩傠偆丅偦偺桳椡岓曗偼僂儔儞偺摨埵懳斾偱偁傞丅偮傑傝丄挻怴惎敋敪偺帪偵嶌傜傟傞倀俀俁俆偲倀俀俁俉偼偦傟偧傟堎側傞敿尭婜傪帩偮偺偱抧忋偵偍偗傞椉幰偺暯嬒揑側斾偲堎側傞抣偑尒偮偐傟偽丄偦傟偑懢梲宯奜暔幙偱偁傞偲偺暔棟揑側徹嫆偲側傞丅尰嵼丄婒晫戝妛偺愳忋恆堦嫵庼偑慡抧媴搥寢偺徹嫆偑摼傜傟傞傾僼儕僇偺僫儉價傾偱廂廤偟偨帋椏傪暘愅偝傟偰偍傝丄寢壥傪妝偟傒偵懸偭偰偄傞偲偙傠偱偁傞丅
係丏俥俢俧亅俹俤俿偍傛傃俹俤俿乛俠俿偵傛傞庮釃偺夋憸恌抐丂丂丂丂丂
嫗搒戝妛愭抂椞堟梈崌堛妛尋媶婡峔
丂拞杮丂桾巑
俹俤俿恌抐偺榖偼偙偺僔儞億僕僂儉偱傕偡偱偵擇搙庢傝忋偘傜傟丄偦偺桳梡惈偼徯夘嵪傒偩偑丄嵟嬤丄娐嫬傕惍偭偰旘桇揑偵棙梡偑墑傃偰棃偨丅偙偙偱偼偙偺媄弍偑偦偺屻偳偺傛偆偵恑壔偟偮偮偁傞偐丄尰嵼偺帠忣傪夝愢偟偰捀偄偨丅
俹俤俿乮俹倧倱倝倲倰倧値 俤倣倝倱倱倝倧値 俿倧倣倧倗倰倎倫倛倷乯偼僌儖僐乕僗暘巕偺堦晹偵億僕僩儘儞乮梲揹巕乯傪弌偡曻幩惈僼僢慺乮18俥乯傪寢崌偝偣偨俥俢俧偲尵偆柤偺栻嵻傪懱撪偵搳擖偟丄偦偺廤傑傞応強傪夋憸壔偟偰恌抐偵棙梡偡傞曽朄偱偁傞丅俥俢俧偼僌儖僐乕僗偲摨偠傛偆偵怴捖戙幱偺寖偟偄晹暘偵廤傑傞偑丄僌儖僐乕僗偲堘偭偰戙幱偼偝傟側偄偺偱廤傑偭偨応強偑梕堈偵尒偮偗傜傟傞丅嵟弶偼摿偵戙幱偺寖偟偄僈儞偺恌抐偵椙偄偲偝傟偰棃偨偑丄尋媶偑恑傓偵偮傟偰丄崱偱偼擼峓嵡傗傾儖僣僴僀儅乕丄怱嬝峓嵡側偳偺恌抐偵傕棙梡偱偒傞偙偲偑夝偭偰墳梡偑峀偑偭偰棃偨丅偨偩丄椪彴偵巊傢傟弌偟偰偐傜傕侾侽擭掱偼巤愝偺悢傕偁傑傝怢傃側偐偭偨偑丄俀侽侽俀擭係寧偐傜偺曐尟揔梡傪庴偗丄摿偵柉娫偺堛椕巤愝偑媫憹偟偨偨傔晛媦偵攺幵偑偐偐傝丄偦偺擭偺巤愝偺悢偼俀擭慜偺幚偵俇攞偵払偟偰偄傞丅
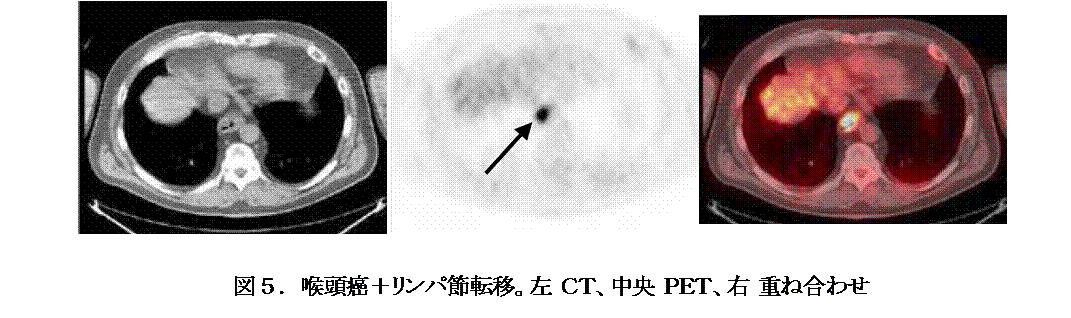 俥俢俧偺曻幩擻偼俀帪娫傎偳偱敿暘偵側傞偺偱丄曻幩慄偺塭嬁傕彫偝偔丄攑婞張棟傕妝側暔幙偱偁傞偑丄偦偺崌惉偵偼丄傑偢侾俉俥傪妀斀墳偵傛偭偰嶌傞僒僀僋儘僩儘儞偲丄偦傟傪尨椏偲偡傞俥俢俧崌惉憰抲偑昁梫偱丄壛偊偰暋嶨側嶣塭憰抲傪崌傢偣傞偲侾侽壄墌偵傕払偟丄摫擖偼娙扨偱偼柍偄丅偦偺揰丄嶐擭丄俥俢俧偺彜梡嫙媼偑巒傑傝丄僇儊儔偩偗偱専嵏嬈偑弌棃傞傛偆偵側偭偨偺偱晛媦偼偝傜偵壛懍偡傞偲峫偊傜傟傞丅
俥俢俧偺曻幩擻偼俀帪娫傎偳偱敿暘偵側傞偺偱丄曻幩慄偺塭嬁傕彫偝偔丄攑婞張棟傕妝側暔幙偱偁傞偑丄偦偺崌惉偵偼丄傑偢侾俉俥傪妀斀墳偵傛偭偰嶌傞僒僀僋儘僩儘儞偲丄偦傟傪尨椏偲偡傞俥俢俧崌惉憰抲偑昁梫偱丄壛偊偰暋嶨側嶣塭憰抲傪崌傢偣傞偲侾侽壄墌偵傕払偟丄摫擖偼娙扨偱偼柍偄丅偦偺揰丄嶐擭丄俥俢俧偺彜梡嫙媼偑巒傑傝丄僇儊儔偩偗偱専嵏嬈偑弌棃傞傛偆偵側偭偨偺偱晛媦偼偝傜偵壛懍偡傞偲峫偊傜傟傞丅
俹俤俿偼娭怱椞堟奜偺昦曄偑暘偐傞偲偐丄婡擻偺峍恑側偳宍懺妛揑側抦尒偵僾儔僗偡傞忣曬偑摼傜傟傞偨傔丄堛椕傊偺僀儞僷僋僩偼戝偒偔丄姵晹偵偮偄偰偺埆惈搙偺昡壙丄恑揥忬嫷丄帯椕岠壥偺敾掕丄嵞敪偺壜斲丄偝傜偵偼専恌偵傛傞僗僋儕乕僯儞僌側偳棙梡偑峀偑偭偰偄傞丅
堦尒丄棟憐揑偵尒偊傞俹俤俿偺僨乕僞偩偑丄弶婜偵尵傢傟偰偄偨傛偆偵捈宎傢偢偐悢儈儕偺偑傫偱傕敪尒弌棃傞丄偼岆傝偱丄偦傫側椺傕偁偭偨偲尵偆偺偑惓偟偄偟丄懠偵傕銷泖丄嫻態丄崪奿嬝側偳傊偺惗棟揑側俥俢俧廤愊側偳丄偝傑偞傑側婾梲惈丄婾堿惈偺梫場偑偁傞丅偨偲偊偽丄専嵏偺慜偵愻幵傪偟偨偨傔偵尐偺嬝擏偵廤愊偑尒傜傟偨椺傕偁偭偨丅
堦曽丄俠俿傗俵俼俬偼夝朥妛揑偵徻偟偄忣曬偑摼傜傟傞偑丄妋怣傪帩偭偰昦曄傪巜揈偡傞偙偲偑偟偽偟偽崲擄偱偁傞丅偦偺偨傔丄椉幰傪暪偣丄斾妑専摙偡傞曽岦偱墳梡偼恑傫偱棃偨偺偩偑丄暿乆偵嶣傜傟偨夋憸偐傜埵抲偺堦抳傪敾抐偡傞偺偼帪娫偺偐偐傞妱傝偵惛搙偺椙偄傕偺偱偼柍偐偭偨丅偲尵偆偙偲偱丄嵟嬤偵側偭偰椉幰偺僨乕僞偑摨帪偵庢傟傞俹俤俿乛俠俿憰抲偑奐敪偝傟偨丅彜梡婡偺戞侾崋偼俀侽侽侾擭偵傾儊儕僇偱敪攧偝傟丄偨傑偨傑墘幰偑棷妛拞偵偦偺峸擖帪偵棫偪夛偭偨偑丄偦偺屻丄恌抐惛搙偑戝偒偔岦忋偟偨丅
偨偲偊偽恾俆偱偼俠俿偩偗偱偼怘摴偑傫偲暘偐傝擄偄偑丄廳偹崌傢偣偨恾傪尒傞偲丄偑傫偺埵抲傑偱偼偭偒傝暘偐傞丅惓偟偄昦婜偺恌抐惉愌傪悢抣偱尒偰傕丄扨撈偺応崌偱俇俁亾丄懳斾恌抐偑俈俇亾偵偨偄偟俹俤俿乛俠俿偱偼俉係亾偵岦忋偟偰偄傞丅曻幩慄偵傛傞偑傫帯椕偱偼徠幩偡傋偒椞堟偺戝偒偝寛掕偑廳梫偱偁傞偑俠俿偺傒偱敾掕偟偨応崌偺56%偱曄峏偑昁梫偲偝傟偰偄傞丅偦偺傎偐懡偔偺徢椺偱帯椕曽恓偵塭嬁傪梌偊偰偄傞丅
偙偺傛偆偵梈崌夋憸偺儊儕僢僩偼懡偔丄専嵏帪娫偑抁弅弌棃傞偨傔僗儖乕僾僢僩偑戝偒偄偺偱丄崱屻偼専恌偵傕埿椡傪敪婗偡傞偲峫偊傜傟傞偑丄栤戣揰偲偟偰偼曻幩慄偺旐敋検偑戝偒偄偙偲偲丄傑偩憰抲偑崅壙側偙偲偑偁傞丅偪側傒偵屻幰偵偮偄偰偼屌掕憰嬶傪巊偭偰埵抲寛傔傪偟丄暿乆偵應掕偟偨僨乕僞傪廳偹崌傢偣偰娤傞曽朄偑埲奜偵桳岠偱偁傞丅偄偢傟偵偟偰傕丄梈崌夋憸偵傛傞憡忔岠壥偺妶梡偼崱屻傑偡傑偡廳梫惈傪憹偟偰峴偔偲峫偊傜傟傞丅
埲忋丄偙偺傛偆側島墘偱偼偍側偠傒偲側傝傑偟偨偑丄師乆偵僗僋儕乕儞忋偵尰傟傞慺恖栚偵傕堦尒偟偰偦傟偲暘偐傞惗乆偟偄夋憸偵埑搢偝傟側偑傜丄堛椕偺恑曕偺嵼傝條偵丄偟偽偟丄帪娫傪朰傟偰暦偒擖傝傑偟偨丅
俆丏掅慄検曻幩慄偲惗懱柶塽擻偺曄壔
搶嫗棟壢戝妛栻妛晹 嫵庼丂彫搰 廃擇
掅慄検曻幩慄偺惗懱塭嬁偼偄偮傕婥偵側傞榖戣偱偡丅崱夞偼儔僕僇儖曔懆嵻偲偟偰傕桳岠側僌儖僞僠僆儞傪巜昗偵偟偰柶塽宯傊偺曻幩慄偺塭嬁傪挷傋偨嫽枴偁傞偍榖偱偡丅
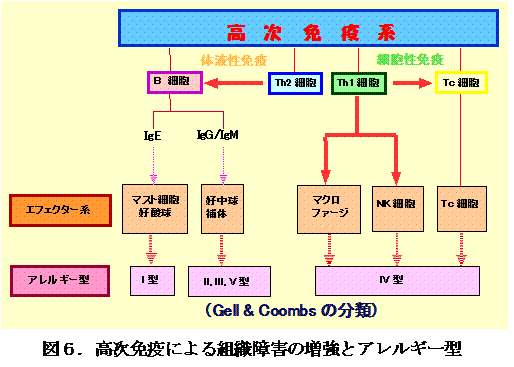 偙傟傑偱偵曬崘偝傟偰偄傞曻幩慄掞峈惈偺桿摫傗娻揮堏偺梷惂丄柶塽婡擻偺妶惈壔側偳偵偮偄偰惗棟妛揑側婡峔傪柧傜偐偵偡傞偨傔偵丄柶塽宯偺摥偒傪壔妛揑偵巟偊偰偄傞偲峫偊傜傟傞峈巁壔暔幙偺堦偮丄僌儖僞僠僆儞乮埲壓丄俧俽俫乯偑掅慄検曻幩慄徠幩偵傛偭偰偳偺傛偆偵曄壔偡傞偐傪挷傋偨丅僌儖僞僠僆儞偼嶰偮偺傾儈僲巁偐傜側傞僩儕儁僾僠僪偱丄偦偺堦偮偱偁傞僔僗僥僀儞偺-俽俫峔憿偵桼棃偡傞嫮偄娨尦妶惈偑峈巁壔嶌梡傪傕偨傜偡丅
偙傟傑偱偵曬崘偝傟偰偄傞曻幩慄掞峈惈偺桿摫傗娻揮堏偺梷惂丄柶塽婡擻偺妶惈壔側偳偵偮偄偰惗棟妛揑側婡峔傪柧傜偐偵偡傞偨傔偵丄柶塽宯偺摥偒傪壔妛揑偵巟偊偰偄傞偲峫偊傜傟傞峈巁壔暔幙偺堦偮丄僌儖僞僠僆儞乮埲壓丄俧俽俫乯偑掅慄検曻幩慄徠幩偵傛偭偰偳偺傛偆偵曄壔偡傞偐傪挷傋偨丅僌儖僞僠僆儞偼嶰偮偺傾儈僲巁偐傜側傞僩儕儁僾僠僪偱丄偦偺堦偮偱偁傞僔僗僥僀儞偺-俽俫峔憿偵桼棃偡傞嫮偄娨尦妶惈偑峈巁壔嶌梡傪傕偨傜偡丅
徠幩偺堄媊傪暘偐傝傗偡偔偡傞偨傔偵丄嵟弶偵柶塽懱宯偺傾僂僩儔僀儞傪Gell & Coombs 偺暘椶乮恾俇乯偵傛偭偰愢柧偡傞偲丄堎暔偺崿擖偵懳偟偰嵟弶偵懳張偡傞偺偼僿儖僷乕俿嵶朎偱偁傞偑丄偦傟偵偼儅僋儘僼傽乕僕傗僉儔乕嵶朎偵娭傢傞嵶朎惈柶塽宯偺Th1偲B嵶朎傪捠偟偰峈懱嶻惗傪懀偡懱塼惈柶塽宯偺Th2偑偁傝丄椉幰偺娫偵偼堦掕偺僶儔儞僗偑曐偨傟偰偄傞丅柶塽宯偼堎暔偵懳偟偰柍偔偰偼側傜側偄偑丄帺屓慻怐偵摥偔偲偄傢備傞傾儗儖僊乕徢忬傪掓偡傞偙偲偵側傝丄尨場偵傛偭偰恾俇偵暘椶偝傟傞偄偔偮偐偺宆偑偁傞丅傢傟傢傟偑懱尡偡傞昦婥偺懡偔偼偙偺拞偵娷傑傟傞丅
幚尡偲偟偰偼丄傑偢丄儅僂僗偵侽.俆俧倷偺曻幩慄傪慡恎徠幩偡傞偲丄銪儕儞僷媴撪偺俧俽俫偼係帪娫屻偵俇乣俈攞偵憹壛偟偨丅摨帪偵丄僉儔乕嵶朎偺儕儞僷庮嵶朎偵懳偡傞嶦嵶朎妶惈乮俶俲妶惈乯傕俇帪娫屻偵栺俀攞丄奜棃偺梤愒寣媴偵懳偡傞儅僂僗儕儞僷媴偺嶦彎妶惈乮俙俢俠俠妶惈乯傕栺係攞掱搙忋徃偟偰偄偰丄徠幩偵傛偭偰柶塽妶惈偑崅傑偭偰偄偨丅徠幩偺戙傢傝偵俧俽俫傪壛偊偰傕丄擹搙偲嫟偵俶俲妶惈丄俙俠俢俢妶惈偑嫟偵憹壛偟丄侾丏侽倣俵偺帪偵侽丏俆俧倷徠幩偲傎傏摨條偺寢壥偲側偭偨丅偙傟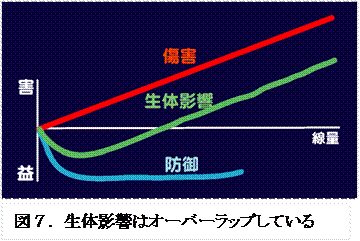 傜偺妶惈偑俧俽俫偺懚嵼偵埶懚偡傞偙偲偼俧俽俫偺慜嬱懱偲偝傟傞暔幙偲偲傕偵俧俽俫惗惉傪慾奞偡傞暔幙傪壛偊偰専徹偝傟偨丅師偵丄屌宍僈儞傪堏怉偟偨儅僂僗偵侽丏俆俧倷偺曻幩慄傪係夞偵暘偗偰慡恎偵徠幩偟偨偲偙傠丄旕徠幩偵斾傋柧傜偐偵憹戝壔偺懍搙偑抶偔側傝丄庮釃柶塽偺妶惈壔傕妋擣偝傟偨偙偲偐傜丄徠幩偵傛偭偰妶惈壔偝傟傞柶塽擻偺梫場偼怴偟偔崌惉偝傟偨僌儖僞僠僆儞偺壜擻惈偑帵嵈偝傟丄偦傟偵敽偭偰庮釃柶塽傕妋擣偝傟偨丅
傜偺妶惈偑俧俽俫偺懚嵼偵埶懚偡傞偙偲偼俧俽俫偺慜嬱懱偲偝傟傞暔幙偲偲傕偵俧俽俫惗惉傪慾奞偡傞暔幙傪壛偊偰専徹偝傟偨丅師偵丄屌宍僈儞傪堏怉偟偨儅僂僗偵侽丏俆俧倷偺曻幩慄傪係夞偵暘偗偰慡恎偵徠幩偟偨偲偙傠丄旕徠幩偵斾傋柧傜偐偵憹戝壔偺懍搙偑抶偔側傝丄庮釃柶塽偺妶惈壔傕妋擣偝傟偨偙偲偐傜丄徠幩偵傛偭偰妶惈壔偝傟傞柶塽擻偺梫場偼怴偟偔崌惉偝傟偨僌儖僞僠僆儞偺壜擻惈偑帵嵈偝傟丄偦傟偵敽偭偰庮釃柶塽傕妋擣偝傟偨丅
堦曽丄僿儖僷乕俿嵶朎偵偮偄偰偺忋婰偺僶儔儞僗傪俿倛侾丄俿倛俀偦傟偧傟偺巋寖偱曻弌偝傟傞僀儞僞乕儘僀僉儞側偳丄偄傢備傞僒僀僩僇僀儞椶偺斾傪挷傋偰捛媮偟偨偲偙傠丄曻幩慄徠幩偼俿倛侾柶塽宯傪嫮壔偡傞曽岦偵孹偐偣丄慡儕儞僷媴偵懳偡傞憡懳斾偱傕俛嵶朎偺尭彮偑尒傜傟偨丅
偙傟傪婎偵丄俛嵶朎偺峈懱惗惉偵桼棃偟丄恾俇偵偍偗傞嘨宆偵暘椶偝傟傞廳徢惈帺屓柶塽昦偺儌僨儖儅僂僗偵偮偄偰徠幩偺岠壥傪挷傋偨偲偙傠丄俿嵶朎偺僶儔儞僗偑俿倛侾傊僔僼僩偡傞寢壥偑摼傜傟傞偲嫟偵丄抈敀擜傗恡憻慻怐偺強尒側偳丄懡偔偺柺偱昦懺偺夵慞偑尒傜傟丄庻柦傕挿偔側偭偨丅偨偩丄堎忢嵶朎偺尒偐偗偺検偑嬌傔偰尭彮偟偰偍傝丄柶塽偲偄偆傛傝偼丄巋寖偵姶庴惈偺崅偄堎忢嵶朎偑巰傫偩偨傔偵丄寢壥揑偵僶儔儞僗偑夞暅偟偰丄昦懱偺夵慞偵傕婑梌偟偨偲敾抐偝傟傞丅
偮傑傝丄曻幩慄偺惗懱塭嬁偼杊屼偲彎奞偺岠壥偑僆乕僶乕儔僢僾偟偰偍傝丄丂恾俈偵帵偡傛偆偵掅慄検偱偼僾儔僗偺岠壥偑彑傞偙偲偑婜懸弌棃傞丅
俇丏崅懍憹怋楩偺奐敪亅乽傕傫偠傘乿夵憿拝庤偵偁偨偭偰亅
乮撈乯擔杮尨巕椡尋媶奐敪婡峔
師悽戙尨巕椡僔僗僥儉尋媶奐敪晹栧丂拞搰丂暥柧
枹棃傪扴偆崅懍憹怋楩乮俥俛俼乯偼幚徹楩乽傕傫偠傘乿偺抜奒偱僫僩儕僂儉帠屘偑敪惗偟丄侾侽擭娫偺僽儔儞僋傪梋媀側偔偝傟傑偟偨偑丄嶐擭傛偆傗偔嵞奐偺栚張偑偮偒傑偟偨丅偙偙偱偼俥俛俼偺堄媊偲嫟偵娭楢偡傞彅帠忣傪榖偟偰捀偒傑偟偨丅
僂儔儞偺拞偱擱椏偲偟偰偼巊偊側偄俋俋丏俁亾偺僂儔儞乮倀乯俀俁俉傪擱椏偵側傞僾儖僩僯僂儉乮俹倳乯偵曄偊偰巊偍偆偲偡傞俥俛俼偼僂儔儞傪愡栺偡傞偙偲偵傛偭偰奀奜帒尮偐傜偺帺棫偲僄僱儖僊乕偺埨慡妋曐傪幚尰偟丄摨帪偵攑婞暔偺敪惗検傪彮側偔偡傞壜擻惈傕暪偣帩偭偰偄傞丅偡側傢偪丄崅懍偺拞惈巕偺応崌丄挿庻柦偺傾僋僠僯僪乮俶倫丆俙倣丆俠倣乯傗偦偺懠偺妀暘楐惗惉暔傪妀擱椏僒僀僋儖偵慻傒崬傒丄娐嫬傊偺攔弌検傪掅尭弌棃傞丅偦偺応崌偺曻幩惈攑婞暔偺敿尭婜偼悢枩擭偐傜悢昐擭偵棊偲偟丄恖娫幮夛偑攃埇偱偒傞斖埻偵偡傞壜擻惈偑偁傞丅
嶐擭侾侽寧偵妕媍寛掕偝傟偨尨巕椡惌嶔戝峧偱偼俀侽俁侽擭埲崀傕擔杮偺僄僱儖僊乕偺尨巕椡埶懚傪俁侽乣係侽亾埲忋偲悇彠偟偨忋偱丄俥俛俼傪崙壠愴棯偲埵抲偯偗丄媄弍奐敪傪懀恑偟偰丄俀侽俆侽擭崰偐傜彜嬈儀乕僗偱摫擖偡傞偙偲傪栚巜偡偲偟偰偄傞丅
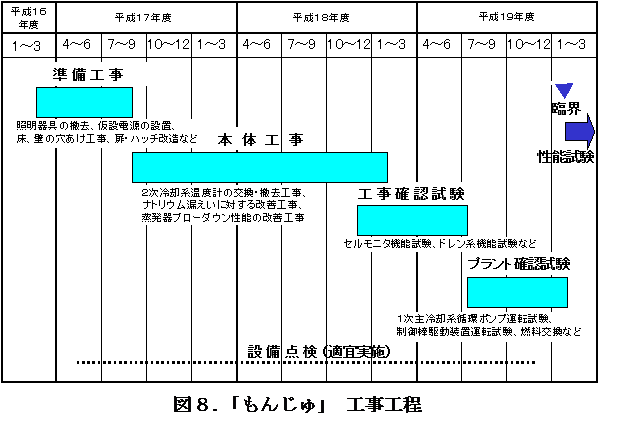 乽傕傫偠傘乿偼侾俋俉俁擭偵愝抲偺嫋壜偑壓傝丄巒摦傪巒傔偰偐傜丄俋係擭偵椪奅偵払偟丄梻擭偵偼係侽亾偺憲揹弌椡傪婰榐偟偨偑丄偦偺擭偺侾俀寧偵僫僩儕僂儉帠屘偑婲偒偰偟傑偭偨丅尨巕楩杮懱偺僩儔僽儖偱偼柍偐偭偨偑丄偐嵟弶棟帠偺晄庤嵺偑晄怣傪偐偭偰埲棃侾侽擭娫掆巭偟丄嶐擭俆寧丄傛偆傗偔夵憿岺帠偺椆夝偑摼傜傟偨偲偄偆忬嫷偵偁傞丅
乽傕傫偠傘乿偼侾俋俉俁擭偵愝抲偺嫋壜偑壓傝丄巒摦傪巒傔偰偐傜丄俋係擭偵椪奅偵払偟丄梻擭偵偼係侽亾偺憲揹弌椡傪婰榐偟偨偑丄偦偺擭偺侾俀寧偵僫僩儕僂儉帠屘偑婲偒偰偟傑偭偨丅尨巕楩杮懱偺僩儔僽儖偱偼柍偐偭偨偑丄偐嵟弶棟帠偺晄庤嵺偑晄怣傪偐偭偰埲棃侾侽擭娫掆巭偟丄嶐擭俆寧丄傛偆傗偔夵憿岺帠偺椆夝偑摼傜傟偨偲偄偆忬嫷偵偁傞丅
乽傕傫偠傘乿偺揹婥弌椡偼俀俉枩倠倂丄倀偲俹倳崿崌偺俵俷倃擱椏傪巊梡偟丄僫僩儕僂儉乮俶倎乯偱椻媝偡傞宆偱丄椻媝宯偺侾師丄俀師偑俶倎丄俁師宯偑悈偱偁傞丅帠屘偼俀師宯偵愝抲偝傟偨壏搙寁偑愜傟偰俶倎偑楻傟偨偺偩偑丄俶倎偼曻幩壔偟偰偄側偄丅悈偲俶倎偼寖偟偄斀墳傪偡傞丅偙偺帠屘傪嫵孭偲偟偰丄俀師宯偺惍旛傪恑傔傞偙偲偵側偭偨丅岺帠嫋壜偺奣梫偼嘆壏搙寁岎姺乮宍忬偺曄峏丄杮悢偺嶍尭側偳乯嘇俶倎楻塳懳嶔嘊悈忲婥楻塳丒埨慡懳嶔偺嶰揰偵廳揰偑抲偐傟丄尰嵼恾俉偺擔掱偱弴挷偵恑傫偱偄傞丅
崱屻偺壽戣傪惍棟偡傞偲丄塣揮傪捠偟偰媄弍忋偺怣棅惈岦忋傪栚巜偡偲嫟偵丄宱嵪惈偺岦忋傪恾傞丅偦偺偨傔偵擱從搙傪俉亾偐傜侾俆亾偵堷偒忋偘偰丄僒僀僋儖偺廃婜傪俆儠寧偐傜侾侽儠寧掱搙偵怢偽偡怴宆擱椏偺奐敪傗怴媄弍偺奐敪丄昗弨壔丄摿偵暘夝偟側偄偱揰専偡傞専嵏媄弍偺妋棫側偳懡偔偺栚昗偑偁傞丅傑偨丄偙偙傪尋媶奐敪偺応偲偟偰恖嵽堢惉傗嫵堢乮僔儈儏儗乕僞乕偺棙梡側偳乯偵妶梡偟偨傝丄崙嵺揑側尋媶嫆揰偵偟偰峴偔偙偲傗丄俆侽侽亷偺擬棙梡尋媶側偳丄惣擔杮偺徠幩棙梡偺応偲偟偰抧堟偲楢実偟偨嶻嬈偺憂惗傪恾傝偮偮丄偦傟傪捠偟偰棟夝偺懀恑傪恾傞偙偲傕廳梫偱偁傞丅偦傟傜偺憤崌揑側寢壥傪婎偵俀侽侾俆擭偛傠偵偼俥俛俼僒僀僋儖偺媄弍懱宯傪採埬偟偰峴偒偨偄偲峫偊偰偄傞丅
堦曽丄奀奜帠忣偩偑丄傑偢丄僀儞僪偼偡偱偵幚尡楩傪塣揮偟偮偮丄尨宆楩傪寶愝拞偱俀侽侾侽擭偵偼塣揮傪巒傔丄偝傜偵係乣俆婡偵憹傗偟偨偄堄岦偱偁傞丅拞崙偼僆儕儞僺僢僋偵偼幚尡楩傪摦偐偡偲偟偰偍傝丄儘僔傾偼幚尡楩丄尨宆楩偲傕偵塣揮拞偱偁傞丅偙傟偵懳偟傾儊儕僇偼僽僢僔儏惌尃偵側偭偰偐傜妀擱椏僒僀僋儖偺昁梫惈傪擣傔丄抧憌張暘傕愭偑尒偊偰偄傞偲偟偰惌嶔揮姺偺僞僀儈儞僌傪寁偭偰偄傞偲偙傠偩偑丄偡偱偵尋媶奐敪儗儀儖偺梊嶼偼偮偄偰妶惈壔偟偮偮偁傞丅僼儔儞僗偼僗乕僷乕僼僃僯僢僋僗偑掆巭偟偨傑傑丄尰嵼塣揮拞偺俀俆枩倠倂偺僼僃僯僢僋僗傕俀侽侽俉擭偵偼掆巭偺梊掕偱丄摉柺丄悈慺惢憿偵偮側偑傞僈僗椻媝楩偺奐敪傪峫椂拞偱偁傞偑丄俀侽俁侽擭崰偐傜巒傑傞婛懚婡偺庻柦岎懼婜偺師偼俶倎椻媝偑杮柦偩偲偟偰丄偦傟傑偱偺娫丄乽傕傫偠傘乿偱嫟摨尋媶偟偰峴偒偨偄偲丄栚壓丄傾儊儕僇傪娷傔偨嶰幰宊栺偺媗傔偺抜奒偵擖偭偰偄傞丅
嵟屻偵偙傟傜偺尋媶奐敪偼抧尦偺棟夝偑偁偭偰巒傔偰埨掕偟丄惉岟偡傞偲偺棫応偐傜丄抧堟楢崌傪怺傔傞偨傔偵楢実戝妛堾傪嶌偭偰嫵庼傪攈尛偟偨傝丄嶻嬈奅偲傕摿嫋偺棙梡傗媄弍憡択側偳偱楢実傪怺傔偰偄傞丅傑偨丄暉堜導偑嶐擭傛傝棫偪忋偘偰偄傞尋媶奐敪嫆揰寁夋偵乽傕傫偠傘乿偑帩偭偰偄傞俥俛俼媄弍乮崅懍拞惈巕丄俶倎丄崅壏愝寁丄専嵏媄弍乯傪採嫙偟丄峷專偟偰峴偒偨偄偲峫偊偰偄傞丅
俈丏崅壏僈僗楩偺妀擬傪棙梡偟偨悈慺惢憿
乮撈乯擔杮尨巕椡尋媶奐敪婡峔
尨巕椡婎慴岺妛尋媶晹栧丂崙晉 堦旻
嵟屻偺榖戣偼嬤偄彨棃偺擱椏揹抮幮夛偵岦偗偰昁梫偲側傞悈慺僈僗傪岠棪傛偔惢憿偡傞媄弍偲偟偰尨巕楩偺妶梡偑拲栚偝傟偰偄傞崅壏僈僗楩乮俫俿俿俼乯偵偮偄偰偱偟偨丅
傑偢丄擱椏揹抮幚梡壔愴棯偺僔僫儕僆傪徯夘偡傞偲丄俀侽侾侽擭偵偼栺俀侽侽枩倠倂梋偵憡摉偡傞俈俁壄棫曽暷偺悈慺僈僗偑昁梫偵側傝丄偦偺屻丄侾侽擭丄俀侽擭偺娫偵偼丄偦偺傑偨俆攞丄侾侽攞偺廀梫偵払偡傞偲偝傟偰偄傞丅悈慺偺惢憿朄偼偄偔偮偐峫偊傜傟傞偑丄揤慠僈僗偺悈忲婥夵幙側偳偱偙傟偩偗偺検傪嶌傝弌偡偙偲偼娐嫬柺偐傜傕戝偒側栤戣偱丄偦偙偵偙偺俫俿俿俼偺桳梡惈偑埵抲晅偗傜傟傞丅
俫俿俿俼偼巁壔僂儔儞傪巐廳偺僙儔儈僢僋偱暍偭偨恗扥掱偺棻巕傪崟墧偺摏偵媗傔偰擱椏朹偲偟丄偙傟傪廤傔偨楩怱偵壔妛揑偵晄妶惈側僿儕僂儉傪棳偡丄偄傢備傞僈僗椻媝楩偱偁傞丅捠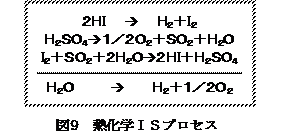 忢偼侾俇侽侽亷埲壓偱塣揮偝傟傞偑丄偙偺僔僗僥儉偼妀暘楐惗惉暔偑旐暍擱椏棻巕撪偵暵偠崬傔傜傟丄崟墧偼俁侽侽侽亷傑偱巊梡偑壜擻側偳丄埨慡惈偼嬌傔偰崅偄丅
忢偼侾俇侽侽亷埲壓偱塣揮偝傟傞偑丄偙偺僔僗僥儉偼妀暘楐惗惉暔偑旐暍擱椏棻巕撪偵暵偠崬傔傜傟丄崟墧偼俁侽侽侽亷傑偱巊梡偑壜擻側偳丄埨慡惈偼嬌傔偰崅偄丅
僿儕僂儉僈僗偼俋俆侽亷偲塢偆崅壏偱庢弌偝傟傞偺偱丄僇儖僲乕岠棪偱俈俇亾偲偄偆崅偄抣偑摼傜傟傞偑丄捈愙僞乕價儞傪夞偟偰偺敪揹丄悈慺惢憿丄奀悈偺扺悈壔側偳傪慻傒崌傢偣傟偽僩乕僞儖偺幚峴抣偱俉侽亾傕偺岠棪偵側傞丅偟偨偑偭偰丄敪揹僐僗僩偱偼倠倂摉偨傝係墌偲寉悈楩偺俆丏俁墌傛傝埨偔丄傑偨丄悈慺傕夵幙悈慺傛傝埨偄棫曽暷偁偨傝侾係丏俁墌偱偁傞丅
偙偺擬弌椡俁侽俵倂偺楩帺恎偼暯惉侾侽擭偵弶椪奅偵払偟偨偑丄嶐擭丄悽奅偵愭嬱偗偰傛偆傗偔俋俆侽亷偺擬弌椡偵払偟偨丅偦偺娫丄崅昳幙崟墧偺奐敪傪巒傔丄擱椏惢憿媄弍丄懴擬丒懴怘崌嬥僴僗僥儘僀倃俼偺奐敪側偳丄俫俿俿俼幚梡壔偵岦偗偰偺婎斦媄弍妋棫傗擬弌椡俇侽侽俵倂偺敪揹僔僗僥儉偺愝寁偲偦偺宱嵪惈傪峫椂偟偨夵椙側偳偵椡傪拲偄偱棃偨丅
堦曽丄悈慺惢憿偼暯惉俋擭偵侾噂乛倛倰偺婯柾偱幚尡偵惉岟偟偨屻丄尰嵼丄俁侽噂乛倛倰偺岺嬈婎慴幚尡偑傎傏廔椆偟偰偍傝丄嵟嬤丄堦廡娫楢懕塣揮偵惉岟偟偨偲偙傠偱偁傞丅
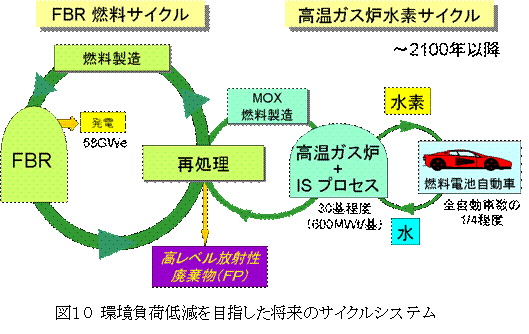 偪側傒偵悈偑帺敪揑偵暘夝偟偰悈慺傪惗惉偡傞偵偼係侽侽侽亷掱偺壏搙偑昁梫側偺偱丄偙偙偱偼儓乕僪乮俬乯偲棸墿乮俽乯傪弞娐暔幙偲偟丄俋侽侽亷晅嬤偱斀墳偑恑峴偡傞擬壔妛朄俬俽僾儘僙僗傪嵦梡偟偰偄傞丅斀墳幃偼恾俋偺捠傝偱丄偦傟偧傟嶰偮偺斀墳宯傪嶌偭偰楢寢偝偣偰偄傞偑丄偙偺曽朄偱堦廡娫楢懕塣揮傪惉岟偟偨偺傕悽奅偱弶傔偰偱偁傞丅
偪側傒偵悈偑帺敪揑偵暘夝偟偰悈慺傪惗惉偡傞偵偼係侽侽侽亷掱偺壏搙偑昁梫側偺偱丄偙偙偱偼儓乕僪乮俬乯偲棸墿乮俽乯傪弞娐暔幙偲偟丄俋侽侽亷晅嬤偱斀墳偑恑峴偡傞擬壔妛朄俬俽僾儘僙僗傪嵦梡偟偰偄傞丅斀墳幃偼恾俋偺捠傝偱丄偦傟偧傟嶰偮偺斀墳宯傪嶌偭偰楢寢偝偣偰偄傞偑丄偙偺曽朄偱堦廡娫楢懕塣揮傪惉岟偟偨偺傕悽奅偱弶傔偰偱偁傞丅
偙偺屻丄枅帪俁侽棫曽暷偺僷僀儘僢僩帋尡偵擖傞偑丄偦偙傑偱偼揹婥壛擬曽幃偱丄偦傟偑惉岟偡傟偽偄傛偄傛俫俿俿俼傪擬尮偵偡傞偙偲偵側傞丅偦偺応崌丄偙傟傑偱偺幚尡偱巊梡偟偰棃偨僈儔僗梕婍偼僙儔儈僢僋側偳偺岺嬈嵽椏偵愗傝懼偊偰峴偔昁梫偑偁傞偨傔丄怴偟偄栤戣偵憳嬾偡傞壜擻惈傕偁傞偲巚傢傟傞丅
俀侽侾侽擭崰偵偼俁侽俵倂偺俫俿俿俼偵枅帪栺侾侽侽侽棫曽暷偺悈慺惢憿僔僗僥儉傪愙懕偟偰丄幚梡壔僔僗僥儉偺娤揰偐傜宱嵪惈傪妋徹偟丄俀侽侾俆擭埲崀偵幚梡僔僗僥儉偺愝寁傪奐巒偡傟偽丄俀侽俀俆擭崰偐傜偺悈慺幮夛傊峷專弌棃傞梊掕偱偁傞丅
側偍丄偙偺楩偼憹怋偼弌棃側偄偑丄俵俷倃傪巊偆偙偲偵傛偭偰彨棃揑偵傕恾侾侽偺傛偆偵俥俛俼擱椏僒僀僋儖偲惍崌惈偺偁傞怴偟偄僒僀僋儖傪峔惉弌棃傞傕偺偲峫偊偰偄傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮摗揷婰乯